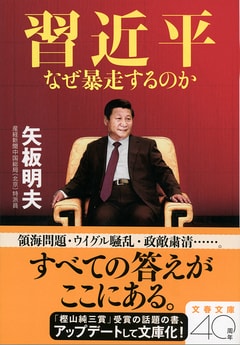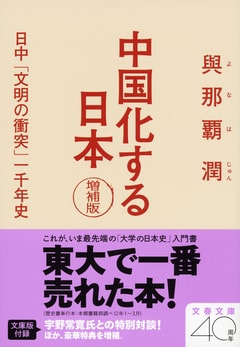第三は、私が新聞記者を辞し、最初に世に出した本となったことだ。本書と辞職には直接の関係はない。大半の内容は、辞職を全く予想していない時期に書かれたものである。だが、全くの偶然であるとも思えない。
中国で取材をし、日本に伝えなければならないことがたくさんあると感じながら、限られた紙面スペースや編集側の不理解に阻まれることがしばしばあった。日々のニュースは明快で、先入観にマッチしたものばかりがもてはやされ、じっくり背景を掘り下げ、深く考えるような記事は敬遠される。見たいものを見て「やっぱりそうなのか」と納得したい読者に迎合した報道である。その結果、各紙には横並びのステレオタイプで皮相的な報道が目立つようになる。
本書を執筆しようと思った大きな動機は、こうした現状を少しでも打破したいと思ったからであり、新聞報道のあり方に対する問題提起が含まれている。この意味で、記者辞職のタイミングと重なったことは、単なる偶然ではなく、必然的な巡り合わせを暗示していると言ってよい。
以上の私的な経験に基づく三点が本書のオリジナル性を支えている。その上で、中国を深く理解することの意義を強調したい。
中国を語る本は汗牛充棟のごとくあるが、日本人にとって有益なのは中国を鏡のように見て我が身を振り返ることである。2000年にわたる日中交流の歴史は、そうした視座を持つことによって初めて意味を持つ。中国を別世界の他者と見なし、見据えるべき現実から目をそらし、浅薄な崩壊論や脅威論を振りかざすことの愚は明白である。一時的な感情のはけ口にはなっても、国の将来にとっては害悪でさえある。
同じ漢字を用いながら全く異なる言語体系、思考方法を持つ両国は、かつて日本が中国を師と仰ぎ、近代以降は中国が日本に学んだ。侵略と冷戦による敵対を経験した後、日本と中国は援助する国、される国の関係を結んだが、現在は歴史上例をみない対等な相互依存の時代を迎えている。グローバル化の波は日中関係を覆い、2国間だけではなく国際情勢の中において考察されなければならない。
中国が米国と肩を並べる急速な大国化を進める一方、少子高齢化と経済の減速を抱えた日本は変化への対応に戸惑い、いわゆる「内向き」指向を強めている。中国からの訪日観光客はすでに日本人の訪中観光客を大幅に超えた。台頭する中国の現場から苦悩する母国を見ると、一層その危機感が強まる。資源を持たない日本は国を開くことによってしか繁栄できない。
国際秩序が大きく変化する時代だからこそ、日本はもっと外に目を向けることが必要だ。大国として台頭する隣国から目をそらす道は残されていない。中国に住む十数万人の邦人、2万数千社の日系企業は多かれ少なかれ同様の気持ちを共有している。現場に身を置き、大局を踏まえながら庶民のレベルまで視点を下げれば、必ずやメディアでは報じられていない新たな発見がある。それが本書にこめた私の思いである。