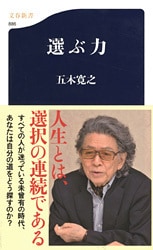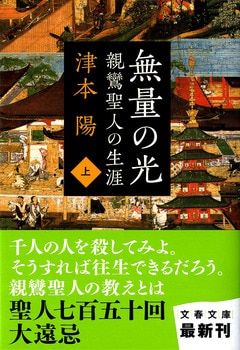後にも少しく触れるが作者五木寛之は音楽を言葉に変換し、それを読者に伝えることのできるほとんど唯一の作家ではないか。それは初期の「さらばモスクワ愚連隊」(昭41・6『小説現代』)での迫力にみちたジャズ演奏の描写で十二分に証明されているが、この雪の中での笛くらべも実に鮮烈で、喨々と鳴る音が読者の耳に響き渡ってくるようである。りん也こと高木凛の吹く金沢の風土や歴史と一体化したような力強い情感の笛の音と艶也の笛から流れ出る永遠に続くかと思われる不思議な音色。読者はいったいどちらに軍配を上げたらよいのか。
しかし見事なのはこのクライマックスだけではない。エンディングがこれをきわやかに受けとめて巧緻きわまりないのだ。
石段をのぼっていくと、夜の空が奇妙に明かるく見えた。もう雪はやんでいる。
「あかり坂は、あがり坂――」
そうつぶやきながら、凛は坂の石段を一歩ずつのぼっていった。
実はこの解説を書くためにノートにメモをしていたが、うっかりして最初にタイトルを「金沢あがり坂」と誤記していた。途中で気付いて「あかり坂」と直したのだが、このエンディングでの凛の言葉を読み、仰天せざるを得なかった。読者の錯覚をも計算に入れていたのだとしたら、五木寛之という作家はほとんど魔術師のような力をここで発揮しているのである。
先述したように再読、三読する価値は十二分にあるのではないか。
この非の打ち所が無い絶品「金沢あかり坂」の原形とも言うべき作品が「浅の川暮色」に他ならない。この作品もまた金沢という古都の花街に滲む女の情念をすくいあげ、読者の感傷的心根に注ぎ込むような物語となっている。主人公の森口は一流新聞社の事業部次長であり、金沢で加賀美術工芸展を開くこととなり、その挨拶もかねて十五年ぶりにこの地を訪れる。ただ、彼のこの地での三年間の記憶の底には罪悪感が潜んでいて、それが重苦しい不安定感として彼を襲うのである。大学卒業後、金沢支局に配属された森口は大学時代の友人でこの地の酒造会社の長男である早崎の案内で料亭を知る。そして、その料亭「しのぶ」の養女となっている高校二年生の柴野“みつ”と出会ったのである。この出会いと二人がしだいに親しくなっていく青春のプロセスは透明感の漂う金沢の風土を背景に美しく描かれていく。卯辰山、三八(さんぱち)豪雪、内灘海岸のニセアカシア……。そして残酷な仕打ちと非情な別離。芸者となった“みつ”の旦那候補として早崎やその伯父が名のりを上げているのをよそ目に見つつ、森口は彼女を捨て出世の夢を求めて金沢を去ったのだった。そして十五年後の今、かつてよく入りびたった鍋料理の「次郎」という店を訪ね、その女主人と語らいつつ想い出にふけるのだ。その女主人は“みつ”の遠い親戚にあたり、なぜか二人の仲を暖かく見守り続けてくれたのだ。そして今も“みつ”が現在どうしているかも語ろうとせず、森口を静かに回想に浸らせてくれるのである。“みつ”は今どうしているのだろうか。森口も訊ねようとしないし、女主人も語らない。もちろん語り手もいっさい明らかにしないわけで、全ては読者の想像力にゆだねられるのだ。何という鮮やかで巧緻なエンディングであることか。
私たち読者はこの二作品で金沢という都市の花柳界の雰囲気にどっぷりとつかり、日常的にはなかなか体験できない艶冶な気分を味わうのだが、それを吹きとばすようなドラマティックな作品が「聖者が街へやってきた」である。