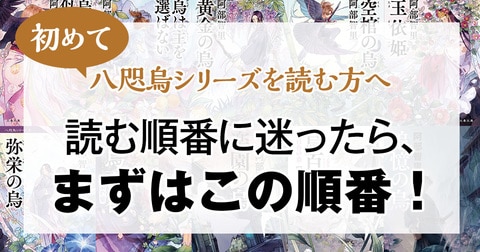NHKアニメ『烏は主を選ばない』完走記念! 八咫烏外伝「ふゆきにおもう」を全文期間限定無料公開
ジャンル : #エンタメ・ミステリ
2024年4月6日からスタートしたNHKアニメ『烏は主を選ばない』は、9月21日の放送をもって全20話の今シーズンを終了します。そして、実はこのアニメの冒頭とラストに大きく関わってくる、若宮と雪哉の本当の出会いが、阿部智里さんの原作「八咫烏シリーズ」外伝の「ふゆきにおもう」(『烏百花 蛍の章』所収)に描かれています。
アニメへのご声援に感謝し、「ふゆきにおもう」を期間限定(~2024年10月8日まで)で特別公開! 本編に登場する多彩な八咫烏たちひとりひとりを照射した、魅力的な短編がずらりと並ぶ「八咫烏外伝」を、この機会にご愛読いただければ幸いです。
八咫烏シリーズ 外伝
「ふゆきにおもう」
阿部智里
垂氷郷郷長の次男坊と三男坊が行方不明となったのは、まだ朝晩の風の冷たい、春先のことであった。
郷長屋敷では、そこで働く郷吏とその家族達が、一堂に会して食事をするようになっている。郷長の妻である梓は厨を預かる立場として、夕餉のために手ずから大量の菜っ葉を白和えにしている最中だった。
外に遊びに出ていた長男が「チー坊と雪哉がいなくなった」と駆け込んで来たのである。
長男の雪馬は十一歳になるが、チー坊こと末っ子の雪雉とは、六つも年が離れている。自立心の芽生えが著しい末弟が、かまいたがりの長男と喧嘩をした挙句、ちょっとした家出をしでかすのはよくあることであり、そんな時は、しっかり者の次男が迎えに行くのが常となっていた。
しかし雪馬は、二人が出て行ったのは昼前なのだと、必死に訴えたのだった。
「いくらなんでも遅すぎるよ。だってあいつら、昼飯にも帰って来なかったんだよ。俺、あちこち探して回ったけど、全然見つからなくって……」
どうしよう母上、と、焦る長男の懐からは、ひしゃげた形の竹皮が覗いている。おそらく中には、二人分の握り飯が入っているのだろう。
「大丈夫だから、そう慌てないの」
「でも」
「どうせ、どこかで昼寝をしているうちに、寝過ごしでもしたのでしょう。お腹を空かせて、きっとすぐに出て来るわ」
お方さま、と、話を背後で聞いていた女が控えめに声をかけてきたので、梓は軽く頷いた。
「でも、そうね。さすがに遅すぎるから、腹ごしらえをしてもまだ戻って来ないようなら、みんなで探しに行きましょう。帰って来たら、きちんと仲直りするのよ」
いいわね、と視線を合わせて言えば、うん、と不安げに雪馬は頷いたのだった。
――しかし、いくら待っても、二人は戻って来なかった。
「チー坊! どこにいるんだ」
「坊ちゃーん。聞こえたら、返事しておくれ!」
一足先に探しに出た梓と女達の後に、夕飯を終えた郷吏達も加わってあちこちを見て回ったが、それに応える声は、一向に聞こえてこない。
山城となっている郷長屋敷のふもとには、畑とそれを預かる郷民の集落、陸路を行く旅人のための宿がある。日中、下の畑に出ていた者は、郷長家の名物兄弟は目にしていないと口を揃えた。
すでに、とっぷりと日は暮れている。
日が出ている間は暖かかったものの、まだ、風の中には冬の名残が色濃い。首元と足首のあたりから冷気が忍び寄り、いよいよ、薄着のまま出かけた子ども達の身が危ぶまれた。
「お前は一度、屋敷に戻って何か口にしてきなさい」
声を嗄らして歩き回る梓に声をかけたのは、夫であり、郷長である雪正であった。
「でも、あなた」
「私達は食事を済ませているが、お前はろくなものも口にせずに出て来ただろう」
「私は大丈夫です。こんな時に悠長に食事なんてしていられません」
「お前は大丈夫かもしれんが、もう、雪馬が限界だ」
ちらりと雪正が目をやった先では、もはや声も出ない様子の雪馬が、半泣きになりながら郷吏の後ろを付いて回っている。
「このままだと、長丁場になるやもしれん。女達には、夜食を作るように言って屋敷に戻した。お前も、雪馬を連れて戻るのだ」
そこでようやく梓は、先ほどまで行動を共にしていた女達の姿が見えなくなっていることに気が付いた。
「……分かりました。一旦、雪馬を屋敷に帰して参ります」
引き下がってはみたものの、喉に物が通る気はしない。
弟達が見つかるまで探すと言っていた長男も、日中から歩き回っていたのだから、やはり疲れていたのだろう。ちょっと休むようにと連れて行った屋敷の軒先で、こてんと小さくなって眠ってしまった。誰かに雪馬を見ていてもらい、自分はもう一度探しに出ようと厨に向かう。
引き戸を開けようとして、ふと、聞こえてきた声に手が止まった。
「チー坊はともかく、あの次男坊が、迷子になったりするもんかね。こんなに探して見つからないってことは、自分の意志で出て来ないんじゃないの」
「どういう意味だい」
「案外、こちらが必死で探しまわっているのを見て楽しんでいるかもしれないってこと」
あの子は捻くれているからね、と言う声は、どう聞いても、次男に対し好意的には聞こえない。
扉の向こうで、おやめよ、とたしなめる声がする。
「本当の話じゃないか。お館さま達の前ではいい顔をしているけれど、うちの子を殴ったのもあの子だよ」
「そりゃ、あんたんとこのが坊ちゃんに失礼なことを言ったからだろう」
自業自得だよ、と呆れたような反応があるが、梓の鼓動は早くなっていくばかりだ。
雪馬や雪雉はともかく、あの次男坊がそんな喧嘩をしていたなんて、今まで一度だって聞いたことがなかった。穏やかで、優しくて、兄と弟が喧嘩している時だって、必ず仲裁に回るあの子が、まさか。
梓が聞いているなどと知るべくもない女は、日ごろの鬱憤を晴らすかのようにまくし立てた。
「でも、お方さまのお子はどっちもいい子なのに、あの次男坊だけ捻くれているのは、やっぱり母親が違うせいだよ。喧嘩のあと、一度だって謝りもしないんだから」
「いいかげんにおしったら。あんたが家でそんなことばっかり言うから、又聞きした子ども達が坊ちゃんにつっかかるんじゃないか」
「それで返り討ちにされてちゃ世話ないやね」
軽やかに起こった笑声にも、不機嫌そうな声は変わらない。
「お方さまもお館さまも、どうしてあいつを手元で育てる気になったんだか、てんで不思議でならないね。さっさと中央に養子に出しちまったほうが、お互いのためだったのにさ」
冬木さまだって、きっと恨みに思っていることだろうよ、と。
――もう、聞いていられなかった。
勢いよく戸を開けば、それまでこちらに気付いていなかった女達が、ぎょっとした面持ちで口をつぐむ。
「お方さま」
先ほどまで悪態をついていた女の顔にも、しまった、と露骨に書いてある。
息子のためにも、何か言ってやらなければならない気がするのに、怒りとも、悲しみともつかない何かで胸がいっぱいになり、結局、口をついて出たのは、全く関係のない言葉だけであった。
「……あちらで、雪馬が寝ています。私はこれから出ますので、誰か、見てやって下さい」
早口で告げ、踵を返した瞬間、「梓さま」と狼狽した声が背中にかけられたが、とても、振り返る気にはなれなかった。
自分が、雪馬や雪雉と分け隔てなく育てたつもりの次男――雪哉の今は亡き母親は、かつて自分が仕えた、大貴族の姫君であった。
***
二人が出会ったのは、今から二十年ほど前、梓が七歳、冬木が十三歳の時のことだった。
東西南北の四大貴族のうち、北領を治める北本家二の姫であった冬木は、生まれつき体が弱く、そう長生きは出来ないだろうと言われていた。
一方の梓は、父親こそ長く北家に仕えていた一族の出であったものの、母親は、北家とは系列を異にする東家方の中流貴族である。梓自身、中央にある母方の屋敷で育てられたため、それまで、北領にある領主のお屋敷から出ることのない冬木とは、顔を合わせたことがなかった。
新年の挨拶にと連れて行かれた先で、今日は姫の調子がいいからと、初めてのお目通りがかなったのだった。
「あなたが梓ね」
そう言って寝台から身を起こし、脇息にもたれた冬木は、記憶に残りにくい面差しをしていた。
顔立ちそのものは父親譲りなのだろうが、屈強な体つきと闊達さによって堂々とした印象を持つ父とは違い、その手足も首も異様なくらいに細く、表情は暗く沈んでいた。小さく開けた口からは、ひゅうひゅうと常に苦しそうな呼吸音が漏れており、やわらかそうな髪の毛は寝癖が直らないまま、血の気のない頬にはり付いている。
型どおりの言葉を交わした後、唐突に、冬木は梓に質問を投げかけてきた。
「ねえ、あなた。あたくしのお姉さまは、若宮殿下に入内できると思う?」
当時、冬木の姉であり、北家一の姫である六つの花は、日嗣の御子の正室候補として噂されていた。
冬木に同じことを訊かれた他の者は「もちろん、お姉さまが入内できるに決まっています」と答えたらしいのだが、この時、梓はじっくりと考え込んだ後、こう答えたのだ。
「中央のおやしきでは、東の人たちが、東家の姫さまがお嫁いりするだろうと言っていました。きっと、西のおうちは西の姫さまが選ばれるだろうと思っているでしょうし、それは南のお家もいっしょだと思います。だから、本当はどうなるのか、私には分かりません」
それを聞いた冬木は満足げに微笑して、「気に入ったわ。あなた、今度からあたくしに付きなさいな」と命令したのだった。
梓達からすれば青天の霹靂であったが、名誉な話には違いない。北家夫妻が乗り気だったこともあり、すんなりと、冬木付きの女童となることが決まったのだった。
伝え聞いた冬木の評判は、決して芳しいものではなかった。
下の者に対して思いやりがなく、意地が悪いと盛んに噂されており、彼女に仕えることになったと伝えた者には、「機嫌を損ねたら、すぐに追い出されてしまうぞ」と半ば脅すように言われてしまった。
実際、一緒に過ごしてみると、拍子抜けするくらい冬木は梓に対して親切であったのだが、一方で、その前評判に頷ける部分もあったのだった。
北家の姫ともなれば他にいくらでも仕えたいと希望する者はいただろうに、どうして自分を選んだのかと聞いた時のことだ。
「あたくし、馬鹿は嫌いなの」
さらりと毒づいた彼女の目は、普段の様子とは打って変わり、冬に張った氷のごとく青白い光に満ちていた。
「あの子達が仕えたいのはね、体が弱くて可哀想な主家のお姫さまであって、あたくしではないの。主の意向に背くことは絶対にないから、自分の意志で口を開くこともない。あれは馬だといえば、鹿さえも馬であると頷く者ばっかりよ」
ろくに会話も出来やしない、と、そう言う声に温度はなかった。
「この先、あたくしは長く生きられるわけではないのだもの。どうせなら、気に入った子と、楽しく過ごしたいじゃない。何も考えていない馬鹿の相手で時間を無駄にするなんて、まっぴらごめんよ」
――屈託なくそう言う彼女には、大貴族特有の傲慢さがにじみ出ていた。
冬木は貴族の姫として求められる以上に読書を好み、盤上遊戯を得意としていた。一読した書籍の内容は絶対に忘れなかったし、すごろく、将棋、囲碁、カナコロガシ、武人達が使う兵法の盤上訓練に至るまで、彼女と対戦して、勝てた者はいなかった。
たまに、現役の武官や、朝廷で働く官人が見舞いがてらに相手になってくれることもあったが、そんな時ですら、彼らは一様に「いやあ、姫さまはお強い」と口を揃えるのである。
多くの者は、北家のご機嫌取りのために、彼らはわざと負けたのだと信じて疑わなかった。だが梓は、「手加減してやったんだ」と裏で嘯く彼らのほとんどが、実際は対戦中に冷や汗を浮かべている姿を目にしていた。
また、中央の土産話を持ってくる客人は少なくなかったので、冬木は決して多くはない言葉の内から、梓が思いもしないような見解を見せることもしばしばであった。
「北家は政治下手よ。入内だけがお家の繁栄につながると考えているんだから、本当に救いようがない。これだけ軍事に長けているのだから、その気になれば宗家にとってかわることだって容易だろうに、わざわざ花街から正妻までとってしまうのだから」
実の両親のことさえも、まるで他人ごとのような顔をして彼女は語った。
「知っている? 美人だったら入内出来るだろうって親戚連中がうるさいから、お父様は中央花街で一番の遊女だったお母様を、わざわざ正室に迎え入れたのよ。上は、姫の顔も性格も気にしてなどいないでしょうに……父も母も兄も姉も、あの馬鹿な親戚達と一緒になって、おままごとに参加出来ないあたくしを哀れんでいるの」
馬鹿みたい、と冬木は吐き捨てる。
確かに、冬木の両親や兄姉は、冬木の心情を理解しそこねている部分があった。使いもしない雛人形やら簪やらを送ってくるあたり、何を冬木が喜ぶかも分かっていないのは明らかだったが、その反面、「冬木は一体何を好むのか」と、梓がこっそり呼び出されることも度々であった。本人が思うほど、両親は冬木に冷淡ではなかったと思うが、彼女はすっかり、自分の身内に絶望していた。
「もし、あたくしが男だったら――もしくは女を捨てて、男として官人になれるくらい体が丈夫だったら、北家を山内の頂点にすることだって出来ただろうに」
それをたまたま耳にした侍女などは「出来もしないことを」と嫌な顔をしていたが、あながち夢物語などでなく、冬木だったら、本当に朝廷を牛耳ることだって可能かもしれない、と梓は思っていた。
これだけ才気にあふれる人ならば、自分の思い通りにいかない体はさぞやもどかしいだろう。そうと周囲に認めてもらえないというだけで、彼女はひどく賢かったし、そしてそれゆえに孤独だったのだ。
「……この体では、どうせ子どもだって望めないのだもの。あたくしはきっと一生、ここで何にも出来ないまま、ひとりぼっちで死ぬんだわ」
入内するだろう姉の話で盛り上がった客人が去った後、彼女がぽつりと漏らしたのは、ささやくような諦めだった。
華やかな着物と中央のめずらかなお土産、それに似合わない大量の書籍にうずもれた小窓から、世界はどんな色をして見えていたのだろう。
いつの間にか梓の中には、鬱屈した彼女の数少ない理解者は、自分なのだという自負心が生まれていた。
自分の両親や兄姉に対してすら冷ややかな態度をとった冬木は、一度でも自分が心を許した者や、無垢なものに対しては、驚くほどに思いやり深かった。
迷い込んできた小さな猫や、抱えられてやって来た赤ん坊を見る時など、ごくまれに、ものやわらかに微笑むことがあったのだ。そんな時、ふふふ、と胸に響かないように笑う声は春先の風のようで、梓には何より好ましかった。
確かに、冬木は捻くれていて、一筋縄ではゆかぬ御仁ではあったけれど、決してそればかりの女ではなかった。梓は、彼女が誰に対しても引いている一線を越える一人目になりたくて必死だったし、そんな心を敏感に察した冬木も、まるで、自分の胸元に来ようと、必死で裳裾に爪を立てる仔猫を見る眼差しで梓を眺めていた。
かわりばえはしなかったが、穏やかで、あたたかな日々だったと思う。
――転機が訪れたのは、冬木が十八、梓が十二になった頃のことである。
中央に出ていた冬木の兄、玄喜が、仲良くなったという友人を連れて北領に帰って来た。
この友人達というのが、まあ、どうしようもなく腹立たしい連中だったのだ。
「いやあ、姫様もお可哀想に。こんなところで閉じこもるしかないなんて」
「中央はいいですよ。中央の話をして差し上げましょう」
そう言って彼らは、自分の一族が中央でいかに財を築き、今はどれだけ豊かで華やかな暮らしをしているのかを、こちらの反応には全く頓着することなく、延々と語って聞かせるのである。
これには参った。
むっつりと黙り込んだ冬木に代わり、梓はそれとなく中央の政治に水を向けたが、そんなことよりも、とすぐに自分の贔屓にしている反物屋が作り出した夏の意匠の話になってしまうのだ。
「……衣服ばかりが派手であっても、中身がなければ意味がないのでは?」
とうとう御簾越しに、冬木が嫌味っぽい一言を投げかけたが、それでも全くへこたれないのだから、ある意味天晴れではあった。
「ええ、ええ、まさにその通り。しかし、中央で貴族として認められるには、見た目もまた大事なのですよ」
中央の娘達も衣服には汲々としているし、それを見る目も肥えているからおしゃれするのも大変で、その点、そういった俗世とは切り離された冬木さまは、清らかなお心をお持ちのようでうらやましい、とまでのたまった。
なんとか話を切り上げて追い返したものの、あれがしばらくこの邸に逗留するのかと思うだけで、憂鬱になりそうだった。
「二度と近づけないで」
「私だって、お相手するのはごめんです」
彼らは、北家に連なりはするものの、すでに本拠地を中央に据えている連中である。北領に来たのも初めてであり、遠乗りにでも出ればこちらに来ることもないだろうと思っていたが、その見通しは甘かった。
彼らはせっかく地方に来ているというのに、領内を見て回ることもせず、翌日から「中央貴族の嗜みだから」と、蹴鞠を始めたのである。
「あいつら、本当に馬鹿なの!」
「全くです」
冬木の部屋に面した庭からは、ひっきりなしに吞気な笑い声が聞こえている。
さっさと帰ってくれればいいのに、と梓が言いかけたその時だった。
「あぶないっ」
切羽詰まった声に、何事かと振り向いた次の瞬間――何か、ひとかかえもあるような塊が御簾を吹き飛ばし、勢いよく部屋の中に飛び込んで来たのだった。
梓と冬木が悲鳴を上げる中、それは壁に跳ね返り、二階棚の上にあった鏡を落とし、床を跳ねまわった。
何が起こったのか分からないまま、思わず冬木と抱き合うようにして竦み上がる。
――どんどん、と音を立てて転がったそれは、蹴立てた痕のある白い鞠だった。
二人して唖然としていると、御簾がなくなった欄干の向こうから、焦った顔がこちらをのぞき込んだ。
「怪我はないか!」
光の中に現れたのは、日に焼けた、精悍な面差しの青年だった。
化粧をしているわけではないのに、眉が描いたようにはっきりとしていて、その眼差しはまぶしいほどにまっすぐだ。たくましい体つきをしており、筋肉の綺麗に盛り上がった二の腕が、めくれあがった袖から見えている。
我に返った瞬間、自分の背後に冬木を庇うように立ち、梓は叫んだ。
「この方をどなたと思っておられるのです! おさがりなさい」
一瞬目を見開いた青年は、自分が前にしているのが誰であるかを悟ったのか、途端に顔色を変えてその場にひれ伏した。
「これは、大変失礼つかまつりました」
梓は慌てて振り返り、冬木の無事を確かめた。
「冬木さま、冬木さま。お怪我はありませんか」
しかし梓の主は、魂をどこかに置き去りにしたかのような顔つきで、地面で跪く青年を見下ろしている。
「冬木さま?」
不審に思って名を呼べば、ハッと目を瞬いた。
「ああ、大丈夫。あたくしなら、大丈夫よ」
「良かった」
安堵の息を吐いたのち、眦を吊り上げ、梓は青年に向き直った。
「一体、何があったのです」
「本当に、申し開きのしようがございません。あの、私が蹴った鞠が、こちらに……」
見れば、青年のはるか後方では、例の中央貴族たちが、小さくなってこちらの様子をうかがっている。
梓は、先日の無礼の件も含め、もう我慢がならないと思った。
「これは、お館さまにもご報告します」
追って沙汰を、と言いかけたところで「お待ちなさい、梓」と冬木がそれを制止した。
「御簾はこんな風になってしまったけれど、誰も怪我もしなかったし、鏡も割れていないわ。ここは、穏便におさめましょう」
いつもの彼女らしからぬ、か細い声である。
すっかり小さくなった冬木を怪訝に思いながら「冬木さまがそうおっしゃるのなら……」としぶしぶ引き下がった梓は、それを聞いた青年が、ほっと安堵の息を漏らすのを聞きとがめた。
「冬木さまがお許しになったとしても、これは大変に、礼を失した行為です。内々でことはおさめますが、二度とこんなことのないよう、くれぐれも注意なさって下さい」
「はい、それは勿論です」
真摯に頷く青年の面差しに、おや、と梓は気付いた。
こうして見ると、先日間近で見た連中のなまっちろい顔とは、似ても似つかない。
「あなた、中央の者ではありませんね。どこの、どなたです?」
「申し遅れました。自分は、垂氷の雪正です。垂氷が郷長が嫡男、雪正でございます。本日は父と共に参上したのですが、そこで、彼らに誘われまして」
「ゆきまさどの……」
ぼんやりとした声のもとを見やって、梓は仰天した。
冬木は、梓が今までに見たことのない顔をして、頬を真っ赤に染めていたのだった。
その夕方のことである。
すでに日は落ちて、あたりはすっかり暗くなっていた。
「梓殿」
冬木の茶器を下げようと廊下に出た梓は、庭先から名前を呼ばれてびっくりした。
「昼間の」
「はい。先ほどは大変失礼をしました。垂氷の雪正です」
「今度は、一体何のご用ですか」
「改めて、お詫びに参りました。あの、喜んで頂けるかは分かりませんが、これを」
そう言っておずおずと差し出されたものを見て、梓は返答に困った。
――さて、なんと言ったらよいものか。
腹立たしさに任せて、もう顔を見せるな、と言ってやりたい気持ちもあったが、冬木の気持ちを思い、それはぐっと我慢した。
「……垂氷の嫡男ともあろう方が、こんな、こそこそと庭からいらっしゃるなんて」
「それはその、お恥ずかしい限りです」
「あちらから、ちゃんと上がって来て下さいませ。冬木さまにお通しいたします」
昼間からすっかり物静かになってしまった冬木は、雪正が来ていると聞くと、小さな悲鳴を上げた。そして、まるで童女にでもなってしまったかのような顔で、梓に縋ってきたのだった。
「どうしよう、梓。あたくし、あの、変な格好ではないかしら」
冬木の猫っ毛はひろがりやすく、くせがつきやすい。慌てて髪を押さえだした冬木に苦笑しつつ、梓は櫛で軽く整えてやった。
「大丈夫ですよ。それに、あちらは謝罪に来ているのですから、冬木さまは堂々としていらっしゃればよいのです」
きっと喜ぶだろうとは思ったが、この狼狽の仕方は意外だった。
そうして、御簾越しに対面した雪正は、最初に潔く頭を下げた。
「昼間のことは、本当にすみませんでした。改めてお詫び申し上げます」
それはもう良いのです、と答える冬木の声は消え入るように弱々しい。そのまま何も言えなくなってしまった冬木に代わり、梓はさりげなく助け舟を出した。
「でも、どうしてあんなに強く蹴られたのです。雪正殿は、蹴鞠をなさったことがなかったのですか」
「いえ。そういうわけではなかったのですが。彼らが、物知らずの田舎者に中央流の作法を教えてやろうという態度だったので、つい腹が立って……」
心底恥じ入った風ではあったが、大体何があったのかは察せられた。しかも、その気持ちは大変よく分かるものだったので、梓も厳しい態度をわずかに和らげた。
「それは、まあ、同情いたします」
「姫さま方には、ご迷惑をおかけしました。詫びとはいえませんが、どうぞこれをお納めください」
そう言って雪正が背後から取り出したものを見て、冬木が息を吞んだ。
薄暗がりの中、ゆったりとした呼吸のような明滅は、鬼火灯籠よりも淡く、鮮烈な色をしている。
雪正の用意した詫びの品は、美しい緑色に光る、不思議な棒状の何かだった。
「それは、何なのです?」
「蛍です」
「中に蛍がいるのは分かりますが……でも、それを入れているのは植物でしょう」
「姫はご存知ないかもしれませんが、これは、葱坊主です」
「ねぎぼうず!」
その、幻想的な見た目にそぐわぬ間の抜けた名前に、冬木は目を丸くした。
「ほたるぶくろは見たことがあるけれど、葱とは、また……」
こらえきれなくなったように、冬木は笑い始めた。
「いいものを見せて頂きました。とても可愛いし、素敵だけれど、わたしは、十分楽しみました。だからどうか、蛍はここで逃がしてやってください」
「分かりました」
蛍が逃げないようにしていた栓を抜いてやると、中にいた蛍はしばしそこでうごめいた後、ふうっと、吐息に吹かれたかのような軽さで、そこから外へと飛び立っていった。
帰って行く雪正を見送る冬木の横顔は、今まで梓が見たことのないもので、こんな顔も出来たのか、と新鮮に思った。なんとなく寂しい気持ちもあったけれど、そんなことどうだっていいと思えるほどに、胸が締め付けられてならなかった。
――なんて、可愛らしい方なんだろう。
なんとかしてやりたいと、心からそう思った。
だから北家の当主夫妻に、それを告げたのは梓だった。
冬木さまに好いたお人がいる、と。
縁談は、とんとん拍子に進んでいった。
娘が見初めた相手だからと、北家当主は張り切ったし、隠居を望んでいた垂氷郷の郷長も、北家という強力な後ろ盾を確保出来る、息子への冬木の輿入れには乗り気だったのだ。
「ありがとう、梓。全部、あなたのおかげよ」
垂氷へと向かう冬木は、幸せに満たされて美しく、自然と、梓の目からも涙がこぼれた。
「冬木さま。どうぞ、お幸せになって」
垂氷郷との折り合い上、梓が、侍女として付いていくわけにはいかなかった。
そうして、冬木は雪正の正室として垂氷郷へと嫁ぎ、梓は、中央づとめをすることになったのだった。
あなただったらすぐに嫁ぎ先も見つかるでしょう、という冬木の言とは逆に、梓はなかなか縁談には恵まれなかった。
いつか冬木が言った通り、結局、冬木の姉は入内せず、北家系列の貴族のもとに嫁ぐことになった。玄喜のもとにも息子が生まれ、梓が中央の北家の朝宅で、その子ども達の面倒を見ていた頃。
北家当主の妻から、にわかには信じられない話を持ちかけられた。
「――私を、垂氷郷郷長の側室に?」
すでに、冬木が垂氷に嫁いでから、五年の月日が経っていた。
あれから何度か文のやり取りをしていたのに、近頃は、その返信がなくなっていた。いよいよ、体の調子が悪いのかと危ぶんでいたところだったのだ。
冬木の実の母である北家当主の妻、お凌の方は、真剣な眼差しで梓に訴えた。
「垂氷で、冬木は窮しているのです。いまだ、垂氷の郷長にはお子がないまま。それも自分のせいだと思えば、肩身が狭くてならないのだそうです」
続けざまに、どうか吞んでやってくれと、北家当主自らが足を運んできた。
「縁談を進めた我々としても、どうにかしてやりたいのだ。冬木は、側室にするならば、せめて梓に、と言っているらしい」
「冬木さまが、本当にそうおっしゃったのですか」
「ああ、そうだとも」
北家当主自ら頼まれては、梓に、選択肢などあろうはずがない。
――違和感はあった。
冬木は、雪正に心底惚れ込んでいた。それなのに、自分から側室が欲しいなどと言い出すだろうか、と。しかし、あの聡い冬木のことだ。葛藤はあったとしても、これからの垂氷郷を思い、後継者の問題を考えたならば、梓を側室に選ぶこともあり得ない話ではないと思ってしまった。
改めて文を送ったが、やはり、返信は来なかった。
中央から、北家の本邸に呼び戻された梓の元に、とうとう、雪正が訪ねてきた。
垂氷の若き郷長は梓に対し、きわめて誠実だった。
「跡取りがいないせいで、冬木は、垂氷でつらい立場にあるのだ。なんとかかばいながらここまで来たが、心労が、最近は体にまでたたっている。冬木はその実、家の采配も出来ない状態なのだ。どうか、冬木を助けるつもりで、側室になってはもらえんだろうか」
側室という形にはなってしまうが、冬木と同様に大切にするから、と。
「一度、冬木さまに会わせては頂けませんか」
「今は、体の調子が良くないから難しい。だが、そなたがうんと言ってくれれば気鬱も治り、じきに会えるようになるだろう」
半ば、雪正にほだされるようにして、梓は雪正の妻になった。
垂氷郷で、居室を新たに増築するということで、しばらくの間、梓は北家本邸に留め置かれた。最初に言った通り、雪正は熱心に通って来て、そして拍子抜けするくらい、梓はあっさりと懐妊したのだった。
北家当主夫妻はこれを、自分の娘のことのように喜んだ。
「冬木も喜んでいるわ」
そう言ったのは、お凌の方だった。
「本当でしょうか……」
いまだ、冬木と言葉を交わすことの出来なかった梓は不安だった。ふくらみの見えない腹を撫でさする梓の言葉を、しかしお凌の方はほがらかに笑って否定したのだった。
「もちろん、嬉しいに決まっています。今はあの子の具合が良くないようだけれど、生まれた頃には、顔を見せに行ってあげましょう」
名前に動物が入っている男子は、健康に育つという。
数月の後に生まれた子は、神馬にあやかり、雪馬と名付けられた。
未だ北家本邸で留め置かれたまま、梓は初めての子を育てることになった。雪正は熱心に雪馬と梓のもとに通ってくれたし、北家の方で羽母も手配してくれたので、子育てについての不便は感じなかった。ただ、雪馬は人の姿をとれるようになってから夜泣きが激しく、泣いていない隙を見計らって休むこともしばしばであった。
その日も、雪馬の隣で横になって昼寝をしていたのだが、泣き声とは違う物音に、ふと、目を覚ました。
何やら、外が騒がしい。
「何かあったの」
「行ってはいけません、梓さま」
侍女は固い表情で止めたが、聞こえてくるのは、甲高い女の声と、それに混じる――苦しそうな、咳の音だった。
「まさか、冬木さまがいらしているの」
息子を抱えて廊下に出ると、同じようにそちらに向かおうとしていたお凌の方が、その行く手を遮った。
「梓。ここは、任せておきなさい」
「ですが」
「いいですね。これは命令です。お戻りなさい」
毅然とした態度のまま、お凌の方は外へ出て行ったが、梓は侍女に促されても、その場に留まり続けた。
「この、裏切り者! 絶対に、絶対に許さないぞ」
――あまりの剣幕に、足が動かなかった。
だがそれは、どう聞いても、冬木の声に違いない。
「何ですか。騒々しい」
呆れたように言ったお凌の方の口調は、まるで聞き分けのない子どもに根気強く話しかけるようだった。
「落ち着いてお聞きなさい。いいですか、冬木。こうなったのは、お前の怠慢です。本来であれば、お前の方から、側室を持つように提案すべきだったのですから」
郷長の妻として最低限のつとめも果たせないのなら、他の者にそれをしてもらうしかないではありませんか、と。
困ったような母親に、冬木は血を吐くような苦鳴を上げた。
「ふざけるな! だったら最初から、あたくしを嫁になどやらなければよかっただろう!」
「それとこれとは、別の問題でしょう。全ては、お前を思ってのこと。垂氷で良い奥方になって欲しいと願っていたというのに、恩を仇で返したのは、お前の方ですよ。この上、側室を認めないなどと、道理の通らないことを言うものではありません」
「何が道理だ。何が、あたくしを思ってのことだ。全部、自分の体面が悪いからだろう。みんなみんな、あたくしを馬鹿にして……あたくしは、お前達の人形なんかじゃない!」
雪馬を抱きしめる手が震えた。弁解したいのに、直接会って話したいのに、聞いたことのないような冬木の怒声が恐ろしくて、どうしても出て行けなかった。
「あたくしは、許さないわ。ええ、死んでも許さない。絶対に!」
絶叫を最後に、咳き込む声が激しくなり、不意に、その音も途切れた。
どうやら、あまりの激昂に、血が頭にのぼって倒れたらしい。
冬木を別棟に連れて行くように下女に指示を出したお凌の方は、凍りついた梓に気付くと、苦笑してみせた。
「あの子には困ったこと。いつまで経っても、自分のことばかりで……。これは、冬木を甘やかしてしまった、あたくしの罪でもあるのでしょうね……」
だから、冬木が言うべきだったことを、この母が代弁したのだと、お凌の方はため息をついた。
「冬木さまが、私を側室にと望んだというのは――嘘だったのですか」
お凌の方は、それには答えなかった。
「厳しいと思えるでしょうが、仕方なかったのです。あの子の立場を思えば、こうするしかありませんでした」
もともと遊女であったこの人は、かつて、ひどく苦労したと聞いている。娘二人と跡継ぎを生むことによって、ようやく貴族として認められた節すらある。
ただでさえ、冬木は侍女たちの間で評判が悪かった。
貴族の妻として認められるには、配下の女達のまとめ役として、家をきりもりすること、そして、跡継ぎを生むことの二つが必要だ。お凌の方は、娘がそのどちらも放棄した以上、わがままを通させるわけにはいかないと考えたのだろう。
果たしてこれは、親心なのだろうか? 自分が嫁いできたばかりの頃と、似たような境遇に追い込まれた娘に対する思いやり?
いや。きっと、違う。
「好いた殿方と一緒になれただけで、何よりの僥倖というに――一体あの子はこれ以上、何を望むというのでしょうね」
静かに言い切ったお凌の方に、もしかしたらこの方は、北家当主のほかに、心から愛しいと思った殿方がいたのかもしれないと、痺れたような頭で梓は思った。
「梓、あなたは何も気にせずともよろしい。ただ、雪馬を良い子に育てなさい」
いいですね、と。
思いやり深く言われた梓は、泣き出した雪馬を抱きしめたまま、何も言うことが出来なかった。
どうして嘘をついたのかと詰め寄った梓に、雪正はとうとう本音をこぼした。
「私は、あれを妻にと望んだことは、ただの一度だってない」
「どういうことです……?」
「北家当主よりそれを言われる前に、すでに縁談があった。そなたとの縁談だ」
私は最初から、そなたを妻にと望んでいた、と、苦しい声で雪正は言った。
「そこに、割り込んできたのが冬木だ。最初は断った。そなたがいいと何度も言った。郷長の後継者問題の最中にあった私が、渡りに船とばかりに縁談に飛びついたとでも思っていたのか? 私は、実力で認められたいと思っていた。妻の家の威光を借りるなんてまっぴらだ。縁談は断ったのに、北家当主自らに頭を下げられては、それを突っぱねることは出来なんだ」
娘はそう長生きは出来ないから、せめて、と訴えたらしい。
「その代わり、しかるべき時が来たら、北家当主から側室には必ずそなたを推薦すると、そういう約束だった」
しばらく、ぱったりと縁談が途絶えたことを思い出し、梓は震えた。
「あなたは――まさか、それを言われて、私が喜ぶとでも思ったのですか」
雪正は一瞬ひるんだが、それでも、己の言を翻すことはしなかった。
「……最初から、そなたが私の妻になるべきだったのだ。冬木だって、内心では私を下に見ている。出世のために自分を利用せよとまで言うのだから。どれだけあの姫は、私を馬鹿にすれば気が済むのか!」
「違う。違うのです」
それは、不器用な彼女なりの献身だったに違いない。
「とにかく、私が最初から愛していたのは、そなただった。冬木ではない」
「お願いですから、どうかそれ以上、おっしゃらないで!」
――冬木は頭の良い女だった。
雪正の思いに気付かなかったはずがない。どれだけ悔しく、恨めしかったことだろう。
みんながみんな、冬木のためと言いながら、結局のところ、誰も冬木がどう感じるのかなどと一度も思い至らないまま、悪びれもしていないのだ。
これでは、冬木の気持ちはどうなるのだと言いかけ――彼女の心を踏みにじった筆頭が、この自分なのだという事実に愕然となった。
垂氷に連れ戻された冬木は、死んでも構わない、命に替えても子どもが欲しい、と怒り狂ったという。
誰も、冬木を止めることは出来なかった。
両親の制止も、雪正の説得も、全く何の意味もなさなかった。しまいには、己の首に刃を向け、半ば脅すような形で寝所を共にしたという噂まで聞こえたが、真実は、冬木の話になるたびに苦い顔をする雪正にしか分からない。
そして、ひとつの卵を産み落とすと同時に、冬木の体は限界を迎えた。
誰も、雪正を責めることをしなかった。北家当主でさえもだ。
羽母のもとで孵った卵から生まれたのは、男の子だった。
垂氷郷郷長、雪正の次男坊、雪哉の誕生であった。
***
「そう心配するな、梓。皆が探している。きっと、雪哉も雪雉も、すぐに見つかるさ」
蹌踉とした足取りで郷長屋敷から戻ってきた妻を安心させようとでも思ったのか、雪正は軽い口調で言った。
「こうなると、本当に雪哉の家出かもしれないぞ」
あいつだったらやりそうだ、という軽口は、今はどうあっても逆効果だった。
「あなたは、どうしてそんなに雪哉に冷たいのですか。あの子が可愛くないのですか」
泣きそうな声で言われ、雪正は驚いたように目を見開いた。
「馬鹿を言え。もちろん、雪哉も私の息子だ。可愛いに決まっている。だが、時々、我が息子ながら、何を考えているか分からない眼をしている時があるから……」
口ごもる夫に、梓は雷に打たれたように悟った。
――雪正が恐れているのは、冬木だ。
冬木に、見た目も頭の出来も良く似た雪哉は、きっと、敏感に父や女たちの思いを嗅ぎ取っていたに違いない。あの、試すような眼差しは、雪馬や雪雉にはないものだ。
二歳になったばかりの頃、雪哉を北家系列の中央貴族の養子に出すか、自分の手元に引き取るかの、二択を迫られたことがあった。
亡くなった冬木さまが可哀想だ、継母のもとで子どもの立場がないと言うのなら、いっそ手を離してしまった方がお互いのためにはよかろう――そう嘯く連中の声の、なんと甘かったことか。
結局梓は、甘言と共に伸ばされた手を振り払った。
雪哉を養子にと望んだ者達は、結局のところ、雪哉の身分にしか興味のない連中ばかりだった。冬木の傍で見てきた彼らのやり口を思い出し、自分のことを「ははうえ」と呼ぶ雪哉を見てしまえば、もう、手放すことは出来なかった。
あの時、自分は雪哉を、自分の息子として育てることに決めて、その決心どおりにしてきたつもりだ。後悔したことはない。だが、それは本当に、雪哉のためになっていたのだろうか。
――自分は果たして、雪哉の母親として、ふさわしいのだろうか。
「梓さま」
たまらなくなり、雪正と離れるように歩いていた梓に声をかけてきたのは、先ほど厨房にいた郷吏の妻のうちの一人だった。
かつて、北家本邸から垂氷までついて来た、冬木付きの侍女だった女である。
「あの、あたし、今まで梓さまに言えなかったことがあったんです。そのぅ、冬木さまについて……」
「冬木さまについて?」
ちょっと躊躇った後、彼女は、覚悟を決めたように頷いた。
冬木が、梓が子を生したという噂を聞き、無理を押して北家本邸までやって来た時のことだ。
お凌の方に会う直前に、冬木は梓のいる棟にやって来ていたのだという。
「でも、梓さまは眠っていらっしゃって……その横に、雪馬坊ちゃんが寝かされていたんです」
彼女は、冬木が雪馬に乱暴するのではないかとひやひやしたが、そうはならなかった。
「あのひと、雪馬殿を抱き上げて――こう、笑ったんです」
「……何ですって?」
「笑ったんです。冬木さまが」
自分でも信じられないという顔をして、彼女は繰り返した。
「優しい、優しい笑みでした。あのひとのあんな顔、あたしは見たことがなかった」
そんな顔をした後で、冬木はしばらく、何も言わずに考え込んだ。
そして、わざわざ一度本邸を出てから、改めて正門から入り、あの騒ぎを起こしたのだという。
「あのひとが何を考えていたのかなんて、分かりません。あのひとはあたし達には本当に意地悪だったから。本当は、梓さまに文句のひとつでも言ってやろうと思っていたのかもしれません。でも、少なくとも、怒ってなんかいなかったんじゃないかって、あたしはそう思うんです……」
あんな優しい笑顔をした後に、いきなり怒り狂った冬木。その瞬間の変化を目にした彼女には、冬木の激昂は、どうにも納得がいかないものだったのだ。
「みんなが悪口を言うたびに、あたし、あのひとのあの笑顔が、どうしても思い出されてならなくって……」
どうにも分からない、と、彼女は梓を見上げた。
「梓さま。どうしてあのひとは、あんな顔で笑ったのでしょう」
芽吹いたばかりの木々はまだ寒々しく、腕のように伸ばされた枝の間からは、淡い月影が漏れている。
郷長屋敷の裏手、斜面に生える木々の間をひとりで歩きながら、梓は考えた。
冬木は、怒りと嫉妬にかられて、自分の命を粗末にするような女だっただろうか。誰も幸せにならないようなことを?
否。
確かに彼女は捻くれていて、性格が良かったとはとても言えない。でも、どんな時だって冷静だった。一時の感情で、そんな自暴自棄になるような女じゃない。彼女なりの計算があったはずだ。
彼女は、おそらくは単純に――自分の子どもが欲しくなったのではないだろうか。
もしかしたら、最初は煮えくり返るような怒りがあったのかもしれないが、それも、雪馬を見たら消えてしまった。もともと、かしましい女房には冷たい目を向けるのに、目いっぱいに泣く赤ん坊には、嫌な顔ひとつ見せたことのない女だ。おそらくは、子どもが好きだったのだと思う。思えば、自分に対してひどく優しかったのも、梓が彼女よりも六つも年下だったせいかもしれない。
だが、普通に「子どもが欲しい」と口にしたところで、反対されるのは目に見えていた。冬木は、雪正が自分を好いていないこともとっくに承知していただろうし、北家の意向を気にして、冬木の身を危うくするようなことを、絶対にしないだろうことも見通していた。
だから、怒っているふりをしたのだ。
そうでなければ死んでやると怒り狂って、周囲がそうせざるを得ないと認めるように。
自分の評価を地に落とし、後々のお家騒動も全て承知していながら、きっと、それでも彼女は子どもが欲しかったに違いない。
そして、うぬぼれかもしれないが、それを彼女がやったのは、梓が雪正の妻だったからだ。
冬木は、身内の貴族連中を嫌っていた。
彼らに大事な息子を渡そうなどと思うはずがない。
立場上、雪哉を育てるか否かを決めることになるのは梓だ。
あてつけの意味もあっただろう。怒りだって覚えていたに違いない。だが、もし自分の推測が当たっていて、彼女が何よりも子どもが欲しいと望んでいたのであれば、そんなつまらない感情で、全てをだいなしにするような愚かな真似をするはずがない。
冬木は冷徹で、捻くれていて意地悪で、そして何より、愛情深い女だった。
彼女は、息子を愛していて、そして、梓を信用していたのだ。
――梓だったら、私の子を悪いようにはしないでしょう?
随分と時間がかかってしまった。それでも、やっと、彼女の本当の声が届いた気がした。
私の子をお願いね、と。
「ええ、そうです冬木さま。私達の息子です」
歩きながら、梓は声に出して言った。
「だからお願いです、冬木さま。雪哉と、雪雉を守ってください。どうか無事に、帰してください」
そう言った瞬間、風もないのに、ざわりと木々が揺れた気がした。
梢にかかった朧月が、おかしな具合にぐにゃりと歪むのが分かる。
一瞬の後、淡く霞んでいた月の輪郭がはっきりと澄み、煌々とした光を放つようになった。その大きな満月を背にして、何やら、黒い影が浮かんでいる。
しばし目を凝らし、梓は息を吞んだ。
――それは、信じられぬほど大きな鳥影であった。
各地から名馬が集められた北家本邸ですら、あれほどの巨躯を持ったものは見たことがない。同族と見定めてよいのか決めかねているうちに、それはこちらに向かって、ゆるやかに近付いて来た。
そして、立ち竦む梓の前に、悠々と着地したのだった。
降り立つ瞬間、翼に煽られて、梓の髪がぶわりと舞い上がった。
近くで見たそいつは、やはり、とんでもなく大きな烏であった。
普通の八咫烏の、ゆうに三倍はあるのではないだろうか。
黒い鉄のような嘴は鋭く、恐ろしく思ってもいいはずなのに、不思議と、そんな感じはなかった。
梓に向けられた瞳は水晶のようにきらきらと輝き、羽は淡い月光の中でも硬質な紫と瑠璃の輝きを帯びるほどに艶々としている。大きさを見なかったとしても、どこか八咫烏離れしているというか、それのまとう空気の色、そのものが違って見える。
唖然と見上げていた梓は、しかしその烏が、何かを咥えていることに気が付いた。
何だろう――籠のようだ。
すると、梓の視線を受けた大烏が、そっと足元にそれを置いた。
「この子は、貴女の息子か?」
思いがけず、少年のような高く澄んだ声が響く。
見れば、花の咲いた藤蔓で編まれた籠の中で、息子達が眠っていた。
「雪哉――雪雉!」
駆け寄り、むしゃぶりつくように籠にすがりつく。
弟を抱きしめるように、泥だらけとなった雪哉がいる。雪雉の方は、まぶたを真っ赤に腫らしていたが、どちらも目に見える範囲では、どこにも怪我はないようだ。
「安心しろ。ちょっと眠ってもらってはいるが、すぐに目を覚ますだろう」
すまないな、とはっきりとした御内詞を話し、大烏は首をかしげた。
「私が中途半端に結界を繕ってしまったものだから、ほころびに足を取られていたのだ」
意味が分からずぽかんとすると、大烏は言い直した。
「この子達は、自力では抜け出せない場所に、はまり込んでいたということだ。私のせいだから、どうか𠮟らないでやってくれ」
梓は夢中になって頷いた。
「あなたは――山神さまの、お使いですか」
「……まあ、そんなようなものだ」
「息子たちを助けて頂いて、ありがとうございます」
「もとはといえば私のせいだ。この子達が大きくなったら、いずれ、また会う機会が来るかもしれん。良い子達だ。大切に育てよ」
大烏はそう言い残すと、翼を翻して飛び立った。
また、月がぐにゃりと歪む。瞬きの刹那に、まるでまぼろしのごとく、大烏は空の中へ融けるようにして消えてしまった。
しばしあっけにとられていたが、その姿が見えなくなってすぐに、雪哉がもぞもぞと動きだした。
「雪哉、雪哉。どこか痛いところはない?」
「母上……?」
𠮟ってはいけないと思っていたのに、つい、「お馬鹿!」と声が出た。
「もう。一体、今までどこにいたの。怪我はない? 大丈夫なの」
「だいじょうぶ」
ああ、無事でよかった、と抱きしめられ、ぼんやりとしていた雪哉は、すぐに我に返ったように「雪雉は!」と叫ぶ。名前を呼ばれたせいか、雪雉もぽかりと目を開く。しばし、何が起こったか分からない顔をしていたが、梓の顔を認めた瞬間、すぐにわあっと泣き始めた。
「ははうえぇ」
「雪雉」
「ごめんなさぁい」
弟が梓に抱きついたので、自然と、雪哉は一歩下がる形となった。
「僕、すぐに帰ろうとしたんです。でも、なんでか同じ道から出られなくなって」
「うん」
「どうして。だってここ、郷長屋敷の裏でしょう?」
周囲の様子を見て、ここがどこだかを悟った雪哉は狐につままれたような顔をしていた。
「どうして、迷子になんてなったんだろう……」
「きっと、山神さまのお庭に入ってしまったのよ。でも、お兄ちゃんが、雪雉を守ってくれたのね」
遠慮するように足を引いた雪哉を構わず抱き寄せ、ありがとう、と言う。すると、すうっと雪哉の眉間から険が抜け、赤ん坊の時と変わらない顔になった。
「……本当は、こ、怖かった」
「そうだよね。怖かったよね」
「帰りたいのに、帰れなくって、雪雉は泣いちゃうし、お腹もへったし」
「でも、雪雉を守ってくれたんだね。強かったね。えらかったね」
お兄ちゃんは頑張った、と言った瞬間、不意に――びええええ、と雪雉に負けない大声で、雪哉が泣き出した。
「お腹へったぁ。もう帰りたい」
もう帰るぅ、と顔を真っ赤にして泣く雪哉に、雪雉の方がびっくりした顔で泣き止んだ。
思えば、ささいなことで喧嘩し、泣いてしまう長男と三男と違い、雪哉がこんな風に泣くのは、ひどく久しぶりだった。
「ごめんねえ、雪哉。一緒に、おうちに帰ろうね」
きっと、色々と我慢をさせていた。申し訳なく思ったが、それでも、こうして泣いてくれるのであれば、まだ何とかなると思った。
雪哉の泣き声を聞きつけ、郷長屋敷の方から慌てふためいて人々が駆けつけて来た。
その先頭に立ち、全力で駆け寄って来るのは、雪正だ。
「雪哉、雪雉! お前ら、どこに行っていたんだ!」
心配したんだぞ、と心底ほっとしたように叫ぶ夫の声。その後ろからは、転がるように駆けて来る長男の姿もある。
今ならまだ、大丈夫。順風満帆とはいえないかもしれないけれど、それでも、この子は自分の息子であり、自分達はひとつの家族なのだ。
今のうちに気付けてよかった。
死んだ八咫烏は、山神のもとに働きに出るという。
もしかしたら、山神に仕える冬木が、このままではいけないと思い、自分にそれに気付く機会を与えてくれたのかもしれない。
――冬木の穏やかな笑い声に似た、木ずれの音を聞いた気がした。
-
『わたしリセット』田嶋陽子・著
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募期間 2024/9/20~2024/9/27 賞品 『わたしリセット』田嶋陽子・著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。