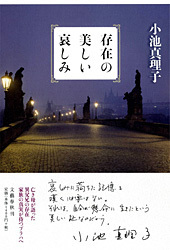──この長編は、とてもユニークな構成になっています。第一章の語り部は「わたし」です。八年前、「わたし」に異父兄がいることを母親から知らされます。二十歳のときのことです。その母が亡くなり、恋人とも別れた「わたし」は、貯金のすべてを使って、異父兄の聡が住むプラハへ向かいます。自分の正体は一切明かさず、聡をガイドとして雇い、プラハを旅する。その二泊三日の旅を描いたのが第一章です。そして、二章目から三人称になっていきます。その辺の目論見は、後ほどゆっくりと伺うとして、まずプラハの街を舞台にした理由を教えてください。
小池 オール讀物編集部から、好きな場所を旅行して短編を書きませんか、という依頼を平成十九年に頂きました。そのとき思いついたのがプラハだったんです。私は米国か欧州かといえば、欧州の方が好きですが、フランスやベルギー、オランダにはすでに行っている。折角ならば直行便がなくてあまり行く機会もないであろう東欧に行きたいと思ったんですよ。
──この取材では、どこを経由して行かれたのですか。
小池 ウィーンです。私はピアノを習っていて、中学生の頃は音楽大学へ進学して音楽の道で食べていきたいと思っていました。その頃仲が良かった友達は、オペラ歌手になっています。彼女とは、音楽室を借り切って、お互いにピアノの伴奏をしあって歌を歌ってました。丁度、その頃に「天使の歌声」と言われる、ウィーン少年合唱団が来日したんです。大ファンでしたし、興奮したことを覚えています。彼女と、「大人になったら一緒にウィーンへ行こうね」と可愛らしい少女の約束をしたことを覚えています。
──プラハと、ウィーン。実際に旅をしてのご感想は。
小池 ひと言で言えば、古いものが、そのままコンパクトに残されている街でした。想像以上に中世の空気が残っていましたね。
──第一章「プラハ逍遥」では、街の描写が丁寧になされていて、まるで一緒に旅をしているような気持ちになります。しかし、第二章「天空のアンナ」はガラリと変わって、「わたし」の母親の視点で物語が始まります。さらに、母の仕事仲間、聡の異母妹、そして聡の視点などと、章ごとに視点を変えて物語が進んでいきます。このような構成にした理由を教えてください。
小池 編集部からは一編だけ書いて欲しいという依頼でした。しかし、短編小説「プラハ逍遥」を書き終えたときに、一作では終わることの出来ない余韻が私の中に残されたんです。この余韻は、短編小説なのに、まるで長編小説を書くときのように、背景にある人間ドラマを克明に設定したからこそ、生まれたのだと思います。二年後、オール讀物編集部から、定期的に何か書いて欲しいという依頼を頂いたとき、浮かんだのが短編「プラハ逍遥」の続編でした。視点を変えていけば、「芹沢」という家が、どのような存在の哀しみを抱えてきたかを書けると思ったんです。「プラハ逍遥」でその軸は書きこんでいましたから、変な話、その後は楽でした。