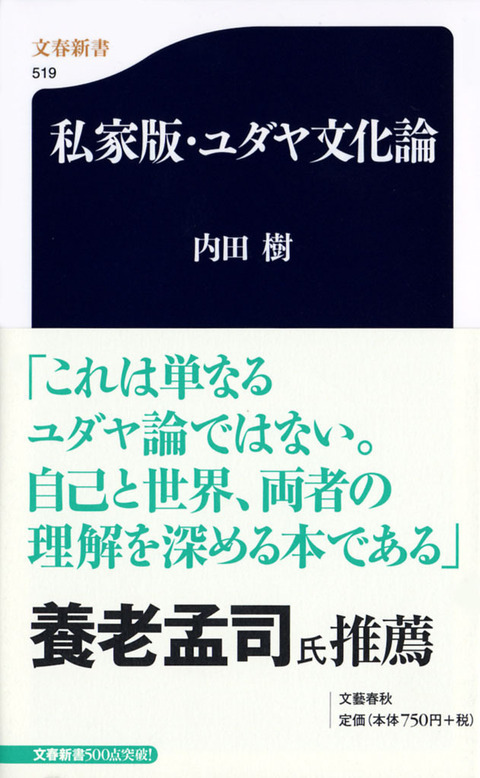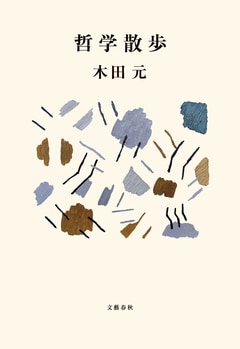昨年、内田樹(たつる)がこの本のもとになる「私家版・ユダヤ文化論」を「文學界」に連載しはじめたとき、なぜいまユダヤ文化が問題なのか、うろんな筆者にはよくわからなかった。けれども、単行本にまとめられたものを読むと、彼がどういうことを考えようと漠然と感じつつ執筆に着手し、最終的に、どういうことを書くことになったかがだいたいのところ、わかる。
ほら、よくあるでしょう。道路を車で行くとその真ん中がこつんと突き出ている。毎回通るたびにガクンとなる。で、ある日車を降りて掘り出してみたら、道路をふさぐばかりか道路自体を載せるほど巨大な岩盤だった。そういうことが今回、内田に起こっている、というのが簡単に言うと筆者の理解である。
小さな始点というのはこうである。
彼は長い間、エマニュエル・レヴィナスという難解さで知られるフランスに住むユダヤ系の哲学者を師として、自分の知的活動を行ってきた。彼には、師の言っていることはよくわかる。そういうことはほとんど師のほかには誰も言っていない。だから彼は師をあがめてきたのだが、しかし、そのことを人に伝えようとすると、それはどうしても「難解」なこととなり、いかにもよそ目に「わかりにくい」。実際問題、人にそう受けとられるだけでなく、彼自身、そう感じる。なぜ、そういうことになるのか。
すばらしいのは、彼がこういう場所でしっかりと立ちどまる人だということである。その答えは、ふつうの学者の場合だと、他の人がバカなせいか、その知能が少し弱いせいか、知的教養において少し不足しているせいか、憶説にまどわされているせいか、である。ふつうの学者・専門家なら、問いはここで終わる。しかし、内田はこの小さな始点から、自分の言いたいことが「難解」なのは、いまの了解作用を成り立たせている標準型の知的な枠組み(われわれがふつう西洋的な知性あるいは知的態度と呼んでいるもの)が、けっしてそれに説得されないもう一つの知的な枠組み(内田がここでユダヤ的な知性あるいは知的態度と呼ぶもの)と対になって存在してきたためではないか、と考える。そして小さな始点から、大きな終点へと歩いてゆく。
-
『赤毛のアン論』松本侑子・著
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募期間 2024/11/20~2024/11/28 賞品 『赤毛のアン論』松本侑子・著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。