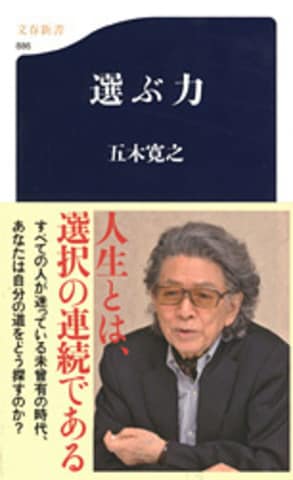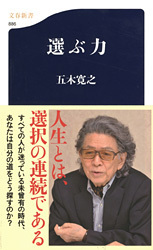子どもが成長する過程で避けて通れないものに、「反抗期」がある。中学1年くらいになると突然、母親が用意した「ごはんとみそ汁」といった朝食に、手をつけようとしなくなる日がやって来る。
「早く食べちゃいなさい。遅刻するわよ」
「…私、今日はパンが食べたい」
「パンはないから、ごはん食べて。あ、おいしい佃煮があるから、出すわね」
「パンがないなら、食べたくない!もういい、いらないから!」
プイッと席を立つわが子に、「昨日まではあんなに素直だったのに」と母親はただ唖然とするばかりだ。
大人から見れば、そのときの朝食がパンかごはんか、というのはさほど大きな問題ではない。しかし、思春期を迎えて「自分らしさ」に目覚めかけた子どもにとっては、「私は今日はパンが食べたい」といったひとつひとつの選択が、人生の重大事なのである。せっかく決めたことがかなえられないと、自分自身が否定されたような気分になる。だからつい、親に対して大声をあげたりモノを投げつけたりしてしまうのだ。こう考えると、子どもは「自分で選んで決める」という行為を通して、本当の自分自身になっていく、と言うことができるだろう。
そして、実は「選ぶことで自分になる」のは、子どもに限ったことではない。いや、それどころか年齢を重ねれば重ねるほど、多様な選択肢の中から自分で考え、選び、決める。そんな場面は増すばかり、その重要性は大きくなるばかりだ。
信仰を持たないわれわれの国にあって、今や多くの人びとの“心の師”となっている五木寛之氏の最新刊を貫くテーマは、まさに「自分で選び、自分で決める」という問題だ。著者は言う。
「私たちはさまざまなものを選ぶことができる。モノを選び、人間関係を選び、職業を選び、配偶者を選ぶ。その限りにおいては自由な人間である」
ところが、実際には「完全な自由などどこにもない」とも著者は述べ、選べないものの代表を「運命」だとする。国籍、性別、生家の貧富なども私たちは選ぶことができない。