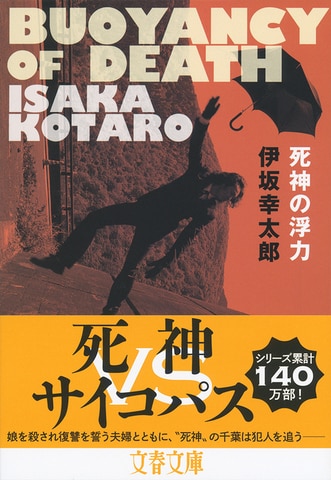
- 2016.07.10
- 書評
笑いを誘う一方、怖さも感じさせる“死神”を登場させた伊坂幸太郎の技
文:円堂 都司昭 (文芸・音楽評論家)
『死神の浮力』 (伊坂幸太郎 著)
出典 : #文春文庫
ジャンル :
#エンタメ・ミステリ

「人間の発明したもので最悪なのは、渋滞だ」と考える千葉は、大名行列は「渋滞」だという。参勤交代を「懐かしいな」とか「あれはなかなか面倒臭い」などと語る彼に対し、周囲の人々は、なにを見てきたような冗談をいっているのかと思う。しかし、千葉はふざけているわけではない。彼は死神であり、大昔から人の死の可否を判定する仕事をしてきた。だから、実際に見てきたのだ。
伊坂幸太郎の連作短編集『死神の精度』(二〇〇五年)において、千葉は、OL、ヤクザ、恋する若者、老女など、死が近い(かもしれない)様々な人間のドラマに立ち会った。なかには、連続殺人事件が進行中の吹雪の山荘にいる人物も、含まれていた。ヴァラエティに富んだ内容であり、表題作「死神の精度」は、第五十七回日本推理作家協会賞短編部門を受賞した。本書はその続編となる長編『死神の浮力』(二〇一三年)の文庫化である。とはいえ、独立したストーリーだから、前著を読んでいなくても問題はない。
このシリーズの世界では、死神たちが対象となる人間をそれぞれ一週間調査し、死ぬべきか、見送るべきかを判断している。ただし、進行する病、自らの罪による極刑、自殺による死は管轄外であり、死神が関与するのは事件、事故、災害などによる不意の死だ。死神は皆、千葉のように町や市の名称である苗字を使っている。彼らが素手で触れると、人間は気絶してしまう。人類とは異なる力や性質を有する死神は、人間の発明で最悪なのは渋滞だと考える一方、最高なのは「ミュージック」だという。このため、CDショップの試聴コーナーなど音楽を聴ける場所では、死神同士が出会ったりする。
いろいろなジャンルに興味を示し、音楽ならなんでも好きなのではないかと思われる千葉が興味を示した一曲に、ザ・ローリング・ストーンズの「ブラウン・シュガー」があった(『死神の精度』所収の「死神と藤田」)。そういえばストーンズには、自分はキリストの死やケネディの暗殺など、歴史上の多くの凶事を目撃してきたと悪魔が主張する「悪魔を憐れむ歌」という曲があった。時代を超えて活動する点で、伊坂の死神と親近性も感じられる同曲の詞は、モスクワに悪魔が現れるというミハイル・ブルガーコフの小説『巨匠とマルガリータ』にヒントを得て書かれたものだった。そのことが意識されていたかどうかわからないが、伊坂は『文藝別冊 総特集 伊坂幸太郎』(二〇一〇年)の企画で自らを作り上げた百冊の本をセレクトしたなかに、『巨匠とマルガリータ』もあげていた。
ちなみに、その百冊には伊坂が愛読した作家としてよく名前をあげる大江健三郎の四作品が選ばれており、『われらの時代』も含まれていた。同作には、自分ができる行動は自殺だけであり、自殺の機会に見張られながら生きるのが自分たちの時代だとするシリアスなテーマがあった。生と死をめぐる問題を純文学作家らしく観念的に語った作品だ。それに対し、同じく死の可能性を題材にするにしても、エンタテインメント作家である伊坂は、死神というキャラクターへと実体化し、わかりやすく表現している。
「死ぬとは限らない」と希望を探したり、「死ぬに死ねない」ともがいたりする調査対象者に、「もちろん人間は死ぬ」とただの事実を思い浮かべる。拷問されて目をえぐられるなら「死んだほうがマシ」という人には、「目が見えなくなったところで、それは死ぬこととはまったく関係がない」と断定する。どんな暴力をくらっても自らは死ぬことがなく、いくらでも時代を超えて活動できる死神と、我々人間には、とてつもない認識のギャップがある。それが笑いを誘う一方、怖さも感じさせるのが、この死神シリーズだ。
『死神の浮力』では、娘を殺した犯人に復讐しようとする山野辺夫妻と千葉が、行動を共にする。今回の千葉の調査対象者が、その夫だからだ。対象者をろくに調査しないまま可否を判断する死神が多いのに、千葉は仕事をさぼらないたちであり、相手をきちんと見届けようとする。だが、人間である読者の感覚からして調査対象者に同情してしまう時でも、千葉が死を見送るべきと考えることは少ない。ほとんど可、つまり死んでよしと判断する。
人間と価値基準が圧倒的に違う彼に、情状酌量なんて発想はない。彼と人間との会話では、「良心がない」と聞いて両親のいない「クローンというやつか」と返すような、とんちんかんなやりとりが頻発する。大昔から人間たちと関わってきたのに、人間たちの価値基準を未だに理解していないし、重視してもいない。だから、山野辺夫妻に同行する千葉は、彼らの復讐を手助けしているのか邪魔しているのか、よくわからない言動を繰り返す。そうして悲喜劇が展開される。
デビュー作『オーデュボンの祈り』(二〇〇〇年)に、言葉を話し未来を予言するカカシが登場したように、伊坂は運命をしばしば題材にしてきた。『終末のフール』(二〇〇六年)では、八年後に小惑星が衝突して地球が消滅すると発表されてから五年が過ぎ、ある種の凪の状態にある街が舞台になっていた。『あるキング』(二〇〇九年)では超人的な野球の強打者を主人公にすえ、シェイクスピア『マクベス』を意識した展開で、彼の人生を見守る三人組の魔女を登場させていた。死神シリーズもこれらと同様に、運命と人の関係を描いている。
一方、伊坂は、善悪や倫理の外にいる存在も、たびたび書いてきた。『オーデュボンの祈り』では、桜という人物が悪事を働いたものを射殺し裁いていた。だが、彼がなにを悪としているのかは他の人間には理解できず、ただ絶対的なルールのごとき存在としてそこにいるのだった。また、『グラスホッパー』(二〇〇四年)、『マリアビートル』(二〇一〇年)には、いずれも多数の殺し屋が出てきた。彼らは仕事として人を殺すことに疑問もためらいもない。選ばれた人間が人を殺すのは是か非かという、罪の問題を扱ったドストエフスキーの古典『罪と罰』を愛読する殺し屋が登場するブラックユーモアもあった。本書の死神も、こうしたキャラクターの系譜に位置づけられる。
かと思えば、『マリアビートル』の中学生・王子慧、『死神の浮力』の本城崇のように狡猾で他人を操ることに長け、悪を楽しむキャラクターもいる。本城も『罪と罰』に言及する。彼は、二十五人に一人いる、良心を持たないサイコパスだとされる。だが、悪を楽しむ王子や本城と、善悪という意識の外で仕事する殺し屋、死神では考えかたに落差があり、『マリアビートル』、『死神の浮力』では両者が摩擦を起こす。一般人、悪を楽しむもの、善悪の外にいるものの三者の意識のズレが、物語を複雑にしていく。
カカシや死神には、人間には見えないことが見通せる。ずる賢い王子や本城は、一般人より何手も先を予想できる。こうした目線の高さや視野の広さの差から生じる齟齬を、伊坂は何度も作品で扱ってきたし、作家としての体質になっているようにも感じる。『ゴールデンスランバー』(二〇〇七年)、『モダンタイムス』(二〇〇八年)、『火星に住むつもりかい?』(二〇一五年)で見張る側の権力と見張られる一般人がせめぎあう監視社会を描いたのも、目線や視野をめぐる物語のヴァリエーションに思える。
死神シリーズにしても、千葉たち調査部の死神は、情報部の指示で動く。千葉は情報部が情報をろくによこさないことに不満を持っている。また、『死神の浮力』を読むと、死神の世界には監査部まであり、情報部の仕事ぶりに問題があることが語られている。人間よりも多くを見通せる死神であっても、死神の組織のなかでは知っていることに差があるわけだ。それは『ゴールデンスランバー』などに描かれた監視社会の権力組織の内部に、階層による権限や取得情報量の差があることと似ている。
そして、この目線の高さや情報量の差は、伊坂の創作術にも関係している。『ラッシュライフ』(二〇〇二年)、『アヒルと鴨のコインロッカー』(二〇〇三年)、『グラスホッパー』など、ある時期までの伊坂は構成の妙で魅せる作家だった。個々の場面を読むだけではよくわからない。すれ違うそれぞれのストーリーを生きている登場人物には、別のストーリーを生きる人物のことはわからない。だが、最終的に物語全体の意外な構図が判明する。伊坂はそういうタイプの構成を得意とし、伏線の回収が巧みだった。登場人物よりも高い目線と多い情報量が与えられ、物語全体を見渡せるのは、作者と彼に導かれた読者である。それは神様(あるいはカカシ)になって世界を俯瞰するような面白さなのだった。
だが、『ゴールデンスランバー』の頃から伊坂は、あえて物語をきれいに構成せず、余剰を残すことを繰り返し試みるようになった。本書でも、伏線が回収されたかと思えば、型通りには盛り上がらず脱力する場面が待っていたり、神様の気まぐれのごとき意外な物語展開に翻弄される。
また、『文藝別冊 総特集 伊坂幸太郎』のインタヴューで伊坂は、映画のDVDをコマ送りにしたり、止めたりしながら、映像で見たアクションを文章に書き起こし、自作の小説に組みこんだことがあると話していた。本書にも、スローモーション的な細かい描写が効果を上げているアクション・シーンがある。死神は、電波に乗った音声を聞きとったり、人間には不可能な倍率でものを見たりすることができる設定だ。感覚の解像度が違う。それに似て作家としての伊坂も、感覚の解像度を変えた描写をすることで、場面を迫力のあるものにしている。
人ならぬものを作中に登場させる伊坂幸太郎は、小説世界の創造主としてそうした技の数々を駆使する。こんな神様の気まぐれならば、何度でも翻弄されたい。
-
『踊りつかれて』塩田武士・著
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募期間 2025/05/30~2025/06/06 賞品 『踊りつかれて』塩田武士・著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。











