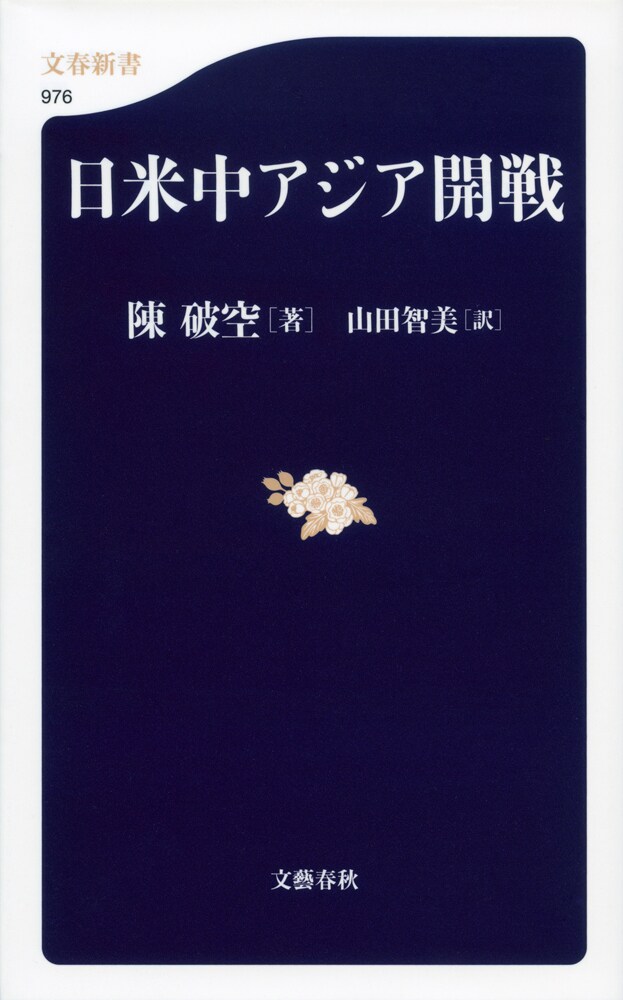
凄まじいエネルギーが込められた本である。いや、驚いた。そしてちょっとスカッとした。
国際社会のルールや世界の常識という観点から見たとき、中国(共産党政権)という国がいかに外れた国であり、また横暴で脅威を周辺国にまき散らしているのかを、これでもかとばかりに口撃しているのである。
中国の取材ではときどき、朝から日が暮れるまで取材相手が話を止めなくて疲れ果てるということがある。とくに中国に酷い目に遭わされた人々が取材対象であれば、ほぼ間違いなくそのパターンだ。
著者の陳破空氏は天安門事件により中国を追われた過去を持つ。まさに共産党政権に対して複雑な感情を抱えた筆者ということ。本書が執念に満ちた作品に仕上がっていることにも頷けるというわけだ。
中国の横暴さに辛辣な一撃
動機が明瞭であるだけに中国の横暴を示す国際的な動きについては非常に良く網羅されていてまとまりがある。そして、その1つ1つの事象にいちいち辛辣な一撃が加えられるのも本書の特徴といえるだろう。
第2章の〈フィリピンへの援助でみせた「度量」〉では、島嶼(とうしょ)の主権をめぐる争いがあるフィリピンが台風30号に襲われたときの中国の反応を描き、民間企業のイケア(スウェーデンの家具会社)でさえ、270万ドルの支援を発表したことと比較して、〈中国は、当初わずか十万ドルしか拠出しないつもりだった〉が、〈国内外からの批判を受けて、しぶしぶ二十万ドルに増やす醜態を晒した〉と皮肉った後に、〈これが大国の「度量」とやらである〉とこきおろす。分かっていても、つい「プッ」と吹き出してしまった。
中国の軍拡に関する記述では、その動機において天安門事件が果たした役割があまりに大きく位置づけられている点には小さな違和感が拭えなかったものの、これまで世界が感じてきた中国による現状変更の試みへの懸念が、疎漏なく描かれている点には感心させられた。
中露間に横たわる複雑な感情
また日本人には分かりにくい感覚として、中国のロシアに対する警戒感に触れた記述も興味深く読んだ。
もちろん60年代から70年代にかけて、核戦争の一歩手前まで危機を高めた両国間が、現在習近平・プーチン間で演出される“蜜月”のそのままだと考えられるはずもないのだが、中露の水面下の感情はそれどころではないらしい。
そして、実際に書き込まれたメッセージは両国国民間の感情が思いのほか複雑であることを知らしめた。
本書では、具体的な書き込みとして、〈「中国人民に最も大きな損害を与え、最も多くの中国の領土を占領し、中国が内戦に陥るのを喜び、中国民主化を極度に遅らせた張本人。血債累々だ」、「人を害する思想主義を突っ返して、神聖な領土を取り戻してこい」〉という2つが紹介されているが、もっとたくさん読んでみたいと思った。
いずれにせよ対日本の歴史の清算が終わっても、中国の歴史問題は終わらないという問題の根深さを予感させ、同時に日本問題はむしろ本番前の準備体操のようなものだと位置づけられるのかもしれない。
ロシアの慎重すぎる対中外交の裏側にはこうした累積した感情の存在があり、一旦火を噴けば大火事は免れないといった事情があるのかもしれない。
さて、本書で示される日米中開戦のシミュレーションだが、もともと高めの筆者のテンションがさらに高まっていることが感じられ、非常に面白かった。開戦のシナリオは決まった材料で料理を作るようなものだが、「なるほど、その2つを組み合わせたか」といった内容だ。
ただ、尖閣が舞台であれば難しいのは占領することではなくそれを維持することだ。それが難しいから中国は手を出さないとも考えられるが、筆者はこの点をどう考えているのか訊いてみたいものだ。
日米中アジア開戦
発売日:2014年07月04日











