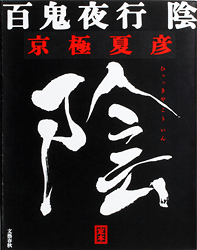京極夏彦さん待望の新作『定本 百鬼夜行 陽』が刊行される。著者の代表作〈百鬼夜行〉シリーズに登場するキャラクター10名を主人公に据え、シリーズ本編では語られることのなかったエピソードを幻想的な筆致で描いた短篇小説集だ。
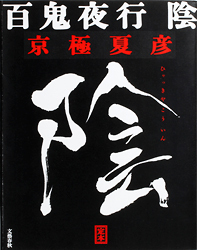

「〈百鬼夜行〉シリーズはどれも長いし、集団劇でもありますから、とにかく登場人物がたくさんいます。物語に関わるキャラクターは展開上何らかの決着がついているわけですが、端役だとそうもいかない。この短篇集はそうした人たちを視点人物にしています。シリーズ本編を丸太に喩えるとすれば、この短篇群は丸太の断面です。外側からでは見ることのできない断面を、切り出して見せているようなものですね」
長篇『陰摩羅鬼(おんもらき)の瑕』の団体役員・平田、『邪魅(じゃみ)の雫』の元警察官・大鷹など、シリーズ本編の愛読者にはお馴染みの顔ぶれが並んでいる。大事件の陰に隠れて、窺い知ることのできなかった彼らの内面や人生が、この短篇集では克明に描かれてゆく。
「人間の行動原理なんて外から見ただけでわかるものではありませんね。特に、つまらないことや、どうでもいいことだと、なぜそうしたのか当人にもわかっていないことが多い。また、世の中にはどうでもいいことが多いんです。でも、そのどうでもいいことが流れを変えたり、決めたりすることも多い。本編の主要人物に関しては内面が語られることも多いですが、端役の場合はカットされてしまうでしょう。でも、作った段階で一応は決めてあるので、そこを切り出した形ですね」
「青行燈(あおあんどう)」「大首」「屏風闚(びょうぶのぞき)」など妖怪の名前がつけられた全10編の冒頭部には、それぞれ江戸時代の画家・鳥山石燕(せきえん)の手になる妖怪画が掲げられている。
「僕の作品はよくミステリだと言われますが、元々は『憑物(つきもの)を落とす話』なんですね。事件という妖怪を拝み屋が特定して、祓い落とす物語です。そのプロセスがミステリの構造に似ていた。初めて短篇を依頼された時、少ない枚数でそのプロセスを書く自信がなくて、あれこれ考えた結果、憑物落としをしない小説はどうだろうかと思い至ったんです。視点人物は憑かれている認識はない。しかし読者から見ると明らかにおかしいわけです。何かに憑かれているとしか思えない状態に見える。読んでる方は気持ち悪いですね。で、読者は憑物落としの役を自分ですることになる。冒頭の石燕の絵は、今回はこういう妖怪が憑いてますよ、という模範解答です。妖怪は特定しないと落しにくいんですよ」
奇妙なこだわり、思いこみ、病的なまでの恐怖感。いびつな心理によって日常の外へと少しずつ押し流されてゆく主人公の姿を、著者は妖怪に重ね合わせる。では妖怪に「憑かれている」とは一体どのような状態なのだろうか?
「人間はいい加減なものですから、理屈では割りきれないような感情を抱いたり、常識で量れない体験をしてしまったりすることもあります。原因はさまざまでしょうが、おおかたはやり過ごしてしまえるし、やり過ごせなくても上手に決着をつけることができるものです。人間は本来、そういうふうにできているんです。でも、稀にやり過ごすこともできなければ決着もつけられない状態に陥ることがある。そうなると、現実の方をねじ曲げてでも無理に決着をつけようとしたりしてしまう。そういう時ですよ、人が何かに『憑かれている』というのは」
本書にはシリーズ第2作『魍魎(もうりょう)の匣(はこ)』から長篇次回作として予告されている『鵺(ぬえ)の碑(いしぶみ)』まで、幅広いキャラクターが登場する。キャラクターと妖怪の組み合わせは、どのような手順で決まってゆくのだろう。
「妖怪のほうは、それまでに使っていない石燕の絵が条件になりますから、そこから選ぶしかありません。一方、視点人物は掃いて捨てるほどいる端役の中から選ぶことになるわけで、これはまあ、誰でもいいんです。お化けとキャラクターがちょうどスロットマシンの目が揃うように並ぶと、それで終わりですね。その段階でどういうものになるかは決まってしまいます。それほど大変な作業ではありません。端役でも設定はある程度細かく決まっているので、後は思い出すだけですね。実はこれが結構面倒で、思い出せなくて勝手に書いてしまうと、シリーズ本編との整合性がとれなくなる可能性がある。メモなんかないし、本編も忘れています。スピンオフという性質上、そこは齟齬がないようにしないといけないんですけど」