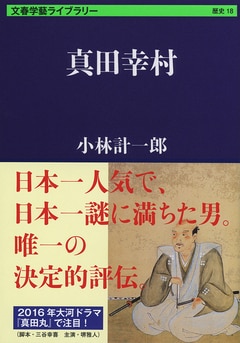中央線の阿佐ヶ谷駅北口を出て、荻窪の方向に少しだけ歩くと、昭和時代を彷彿とさせるような居酒屋のひとかたまりがあって、その尾っぽあたりにクラシック音楽を聞かせる、その内部がウィーンの楽友協会ホールを模した恰好の『ヴィオロン』という喫茶店がある。
この喫茶店の親爺は少し変わっていて、音響装置に凝ったりしているが、芝居や音楽好きの連中に夕方から店を明け渡してくれる。
あるとき、この店で、長宗我部盛親ファンを集めて「盛親を語る会」を企画した。盛親の催しはかつてもやったことがあるが、人があまり集まらず、トラブルも多いので、しばらくやっていなかった。時代がちがってきたのか、この日は予定を超えて三十人ほどが集まった。しかも若い女性が多かった。
だが、やはり問題はいくつか起こった。それでも、なんとか会は終わり、盛親好きも結構いるとの実感を得て、私は満足した。
その帰りがけのことである。喫茶店を出てすぐに、ひとりの中年の男性が私の歩く速度に合わせて寄ってきて肩を並べた。
その男性は「盛親のことを悪くいってはいけませんよ。必ず祟ります」。そういうのだ。そのときは何とも答えようがなかったが、そういう人も盛親のファンにはいるのか、と思った。
だが、盛親が祟るという話はいくつかはある。盛親が捕縛されたときにその居場所を蜂須賀の士に教えた家とその村の者が祟られているといったことを人づてに聞いたことがある。いずれにせよ、かなり前のことである。いまどきそのようなことをいう人もいるのか、とは思ったが、そのちょっとした出来事が、盛親のことをもう一度、その思いとともに考えてみようというきっかけになったことは確かである。
盛親については謎が多い。なぜ、と思うことが多すぎる。だから、ついつい短絡的に「盛親は暗君か」と思ってしまうし、思い返すと、私も前著『長宗我部』(文春文庫)で、盛親については長宗我部家の系譜のなかでの「暗転」と位置付けた。盛親の人生を振り返ると、不運としか思われない。「名将」とはいえず、せいぜい「勇将」でとまってしまう。だが、不思議に盛親を支持する人は根強くいるのだ。
それは大坂の陣で、真田幸村や毛利勝永らとともに「義」をもって戦ったからだろうか。
長宗我部元親を主人公にした小説『夏草の賦』の著者である司馬遼太郎は、長宗我部家の人物を元親のほかにも何人か取り上げているが、最初に描いたのは盛親である。昭和三十五年(一九六〇年)八月に「講談倶楽部」に連載を始めた『戦雲の夢』がそれである。
長宗我部家の当主として選ばれながらも、その座にあったのは一年半足らずである。その後、ほとんどの人生を京の都で牢人として過ごし、大坂の陣に大名家復活の夢を賭けた。そういう男の生き方を小説にしたいと思ったのであろう。
しかも盛親は自害せず、最期まで生きることにこだわり、斬首されている。
本書では、その「生き抜く」という盛親の心を考えてみたかった。