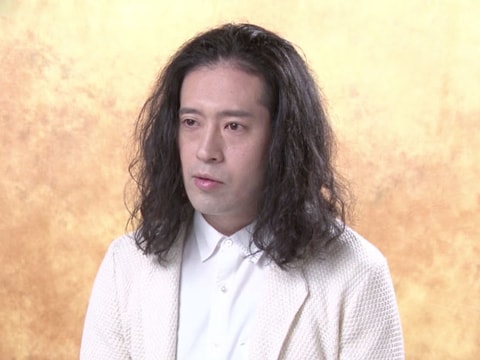大地を震わす和太鼓の律動に、甲高く鋭い笛の音が重なり響いていた。熱海湾に面した沿道は白昼の激しい陽射しの名残りを夜気で溶かし、浴衣姿の男女や家族連れの草履に踏ませながら賑わっている。沿道の脇にある小さな空間に、裏返しにされた黄色いビールケースがいくつか並べられ、その上にベニヤ板を数枚重ねただけの簡易な舞台の上で、僕達は花火大会の会場を目指し歩いて行く人達に向けて漫才を披露していた。
中央のスタンドマイクは、漫才専用のものではなく、横からの音はほとんど拾わないため、僕と相方の山下は互いにマイクを頬張るかのように顔を近づけ唾を飛ばし合っていたが、肝心な客は立ちどまることなく花火の観覧場所へと流れて行った。人々の無数の微笑みは僕達に向けられたものではない。祭りのお囃子が常軌を逸するほど激しくて、僕達の声を正確に聞き取れるのは、おそらくマイクを中心に半径一メートルくらいだろうから、僕達は最低でも三秒に一度の間隔で面白いことを言い続けなければ、ただ何かを話しているだけの二人になってしまうのだけど、三秒に一度の間隔で無理に面白いことを言おうとすると、面白くない人と思われる危険が高過ぎるので、敢えて無謀な勝負はせず、あからさまに不本意であるという表情を浮かべながら与えられた持ち時間をやり過ごそうとしていた。
結果が芳(かんば)しくなかったので、どのようなネタをやっていたのかはあまり正確に覚えていない。「自分が飼っているセキセイインコに言われたら嫌な言葉はなんや?」というようなことを相方に聞かれ、「ちょっとずつでも年金払っときや」と最初に答えた。それから「あのデッドスペースはもうあのままやねんな」、「折り入って大事な話あんねんけど」、「昨日から眼を合わせてくれへんけど食べようと思ってる?」、「悔しくないんか?」などと、およそセキセイインコが言うはずのない言葉を僕が並べ立て、それに対して相方が相槌を打ったり、意見を述べたりしていたのだけど、なぜか「悔しくないんか?」という言葉に対してだけ相方が異常に反応し、一人で笑い始めた。その時、僕達の前を通り過ぎた人達は相方の笑い声しか聞こえなかったはずだが、相方は声を出さずに笑う引き笑いなので、ほとんど僕達は二人でただそこに立っているだけの若者だった。相方が笑ったことが唯一の救いだった。確かに一日の充実感を携えて帰宅したところをペットのインコに「悔しくないんか?」などと言われたら、少しだけ羽を燃やしたくなるかもしれない。いや、羽を燃やしたらインコが可哀想だ。むしろ、ライターで自分の腕を炙(あぶ)った方が火を恐れる動物に激烈な恐怖を与えられるかもしれない。火で自分の腕を燃やすなんて、鳥からすれば驚異以外の何ものでもないだろう。そんなことを思うと、僕も少し笑えたのだけど、通行人は驚くほど僕達に興味がなく、たまに興味を示す人もいるにはいたが、それは眉間に皺を寄せながら僕達に中指を立てて行くような輩ばかりで、頗(すこぶ)る不愉快だった。大勢の中での疎外感に僕はやられていて、いま、飼っているインコに、「悔しくないんか?」と言われたら、思わず泣いてしまうのではないかと思っていたら、僕達の後方の海で爆音が鳴り、山々に響いた。
沿道から夜空を見上げる人達の顔は、赤や青や緑など様々な色に光ったので、彼等を照らす本体が気になり、二度目の爆音が鳴った時、思わず後ろを振り返ると、幻のように鮮やかな花火が夜空一面に咲いて、残滓(ざんし)を煌(きら)めかせながら時間をかけて消えた。自然に沸き起こった歓声が終るのを待たず、今度は巨大な柳のような花火が暗闇に垂れ、細かい無数の火花が捻じれながら夜を灯し海に落ちて行くと、一際大きな歓声が上がった。熱海は山が海を囲み、自然との距離が近い地形である。そこに人間が生み出した物の中では傑出した壮大さと美しさを持つ花火である。このような万事整った環境になぜ僕達は呼ばれたのだろうかと、根源的な疑問が頭をもたげる。山々に反響する花火の音に自分の声を掻き消され、矮小な自分に落胆していたのだけど、僕が絶望するまで追い詰められなかったのは、自然や花火に圧倒的な敬意を抱いていたからという、なんとも平凡な理由によるものだった。