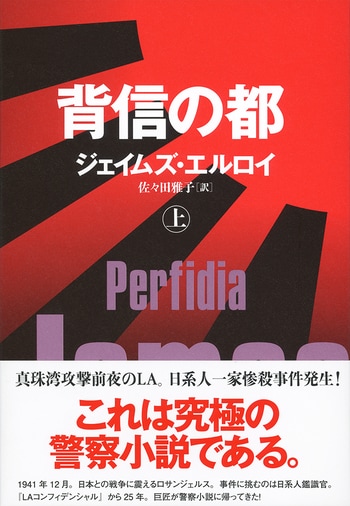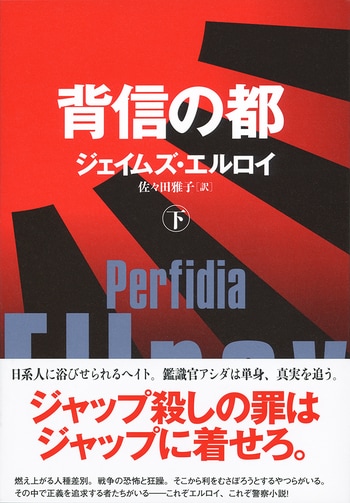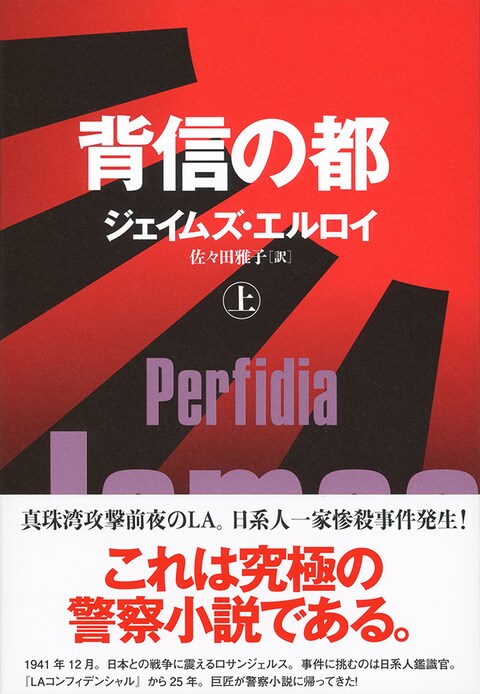
- 2016.06.06
- 書評
巨匠エルロイ、20年ぶりの警察小説 戦時下のLAで刑事たちが謎を追う!
文:永嶋 俊一郎 (文藝春秋)
『背信の都』 (ジェイムズ・エルロイ 著/佐々田雅子 訳)
出典 : #文春文庫
ジャンル :
#エンタメ・ミステリ
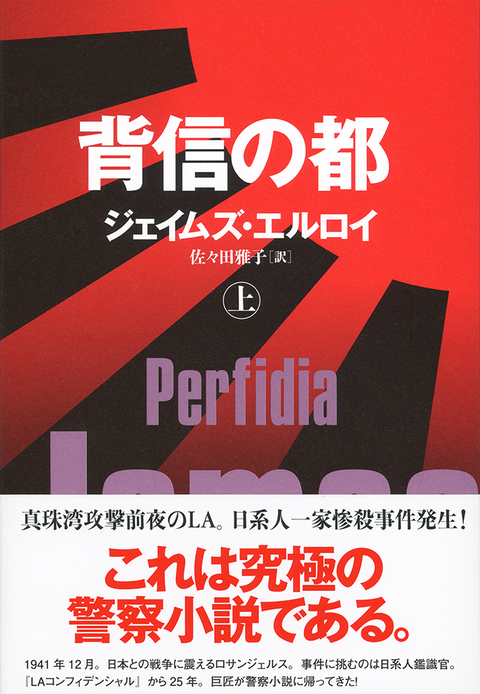
本書はジェイムズ・エルロイの第十四長編Perfidia(Knopf, 2014)の全訳で、エルロイが開始した《新・暗黒のLA四部作》の第一作となる。「裏切り」といったような意味を持つ「Perfidia」は、グレン・ミラーやナット・キング・コールなどのヴァージョンもあるジャズのスタンダード曲のタイトルからとられた。本書のなかでも、あちこちで「パーフィディア」の調べが奏でられている。
前作『アンダーワールドUSA』で、エルロイはアメリカの政治と暗殺のクロニクル《アンダーワールドUSA三部作》の幕を閉じた。ジョン・F・ケネディ大統領暗殺にはじまり、ロバート・ケネディ司法長官とマーティン・ルーサー・キング牧師の暗殺、リチャード・ニクソンの登場とアメリカの中米への干渉――ヴェトナム戦争を機に没落してゆく白人の支配体制のあがきを、白熱のノワールとして、悪の全体小説として、エルロイは描き切った。
それから四年のブランクを置いて発表したのが本書である。
物語は一九四一年十二月六日にはじまる。ロサンジェルス市警の鑑識官を務める日系二世のヒデオ・アシダは、頻繁に強盗に襲われるドラッグストアを監視するため、手製の自動写真撮影機を設置していた。アシダは科学と工学に秀でた怜悧な青年である。
惨劇が起きたのはその夜のことだ――日系人農園主リョーシ・ワタナベの一家四人が血まみれの部屋で発見された。一報を受けて現場に急行したのはLAPDのダドリー・スミス巡査部長。腹部を裂かれた死体はまるで日本の切腹のようであり、壁には日本語で書かれた遺書らしきものが残されていた。日系人であるアシダを呼びだし、ダドリーはその文字を解読させる。
いま迫り来たる災厄は/われらの招きたるものに非ず/われらは善き市民であり/かかる事態を知る身に非ざれば――そう書かれていた。「迫り来たる災厄」とはいったい何なのか?
無理心中とするには不可解な点がいくつもある現場を離れた翌朝、十二月七日。アメリカ全土を揺るがすニュースが届いた――日本軍が真珠湾を奇襲したのだ! ついに日米は戦争状態に突入し、ロサンジェルスを不安と怒りが覆う。ひとびとは軍に志願するために列を成し、日系人へのヘイトが燃え上がり、彼らは財産を没収され、拘置されてゆく。
そんななかで「ジャップ」の殺しを解決する必要があるのか? LA市警とLA市の大物たちは、この事件をきちんと扱うことで自身の正当性を示そうと決めた。しかし真犯人を捕らえる必要はない。ちょうどいい変態なりジャップなりに罪を着せればいいではないか。その意を受けて、ダドリー・スミスが動きはじめる。
一方、ヒデオ・アシダは収集した証拠をもとに独自の捜査をつづける。「迫り来たる災厄」とは真珠湾攻撃のことではないのか。殺されたワタナベはスパイだったのではないか。しかし日系人収容の網はアシダにも迫り、徐々に彼を追いつめてゆく……
アシダの決死の捜査。それを妨害し、ときに利用する悪徳刑事ダドリー・スミス。この二人を軸にしつつ、エルロイは、視点となる人物をさらに二人登場させる。《暗黒のLA四部作》でもしばしば名前の挙がっていた、のちのロサンジェルス市警察本部長で実在の警察官ウィリアム・パーカーと、『ブラック・ダリア』に登場した女ケイ・レイクである。それぞれに自身の信じる「正義」を貫こうとする彼らの行動が描く線は、しかし、複雑怪奇な策謀でさまざまに屈折する。ロサンジェルスに「第五列=スパイ」が潜んでいるのではという疑心暗鬼も高まり、戦争に乗じて儲けようとする者たちも陰謀を企む。政治と欲望と暴力の衝動が織りなす壮大なタペストリーを編むエルロイの筆は健在であり、むしろ力感は増している感さえある。
三人の男たちの物語にひとりの女性の手記をはさみこむ手法は、前作『アンダーワールドUSA』を踏襲したものだ。男性主人公の犯罪小説を書きつつも、そうした物語にありがちな男性優位主義に陥らないのがエルロイのひとつの特徴だが、女性視点をひとつ入れることで、そうした側面がさらに深みを増している。悪徳の交響曲のごとき『背信の都』で最後の重要な調べを奏でる役割も、女性に与えられているのだ。
セクシズムだけではない。本書には日本人を意味する差別語「ジャップ」や、中国人を差別する語「チンク」といった言葉が乱れ飛ぶ(どころか第一部、第二部のタイトルにまでなっている)が、これは真珠湾攻撃直後にLAを覆うヘイトを描いているだけで、エルロイ自身がレイシストでないことはヒデオ・アシダの扱いを見るだけでわかるはずだ。肌の色が何であろうと、あるいは性別や宗教がどうであろうと、悪いやつは悪いことをする。悪いやつがいいことをすることもある。それがエルロイの人間観であり、それはレイシズムからもセクシズムからも遠く離れたものだ。
さきほど、ダドリー・スミス、ウィリアム・パーカー、ケイ・レイクといった登場人物を挙げたが、本書には過去のエルロイ作品に登場した人物が多数登場する。ヒデオ・アシダも『ブラック・ダリア』の序盤で(名前だけだが)語られていた。くわしくは下巻巻末のエルロイ自身による「登場人物名鑑」をご覧いただきたいが、登場するのは《暗黒のLA四部作》の人物だけでなく、《アンダーワールドUSA三部作》のキャラクターも本書の重要な役割を担っている。最終的に『ブラック・ダリア』の直前で閉幕するという《新・暗黒のLA四部作》は、つまり、《LA四部作》と《USA三部作》を統合し、一九四一年から一九七二年に至るエルロイ世界のクロニクルを完成させる壮大なプロジェクトと言っていい。
これまでエルロイの小説に触れたことのない読者に、本書は恰好の入り口でもある。本書は「エルロイ世界」の時系列の最初に位置する物語だからである。本書のあとに《LA四部作》や《USA三部作》を読むことで、本書に登場した人物にふたたび出会うことができる。若かった彼らや彼女らが、どう歳を重ね、どう人生を全うし、あるいはどんな死を迎えるのか。それを目の当たりにする機会が、未読の皆さんを待っているのだ。《アメリカ文学界の狂犬》との異名をとるエルロイの唯一無二の小説世界にぜひ触れていただきたい。
エルロイ自身は、自分流の警察小説の原点として、ジョゼフ・ウォンボー(『センチュリアン』『クワイヤボーイズ』など)と、ジョン・グレゴリー・ダン『エンジェルズ・シティ』をしばしば挙げている。警官たちの粗野な日常と言語をモザイクのように組み合わせて、コミカルさと重厚さを併せ持つ小説世界を編んだウォンボーの手法は、エルロイの初期作品『秘密捜査』の段階ですでにみられ、『ビッグ・ノーウェア』以降の作品の基本線となっている。ジョン・グレゴリー・ダンの『エンジェルズ・シティ』は、ブラック・ダリア事件を思わせる猟奇殺人をカギにして、刑事と聖職者のふたりの視点からロサンジェルスの政治と倫理と犯罪を描いた大作。人間の魂の上半身と下半身を通じて、悪徳と政治を複眼的に描くこの作品の佇まいは、まさに『ブラック・ダリア』以降のエルロイの核心部分と通じ合う。ことに本書『背信の都』では、カトリック系のアイルランド人であるダドリー・スミスとカトリックの大司教との関係を通じて、宗教の問題が存在感を増してもいる。
単に犯罪を捜査する役割だけではなく、警察組織の政治力学や腐敗と無縁ではいられない組織人でもある存在として、エルロイは警察官を描いてきた。それによって「警察小説」の新たな地平を拓いたエルロイが、『ホワイト・ジャズ』から二十年以上を経て、生まれ故郷のロサンジェルスと、古巣である警察小説に帰ってきたのである。
「ジョーンは丸太に横木を渡した柵に腰掛けていた。格子縞のシャツ、膝までのブーツ、乗馬ズボンという格好で。髪を真ん中で分けて縛っていた。厳しく、はっとするほど冷ややかな美しさを発散していた」(本書下巻35ページ)
熱心なエルロイ・ファンのなかには、この写真に見覚えがあると思うかたもいるかもしれない。そう、これはエルロイの母、エルロイが十歳のときに何者かに殺害されたジニーヴァ・ヒリカー・エルロイの姿なのである。エルロイの自伝『わが母なる暗黒』のカバーをご覧いただけば、そこにある女性の写真が「赤毛のジョーン」の写真そのままだとわかるだろう。
エルロイが犯罪小説を書きはじめた動機の芯の芯には、母ジニーヴァの死があった。夜ごとの妄想のなかでエルロイは母とブラック・ダリアを重ねあわせ、殺人犯を撃退した。当時のLAの犯罪実録『The Badge』で活躍する刑事たちに自分を重ねた。デビュー二作目の『秘密捜査』で、エルロイは“ダストボウル生まれの赤毛の女”を殺人の被害者として登場させ、母を殺された十歳の少年(つまりエルロイ自身だ)を登場させ、刑事たちに事件を解決させた。そして初のハードカバー作品を書くにあたって、エルロイは『秘密捜査』の変奏を試みる。『秘密捜査』そっくりの構成で、エルロイは母殺しと分かちがたく結びついた「ブラック・ダリア事件」に取り組み、解決した――出世作『ブラック・ダリア』である。
本書の時点では、パーカーにとってジョーンが何であるのか、多くが謎のまま残されている。本書でのパーカーはアルコール依存症を克服しようと苦闘しており、同じく依存症に苦しんだエルロイ自身の姿がそこに重なる。パーカー=ジョーン/エルロイ=ジニーヴァ。この二重写しは、この《新・暗黒のLA四部作》もまた、エルロイのオブセッションたる母の死を語り、理解しようとするエルロイの試みなのではないかと思わせる。
すでに取材がはじめられているという四部作第二作の登場を待ちたい。
-
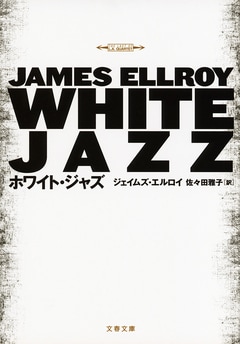
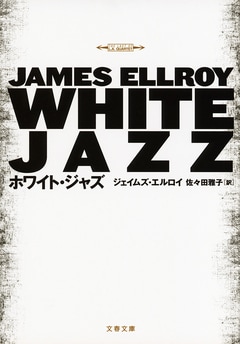
解説――血をまき散らせ!
2014.07.01書評 -


暗闇の中で小説は生まれる
2011.07.20インタビュー・対談
-
『グローバルサウスの逆襲』池上彰・佐藤優 著
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募期間 2024/4/19~2024/4/26 賞品 新書『グローバルサウスの逆襲』池上彰・佐藤優 著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。