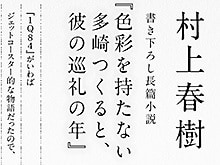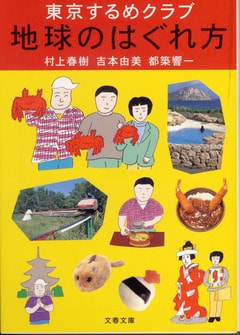本書はグレイス・ペイリーのいちばん最初の短編小説集である。アメリカでは一九五九年、つまり四十六年前に発表されたものだ。そのとき彼女は三十七歳だった。次に発表されたのは一九七四年の『最後の瞬間のすごく大きな変化』で、彼女は五十二歳だった。次いで一九八五年に『その日、もっとあとで(Later the Same Day)』が発表されたとき、彼女は六十三歳になっていた。そして今のところこの三冊しか世に出ていないそうである。
高齢とはいってもペイリーはまだ健在だし、筆を折ったわけではない(らしい)から、長い作家生活を思うと三冊は確かに少ない。たいへん寡作な人のようだ。その理由は本書の訳者あとがきに詳しいのでここでは省くが、しかし私は、発表時のペイリーさんの年齢の三つともが、女性の人生の中で特にだいじな節目と思われる年と(多少はズレても)重なっていることに意味を感じて、もうそれだけでいい、ペイリーさんはこの三冊でもう充分じゃないかという気もしている。たった三冊という数字はファンにはもの足りなく思えるが、しかしそのそれぞれの一冊は、節目から節目に至る十数年間の彼女の感情が、凝縮され、あるいは濾過され、または余計な嵩(かさ)を削ぎ落とされて残ったもの、精油みたいなものであると考えると、部屋が狭くなる不安もないという具体的な理由も加勢して、数で勝負の作家さんより私には好ましく映る。量じゃなく質を取りたい。
私がグレイス・ペイリーという、元ハリウッド女優を思わせる端正な響きを持った名前を知ったのはかなり前(正確には思い出せない)だ。短編小説・翻訳ものがささやかながらブームとなっていた頃のグラビア誌の、アメリカ短編小説特集、あるいは翻訳小説特集、または女性小説家特集みたいな中に発見した。訳が村上サンということも後押ししたが、こういう美女を彷彿させる名前の持ち主はいったいどういう話を書くのかと、たいへん俗な興味から読んでみたのだ。それは母親の話だったか、死の床にある友だちを見舞う話だったか。以後同じような特集で何編か読んだので(すべて村上サンの翻訳)確かな順番はオボロだが、まずとにかく、個性的な文体に引き込まれた。自由自在にあっちこっちを行き交う言葉。ナマな会話。礫(つぶて)のように撒き散らされた奇妙なユーモア。そして見え隠れしている憤りの気配。それらが、おカタイような柔らかいような、哀しいような可笑しいような、クールなようなホットなような、曰く言い難い物語を紡いでいく。一発でヤラレたのだった。
-
『赤毛のアン論』松本侑子・著
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募期間 2024/11/20~2024/11/28 賞品 『赤毛のアン論』松本侑子・著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。