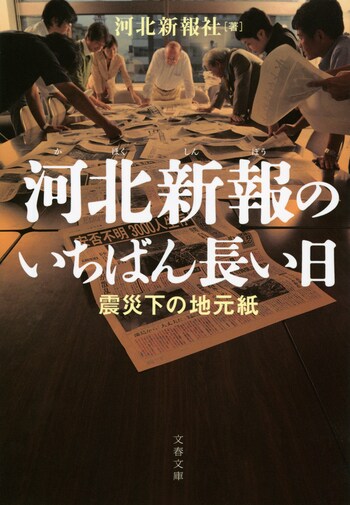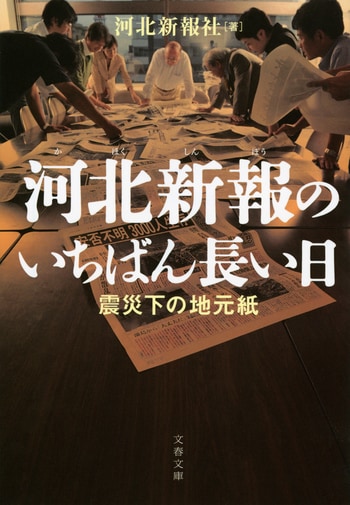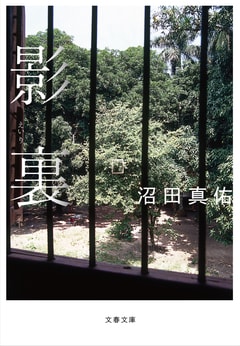二〇一一年三月十一日に勃発した東日本大震災にさいして、地元紙・河北新報が、震災にいかに対応し、何をどう伝えたか……を克明に記すドキュメントである。
河北新報は、宮城・仙台を本拠に、東北各県をエリアとするブロック紙である。震災で本社の建物は持ちこたえたが、沿岸部にある支局や販売店は軒並み被災した。販売店でいえば、店主が死亡した店が三店、全壊が十九店舗。配達員など従業員で亡くなった人が宮城県内で十五人、行方不明者九人と、すさまじい数に達している。新聞社は文字通りの被災者でもあった。
自家発電によって本社ビルの電力は維持されたが、組版サーバーは使えず、水、食料、ガソリン、刷り紙……が窮乏するなか、号外を出し、翌日の朝刊を出し、以降も新聞は途絶えることなく発行され続けた。
それは、記者、カメラマン、デスクなどの編集部門だけではなく、支局、総務、販売、輸送など新聞社を構成する全部局の総力によって維持されたものだった。社内で急遽つくられた「おにぎり班」も裏方の“兵站”を担った。
決して休刊にしない──新聞人の熱い思いが、全編を貫く音色として、ひしひしと届いてくる。
河北新報は一八九七(明治三十)年に創刊されている。明治維新で“賊軍”となり、「白河以北一山百文」と揶揄された東北人の意地と矜持が社名に込められているが、改めてその底力を見るようである。
随所に、個々の新聞人の奮闘ぶりが記されている。
カツオの水揚げ高日本一を誇る港町、気仙沼の総局長をつとめる菊池道治。入社二十八年目の古参記者だ。停電によってパソコンは使えず、コピー用紙の裏面に手書きで原稿を書いた。
《〈白々と悪夢の夜は明けた。湾内の空を赤々と染めた火柱は消えていたが、太陽の下にその悪夢の景色はやはりあった。……
美しい景色と水産のまち・気仙沼市は、今まで誰も見たことのない、形容しがたい無惨な姿をさらしていた。
その景色を見ることができたのは、むしろ幸運だったのかもしれない。
震災当日の11日、襲い来る津波に胸までつかり、死にかけた。気仙沼総局に避難してきた人たちに食料をとコンビニに走ったのが失敗だった。
水は白い波頭を見せ、道沿いにひたひたと迫ってきた。近くのビルの2階ベランダに駆け上がったが、勢いは一向に衰えない。あっという間、5、6メートル流された。フェンスによじ登り、柱にしがみついた。水かさは増す。死を覚悟した。……〉》
手書き原稿は、本社から総局にたどりついた記者、武田俊郎に手渡された。帰路、武田は原稿を「道中、バッグに入れずにずっと手に持っていた」とある。先輩記者が命を賭して書いた原稿を失ってはならぬ、と思ってである。降版間際に本社に持ち帰られた原稿は十三日付朝刊に載った。
《「店はやられたが、配達はできる。今、新聞を取りにそっちに向かっているから、とりあえず五百部、用意してくれ」》
阿部を突き動かしていたのは避難所での読者の反応だった。テレビもネットも断ち切られた状況下、手持ちの新聞を「壁新聞」として張り出すと、誰もが食い入るように見詰めた。
《「ありがとう」「役に立ったわ」避難者から口々にお礼を言われた。
これまで新聞を届けて「ありがとう」と言われたことはあっただろうか。「ご苦労さま」とはよく言われるが、「ありがとう」を耳にしたことはない。……
そんな中、地域の被災状況を丹念に伝える河北の報道に触れ、初めて自分の置かれた状況を知ることができた。地元紙は、暗い足元を照らす明かりのような存在として、確かにあった》
本書の成立には、震災から一カ月後、記者たちから集められたアンケートが元となっている。さまざまな思いを抱いて取材活動にあたった記者たちの肉声が綴られていた。
震災翌日、ヘリで石巻上空から空撮を行ったカメラマン。小学校の屋上で「SOS」の文字を作って必死に手を振る人々の姿を痛みを覚えつつ撮った。新聞に写真が載れば、すみやかな救援活動が行われるだろう……。願いを込めた一枚だった。
けれども検証報道「その時 何が」のなかで、小学校はその後も飢えと寒さのままに放置され、医療チームが派遣されたのが一週間も後だったことが判明する。
《「医療チームが入るまで相当な時間がかかり、あの写真が結果として無力だったことが分かった。いったい報道とは何だ? 俺の仕事は本当に人の役に立っているのだろうか?……」》
カメラマンは自己嫌悪に陥りつつ自問自答を繰り返す。
あるいは福島原発の取材に当たった福島総局の女性記者。放射能汚染が広がった時点で、本社は当地より記者たちの退避指示を出した。記者は故郷の佐渡に一時帰郷したが吹っ切れない。なぜ福島を離れたのか……。
《佐渡から電話取材をした。知っている首長の携帯に電話した。田村市の市長には「記者なんだから電話で聞かないで見に来い」と怒鳴られた。安全な場所にいる自分を呪い、号泣した。……
佐渡に来てからまともに眠れていない。田村市長の言葉が耳に残る。自分が現場にいないことを恥じた。自分の安全を優先させる者は記者ではない。私は記者なんて大それた仕事に就いてはいけなかったんだ》
《何でもいいから戻りたい。このまま戻らないと、一生立ち直れない》
現地に戻った彼女は被災地のレポートを書き続けていくが、一時的であれ福島から退避したことに苦しめられる。震災から五カ月後、仕事に区切りをつけた、と記されている。
地元紙は、倒壊家屋の中から九日ぶりに救出された老婦人と少年のスクープを行い、被災者のためにきめ細かい生活情報を提供し、さまざまな検証報道を展開した。その背後に、記者たちの逡巡や後悔や苦悩があったことを知る。そのことを赤裸々に伝えることによって、本書は、震災にまつわるドキュメントを超えた、固有の作品性を獲得している。
紙面制作に当たる整理部の記者たちもまた悩み、苦しんだ。
震災から二日後、宮城県警本部長は、遺体の数が「『万単位』に及ぶことはほぼ間違いない」と言明、知事もまた「そう思う」と追認した。
死者「万単位に」────という見出しを作りつつ、宮下拓は迷い続けた。
《宮下は、石巻周辺の見慣れた光景を思い返してみた。死者のほとんどは地震と津波が到来する直前までいつもと変わりない日常を送っていたはずだ。職場で仕事し、家で家事をし、学校で学び、趣味を楽しんで「生きていた」。その自分の隣人たちに「死者」という言葉を付けることができるのか。また生き残った隣人たちに、奪われてしまったものを突き刺すようにして追認させるような見出しを自分は打てるのか》
翌十四日朝刊、全国紙、他紙の見出しが「死者は万人単位」などであったのに対し、河北は「犠牲『万単位に』」だった。「犠牲」と打ったのは河北ただ一紙だった。
それが、正しい判断であったのかどうか。「今も答えが出せません」と宮下は語っている。
福島原発一号機の建屋が水素爆発によって吹き飛んだ。他紙が「原発爆発」という見出しであったのに対し、河北が「建屋爆発」としたのも整理部記者に同種の心理が働いたからである。
宮城・南三陸町の三階建ての町防災対策庁舎ビルが津波に飲み込まれる瞬間を連続撮影した写真が持ち込まれた。約三十人の避難者が屋上にいる。次のコマでは、無線塔によじ登り、フェンスにしがみついた人々が約十人に減っている──。衝撃的な写真だった。
掲載の是非をめぐって議論が分かれ、報道部長の武田真一は現地取材班の記者に電話をかけた。
《「その写真を地元の人が見たら、多分もたないと思います」記者はそう即答した。
それを聞いた太田(巌・編集局長)は断を下した。
「掲載は見送ろう。われわれは被災者と共に、だ」》
被災地と被災者に寄り添う──。本書で何度か記されている言葉であるが、お題目ではなく、日々そのことを自問し、模索しつつ紙面づくりが進められていったことを知る。
未曾有の大震災。記者たちにとっても未曾有の取材行だった。だれもが傷を負いつつ、震災は彼らを本当の新聞記者にしていったのだと思う。
本書のラストは、記者たちを指揮し、差配した武田の、「そもそも報道とは何なのか? 武田の自問は続く」という一文で締め括られている。 “正しい”答えはないのだろう。けれども、新聞人たちが解のない自問自答にもがきつつ歩き、撮り、書き、制作し、読者へと送り届けたが故に報道は力をもったのだ。
「白河以北」の地にあった新聞人たちは、新聞の──ジャーナリズムの、と言い換えてもよい──原点と役割をいま一度示してくれた。本書を読了し、そんな思いがよぎる。
なお、一連の報道により、河北新報は二〇一一年度の新聞協会賞を受賞している。また本書を原作として制作されたテレビドラマ『明日をあきらめない…がれきの中の新聞社』(テレビ東京)は、二〇一二年度の日本放送文化大賞および東京ドラマアウォードにおけるグランプリを受賞している。ドラマ評はまた別個のものであるが、録画を見る機会があり、不覚にもしばしば涙腺が緩んで困った。
──武田真一氏の「文庫版へのあとがき」を読むと、河北新報はその後も、粘り強く、「震災その後」の報道を続けていることを知る。敬意を表したい。そして、河北新報は、〈東日本大震災〉を担うべき運命にあった新聞なのだと思う。
歴史時間のなかでいえば、かつて中国新聞が〈原爆〉を、沖縄タイムスが〈沖縄〉を、熊本日日新聞が〈水俣〉を、神戸新聞が〈阪神・淡路大震災〉を担い、秀でた報道を持続してきた。河北新報は、日本の新聞史の、誇るに足る歴史の列に新たに参入した。健闘を祈る。
河北新報のいちばん長い日
発売日:2014年04月11日
-
『新・常識の世界地図』21世紀研究会・著
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募締切 2025/08/28 00:00 まで 賞品 『新・常識の世界地図』21世紀研究会・著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。