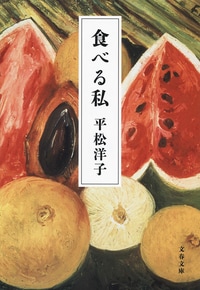
──本書には29名の方々が登場しますが、今回、食を通じて「人」に焦点を当てようと思った理由は?
食べものについて話をしようとすると、「特に強いこだわりがあるでもないし、食べものについて自分はとくに語るべきことを持っていない」と構えてしまう方も多いと思います。でも私の経験上、自分が食べるということについて、人は必ず語りを持っている、という確信がありました。実際にいろんな方にお話を伺ってみると、やはりみなさん独自の言葉を持っていらっしゃって、どんどん引き込まれました。食べものについて話を伺ううちにひとりの人間像が鮮やかに浮き上がってくる、そういう感じがありました。
──連載時から、インタビューや対談ではなく、「対話」になるように心がけたということですが、それはどういう意図だったのでしょうか。
“食べる”というのはあまりにも日常的な行為なので、普段はあまり意識していないことが多いですよね。だからこそ、食べものについて語る場合、相手があってこそ言葉になるという面が大きいと思います。食べることをめぐって何気なく発せられた言葉に対して、こちらが何か反応したり、その言葉の意味を感知したりすることによって、話す人の言葉がどんどん開けていく。こちらが「聞き出す」というのではなく、食べものに対する記憶や潜在的なものを、話しながら一緒に言葉にしていくという感じでしょうか。それを何と呼ぶかというと、「対話」かな、と。
──皆さんと話していて、どんな発見がありましたか。
特に興味深かったのが、食の話をしていると、年齢、性別、職業関係なく、必ず子どもの頃の話になるんです。それは、何を食べたかということだけではなく、親との関係だとか当時の環境だとか、家族のなかで育まれたものが子ども時代の食体験に集約されているからだと思います。食べものというのは、具体的だから強いんですよね。
たとえば、ギャル曽根さんをテレビで見ていると、ただ大食いなのではなく美味しいから食べているという感じが伝わってきて、それは一体なぜだろうと思っていたんです。実際に彼女と話してみたら、きょうだいで楽しく食卓を囲んで、料理上手のお母さんが作る料理をみんなでどんどん食べている様子が、情景として浮かんでくるようでした。
デーブ・スペクターさんのマカロニチーズ
──連載第1回にデーブ・スペクターさんが登場した時は、「食」のイメージがあまりなかったので驚きました。
食に対して興味がなさそうに見えても絶対に何か話すことを持っているという確信があったからこそ、第1回をデーブさんにお願いしたかったんです。
お母さんが作ってくれたマカロニチーズの話に行き着いたときは、デーブさんの記憶が開いた瞬間を感じましたね。黒く焦げたバターの味を、「僕にとって、それ、グルメ」とおっしゃったとき、自分にとって大事なものがあれば生きていけるという幸福な孤独感に接したようで、じーんとして感銘を受けました。こういう強固な記憶があれば人は生きていける、食べものはそれを支える存在でもあるということを痛感しました。ときに、食べものは、その人の持っている幸福感と孤独感、その両方を浮き彫りにして奇跡的な瞬間をもたらすことがあります。
──他にも、印象的なエピソードがたくさんありました。伊藤比呂美さんが大好きで多いときは五つも六つも食べるという生卵。安藤優子さんが「チャーリー」と名前をつけていたという糠床。田部井淳子さんが山に登る時に「これだけは持って行く」というわさび。髙橋大輔さんが探検に行く前に必ず食べるというカツ丼……。金子兜太さんの「本当に好きな食べものなんていうものはあらへんのです」という言葉も、印象的ですね。
生きている限り、ひとは食べるという行為から逃れられないし、それは作家でも、アスリートでも、芸人でも同じことです。みなさんと話していて感じたのは、食にまつわる言葉は、深いし、強いということ。情景が浮かぶような記憶や、身体性と直結する感覚、それに、その人のありかた自体……いろんなものがその言葉に現われていると思います。









![[文庫化記念対談]皆川 明×平松洋子 トレンドを超越するテキスタイル・デザインの力](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/1/f/480wm/img_1f197f912afbd254edc72fd9279395a146600.jpg)









