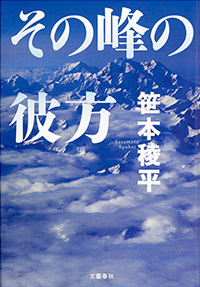
「山登りと執筆は、やっぱり似ています。登山の途中は執筆と同じで苦しいし孤独。でも、登り終え、書き終えた時は、その疲れが全て吹き飛んでいきますから」
警察小説や国際謀略小説など、幅広いジャンルで活躍してきた笹本稜平さん。近年は『還るべき場所』『春を背負って』と、山を舞台にした重厚な人間ドラマで数多くの読者を獲得している。本作もその系譜に連なる本格山岳小説だ。
「もともと山は好きで、学生時代から北アルプスや八ヶ岳あたりに入りびたっていました。これまでの作品でも『天空への回廊』をはじめ、山を舞台にしたシーンを書いています。好きな作家であるF・フォーサイスがヒマラヤを舞台にスパイものを書いたらどうなるか、最初はそんなイメージでした。でも、そういった謀略要素を抜きにして、純粋に山と山に生きる人々を描きたいとはずっと思っていて、今、その思いを形にしているところです」
孤高のクライマー・津田悟が北米最高峰・マッキンリーに挑み、消息を絶つところから物語は始まる。迫力満点の山の描写も勿論読みどころだが、悟や仲間がギリギリの局面で口にする、幾多の名セリフが胸に残る。

「考えたり、どこかで接したり、心の中に溜まってきた言葉が、ここにきて熟成されたように思います。この作品の中では、悟とアメリカ・インディアンの長老との対話の中で示される“握りしめた手の中には何もなく、開いた掌には世界がある”という言葉が好きですね。自然に向かう姿勢、宇宙の中の人間存在の意味を示唆しているような気がします」
そう、この作品は、山岳小説にして、人の生きる意味や生死について考えを深めるヒントに満ちている。
「私は『還るべき場所』の中で、山に登るという行為自体の中に人が生きる意味、“魂の糧(かて)”がある、と書きました。本作では、その生きる意味の本質的な部分に踏み込んでみたかった。山に登ることは、ある意味無意味なことかもしれない。でもそれは人生そのものを非常にピュアな形で凝縮した行為ともいえる。そこで主人公たちが苦しみ、悩み、互いに励まし合いながら前に向かい、1つになっていく。それは今生きている、あらゆる人間の人生の根っこの部分で共通する何かなのではないか……。その何かを『これだ!』と指し示せたかどうかはわかりませんが、それをさし示す指の形だけでも読者に読み取ってもらえたら嬉しいですね」










