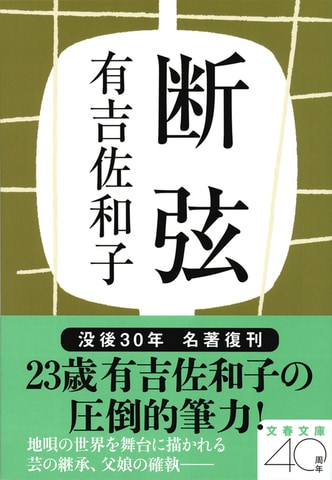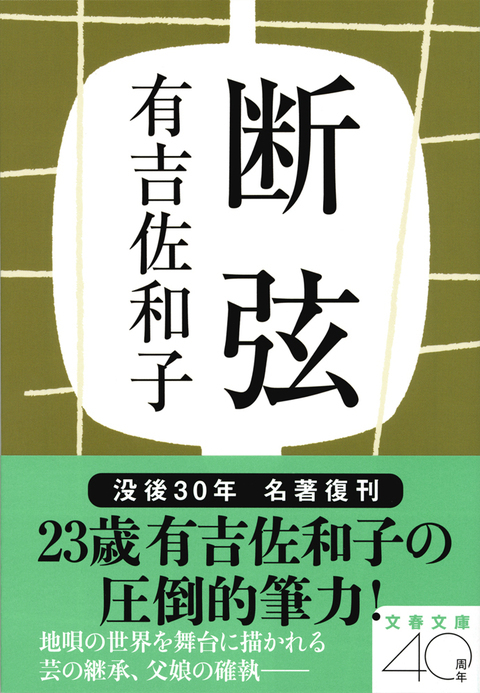本書の第一章を書いたのが二十二・三歳の頃だった、という著者による文庫あとがきを読んだ時、私は「えっ」と驚きました。そんなに若い時だったのか、と。
まずは地唄というテーマの渋さが、若者らしくありません。のみならず、二十代女性が書いた初めての長編小説とは思えない完成度の高い作品なのであり、著者の早熟な才能が、端々にほとばしります。しかし改めてこの物語を思い返してみると、やはり若い女性であるからこそ書くことができたものだとも、思えてくるのでした。
この物語は、新しいものと古いものとの対比と断絶を、描きます。地唄の世界の長老である、大検校菊沢寿久。彼が守ってきた古典的な作品の世界は、次の世代への継承が危ぶまれています。頼みにしていた娘の邦枝は、音曲の才を持つにもかかわらず、日系の米国人と結婚して、渡米。また期待をかけていた弟子の菊守光也は、伝統と離れた新しい芸の方向へ進もうとする……。
菊沢寿久が象徴する古い世界を、著者は闇によって表現します。大検校がこもる二階の部屋は、滅多なことでは人も立ち入ることができず、日中でも雨戸を閉じたままの、埃臭い場所。
対して、新しい人達の世界は、光に溢れています。結婚した邦枝が住む外国人向けアパートは、ま新しく白い天井の洋間に、すっきりと明るい調度。ダブルベッドには真っ白なシーツが敷いてあります。彼女達はそこから、さらにまぶしい「カリフォルニヤ」へと旅立っていくのです。また菊守光也にしても、銀座で開いた演奏会に、「純白の綸子の着物に、金襴の袴」という派手な格好で登場するのでした。
闇がそこにあるからこそ、隣にある光は際立ち、強く輝きます。菊沢寿久という闇がどろりと濃厚であるほどに、若い世代はその濃度に足をとられないよう光の世界へと進むことになり、両者の間の断絶は進行してゆきました。
今の時代、日本の伝統芸能の数々は、そのクラシックさがかえって魅力となって若いファンも増え、また後継者も育っているようです。欧米に追いつき、追い越そうと懸命になってきた一時期が終った時、自国を改めて見つめ直した日本人は、新鮮なアイデンティティとして伝統芸能を浮上させた、ということなのかもしれません。
しかし「断弦」が書かれたのは、戦争が終わってから約十年が経った頃のこと。日本人が、敗戦のショックから立ち直り、その遅れを取り戻そうと必死になっていた時代です。当時の日本人は、欧米、特にアメリカの方を向き、その明るさと豊かさを自らのものにしようと頑張っていたのではないか。
そんな中で、盲目の大検校の手による三味線の音は、いかに重く、古い響きを持っていたことか。多くの日本人は、古いものより新しいもの、暗いものより明るいもの、苦いものより甘いもの……を、求めていたのであり、そんな人々の気分によって、新しいものと古いものをつないでいた「弦」をつないでいくことが難しくなった。