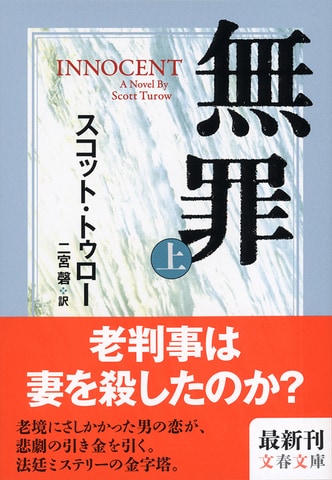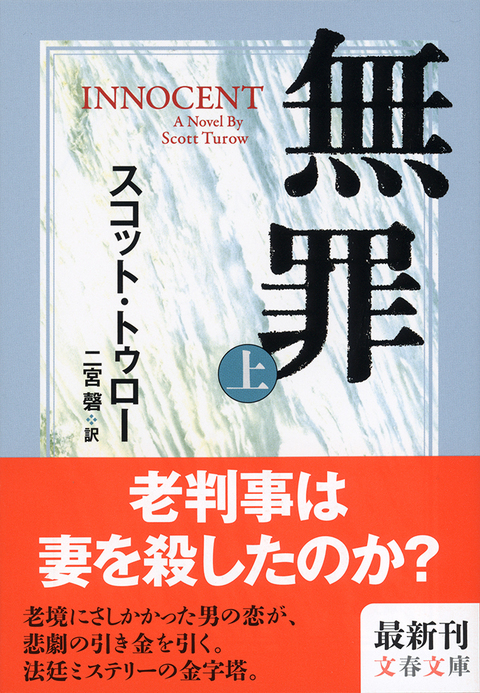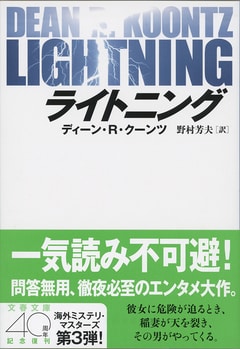本書を語るためには、まず『推定無罪』から語らなければならない。一九八七年度の英国推理作家協会シルヴァー・ダガー賞を受賞し、のちにハリソン・フォード主演で映画化された傑作である。我が国では一九八八年に翻訳されて、「週刊文春ミステリーベスト10」の一位に選ばれている。
当時の新刊評で私は次のように書いた。
「地方検事の座を争う上司と元同僚、そしてさまざまなタイプの警察官などを配して、地方都市のかかえる矛盾(それは現代アメリカのかかえる病巣でもあるが)を背景に、作者は巧みなドラマをつくり上げる。何といっても圧巻は法廷場面で、検事側があまりに都合よく失点を重ねすぎる点は気になるが、それを読者に意識させずに次々とたたみかけていく展開は、作者の筆力というものだろう」
スリリングな法廷場面を物語の核にすえる小説を「リーガル・サスペンス」と言うが、この名称が世間に流布されたのはこのころではなかったか。トゥロー以前にこの名称が広く使われていたのかどうか、詳しく調査したわけではないので断言できないが、この作品がその名称を広く流布させたきっかけになったような気がする。『推定無罪』はスコット・トゥローのデビュー作だが、それくらい画期的な作品であった。
後年になって、そのリーガル・サスペンス界の番付を作ったことがある。リチャード・ノース・パターソンとスコット・トゥローが東西の横綱で、スティーヴ・マルティニが関脇、フィリップ・マーゴリンが小結で、残念ながら大関は空位(グリシャムは十両だ)、というのがそのときの番付であった。新刊評で「何といっても圧巻は法廷場面」と書いたように、スコット・トゥローはスリルと躍動感に富む法廷シーンを描いて颯爽とデビューし、一気に横綱に躍り出たのである。
しかし、『推定無罪』が強く読者の胸に刻まれたのは、その法廷シーンが驚くほど鮮やかであったという理由だけではない。いや、実際にはその要素が大きいのだが、ここでは違う点を指摘しておきたい。スコット・トゥローの作品がリーガル・サスペンスとしていかにすぐれているかはいまさら私ごときが言うまでもなく、いまや常識とでも言っていいことなので、ここに書くまでもないのだ。というよりも、違う側面の、その話を書きたくて本稿を引き受けたのである。そういうきわめて個人的な話を今回は書く。ようするに、『推定無罪』が強い印象を残したのは、主人公サビッチのキャラに負うところが大きかったのではないかということだ。どういうことか。
この男、ダメ男なのである。そもそも『推定無罪』は、主人公の地方検事補サビッチが、不倫関係にあった同僚の女性検事補キャロリン殺害の罪で逮捕され、裁判にかけられる話である。妻がいながら他の女性にふらふらするのがダメ男だ、と言いたいわけではない。『推定無罪』の冒頭近く、キャロリンと別れたサビッチが、夜自宅で家族と食事するシーンがある。少し長くなるが、その箇所を引く。
「ナットが、三十分だけ許されているテレビを観に席をたったあと、どういうわけか、急に、わたしの抑制の“たが”がはずれた。月の光。この雰囲気。酒。心理学者なら遁走状態というだろう。食卓を呆然とみつめ、心はあてもなくさまよう。ハイボールのグラスを手にとる。キャロリンの家にあるのと同じものだ。それを見ると、彼女のことが強烈に思い出され、突然、抑えきれなくなって、泣きだした――そこに坐ったまま、嵐のような感情に身をまかせて泣きじゃくったのだ。とたんにバーバラはさとった。彼女はわたしが病気だとは思わなかった。疲れや、公判の緊張や、涙腺の異常だとも思わなかった。妻にはわかったのだ。わたしの嗚咽が、恥からではなく、喪失感からだということが」