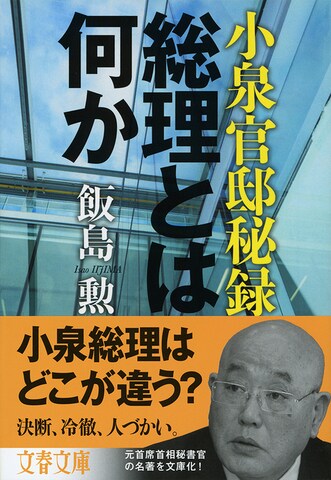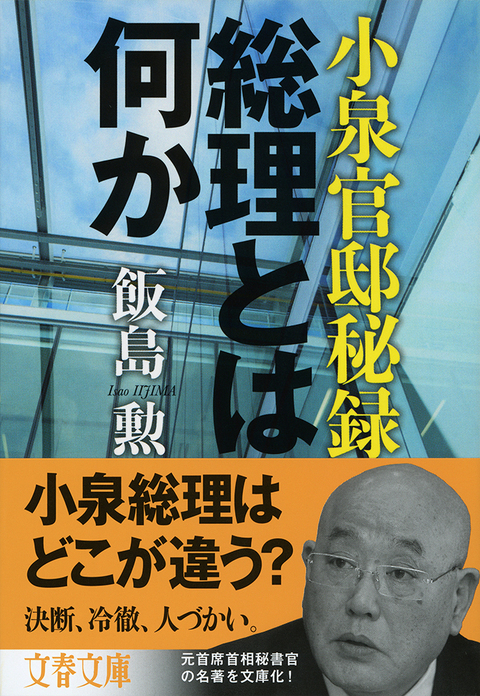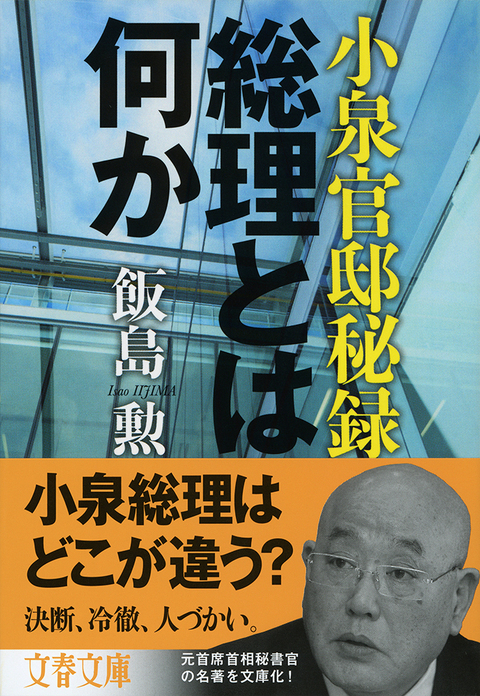
政治を評論する立場となるルートは大きく分けて五つある。政治学者、官僚、政治記者、そして政治家、その秘書だ。学者や官僚、記者が外側から見ているのに対し、政治家や秘書は内側から見ている。その分、外側からは見えない事実を知ることができるのだが、客観性や洞察力に欠けるという陥穽にはまりやすい。
その罠にかからずに、時代を超えて読み継がれていく本がある。現象から導き出される普遍性、すなわち時代が変わろうとも変わらない本質が描かれていれば風化に耐えられる。たとえば、西日本新聞社の記者出身で、池田内閣で飯島勲と同じく首席首相秘書官を務めた伊藤昌哉は『実録 自民党戦国史─権力の研究─』(朝日ソノラマ)で権力闘争の本質、政治家のすさまじさを描いた。
「政治は感情だ、これがしこりとなって固定すると、いつか政争への火種となる」
「人事ほど、首相の肚を端的に物語るものはない」
私は田中派や竹下派の分裂、自民党総裁選などさまざまな権力闘争や組閣、内閣改造・党役員人事を見るたびに、伊藤の言葉を何度となくかみしめた。伊藤はさらにこう書いている。
「新聞記者はいろいろと記事を書き、日々の歴史を綴って一応の答えを出してはいるが、いずれもその場かぎりの答案ではないだろうか」
我々記者は幅広く取材し、バランスが取れた見方のもとに報じているという自負心を持っている。しかし、記者の一人として、伊藤の指摘を受け入れざるを得ない。懸命に取材し、真実に肉薄したにしても、その場にいたわけではないので、内部で観察していた人に比べたら、残念ながら劣る。
首相経験者ら政治家本人が書くのが一番正確と思うかもしれない。だが、政治家自身が書く場合、往々にして自分に都合が悪いことは触れず、都合の良い事実を書き連ねることで、自分をプレーアップする。政治家の自画自賛から脱却した本は『指導者とは』(リチャード・ニクソン、文春学藝ライブラリー)、『岸信介証言録』(原彬久編、中公文庫)など数少ない。
しかも、記憶は嘘をつく。人一倍自尊心が強い政治家は悪気があるわけではないが、不都合な事実を封印しているうちに忘れ、都合が良い事実だけを覚えている。そういう意味において、首相秘書官が主と距離を置いて見る観察眼が備わっているなら、政治の実態を書き残す意味は大きい。
嘘の度合いは時を経るほど大きくなる。この点、『小泉官邸秘録』は小泉純一郎が自民党総裁任期満了に伴い、首相の座を去った直後の二〇〇六年一二月に出版されている。生々しい記憶が残っている時期だ。
同書は、首相官邸で、次々と降りかかってくる難題にいかにして立ち向かったかを描いている。
小泉政権は「官邸主導」が定着した、初めての政権だ。田中派や竹下派全盛時代の党主導でも、財務省を頂点とする官僚主導でもなく、首相が決めたことが政府の方針となった政権だった。その装置は二つあった。