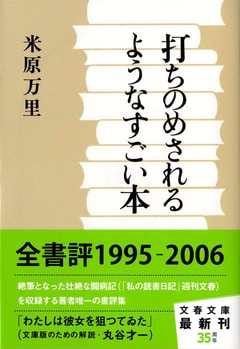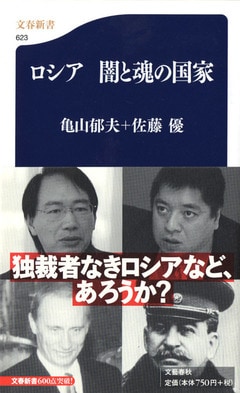類い稀な才能を持つ米原万里さん(一九五〇年四月二十九日~二〇〇六年五月二十五日)が亡くなって、ちょうど十年になる。米原さんは、エッセイスト、小説家、ロシア文学者、ロシア語の翻訳者、会議通訳者など、いくつもの顔を持っていた。しかし、米原さんは、本質において表現者で、どのような形態をとるかについては、実のところ無頓着だったのだというのが私の認識だ。
現代作家で、死後十年を経ても、その作品が読み継がれている人は少ない。米原さんの作品は、著者が生きているときと同じように毎年、新たな読者を獲得している。なぜか? 私の理解では、米原さんの言葉に独特の力を伴った魂が宿っているからだ。この言霊(ことだま)の力は、米原さんの人間観と深く結びついている。米原さんは、ヒューマニストだった。徹底したヒューマニストは、神を信じないし、神の存在も認めない。それは、神を持ち出すことで、思考の中断が起き、その結果、人間が人間の可能性をあきらめることがあるからだ。そうあってはならないと米原さんは考えていた。米原さんは、他者に対して優しい人だった。表面的には厳しいことを言う場合も、あるいは毒舌で時の為政者を批判しても、その根底には人間を信じている人が持つ独特な温かさがあった。
米原さんが亡くなる四カ月くらい前のことだったと記憶している。「話があるから家に来て」という電話があったので、私は鎌倉の米原邸を訪ねた。米原さんは、だいぶ時間をかけて二階の寝室から一階の応接間に杖をつきながら降りてきた。
「杖をつくような状態になっちゃったのよ。それにしても、ガンは痛くて苦しい。今までみんなによくしてもらったし、もう向こう側に行ってもいいと思うのよ。生きていて本当に良かった。みんなに感謝しているのよ」
米原さんは、笑みを浮かべながらこう言っていた。私はその姿を目の当たりにして、もし自分が末期ガンで、持ち時間がかなり限られているという状況になったとき、「生きていて本当に良かった。みんなに感謝している」と言えたであろうかと自問自答した。そして、恐らく言えないであろうと思った。それは、私がどこか根源的なところで、人間を信じていないからだ。
このとき、私は、米原さんと作家としてかなり根源的な話をした。「どういう人の言葉を信じることができるか」という問題について話し合った。具体的には、チェコからフランスに亡命した小説家ミラン・クンデラについてのやりとりが印象に残っている。