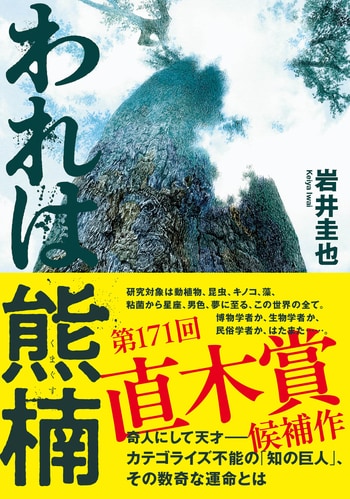◆南方熊楠を描くなら自分の手で
――岩井さんは毎作新しいことに挑戦されていて、新作の『われは熊楠』は初の評伝小説です。以前から知の巨人、南方熊楠に興味があったのでしょうか。
岩井 作家になる前から、いつか熊楠を書かなきゃいけないと思っていました。というのも、両親が和歌山の出身で、特に母方の実家は、まわりに南方姓がいっぱいいる地域だったんですよ。それで私も幼い頃から「南方といえば南方熊楠という人がいて」という話をよく聞いていました。その後、熊楠は在野を貫いた異形の研究者なのだと知って、ますます興味を持つようになって。
熊楠はあらゆる分野を横断的に研究していましたが、なかでも菌類・粘菌・淡水藻の研究に熱心でした。私も大学時代、バイオテクノロジーがやりたくて農学部に進み、応用菌学の研究室でカビやバクテリアといった微生物の研究をしていたんです。だから、もし熊楠を書くなら絶対に自分の手でやり遂げたいと思っていました。彼と重なる部分の多い自分になら、深く書けるのではないかと。
とはいえ、南方熊楠というのは、そう簡単に理解しきれるような人ではありません。自分は二〇一八年にデビューしたばかりの新米だし、いまの筆力では書ききれないかなとも思っていました。

――在野の博物学者であり民俗学者であり生物学者だった熊楠については、すでに本人の著作も関連書もいろいろありますよね。
岩井 そうなんです。熊楠自身による膨大な量の研究記録が残っています。でもそのわりに、内容については一般にはあまり知られていないんですよね。天才とか奇人といったイメージばかりが先行していて。小説で書かれた例もあまりなくて、神坂次郎さんの『縛られた巨人』と津本陽さんの『巨人伝』くらいだと思います。あとは、『週刊少年ジャンプ』で連載されていた『てんぎゃん ――南方熊楠伝――』という岸大武郎さんの伝記マンガがあるぐらいで。
小説の世界で熊楠を書く人が少ないのには、いろいろな要因があると思います。何より、書きどころが多すぎるんですよ。熊楠の人生って面白いことがありすぎて、全部書きたくなっちゃう。孫文と仲が良かったとか、アメリカへ留学していた頃、旅先のキューバでサーカス団についていったとか、伝説には事欠かない。彼の身に起きたことを順番に書くだけで十分に面白いので、小説としての切り出し方が難しいんです。わざわざ小説にする意味がないといえばない。
でも私は研究者としての熊楠はまだ「未踏の山」だと思っていました。後世の人が〝発見〟できていない熊楠がいるのではないかと。一年間ほど準備期間をもらえたので、その間にプロット以前の、資料を読み構想を練る作業に没頭しました。たとえば熊楠は「事の学」という独自の学問構想を持っているんですが、それは一体どういうことなのか、自分なりに生物哲学や科学哲学の本を読んで考えたりして。そこから、熊楠の人生における要点を整理し、どこを抜き出すかを編集者と議論しながら、たたき台を作っていったんです。二〇二二年の秋には和歌山にも取材に行きました。
――熊楠は和歌山県に生まれ、一度上京した後にアメリカやイギリスに留学し、帰国後は那智の山中にこもり、のちに下山して田辺で暮らしました。たとえば本作では、アメリカ時代の出来事はほとんど書かれていませんよね。
岩井 熊楠の生涯で動きがあって楽しいのは、海外遍歴の期間なんですよね。ただ今回は、研究者・熊楠として重要なステージはどこか? ということに焦点を絞ったので、アメリカ時代にはあえて踏み込みませんでした。
人間・熊楠としては、その時代にも何かエポックメイキングなことがあったかもしれないけれど、研究者・熊楠としてはそうではないのかもしれない。だから思い切って切り落としたんです。
帰国した後は基本的に和歌山の田辺から動かなかったようですね。結婚して子供が生まれて、世間一般の暮らしというか、見ようによっては地味な生活を送っていく。この時期は熊楠にとって、挫折の期間だったはずなんです。でも様々な資料を読んでいくうちに、この後半生こそ、彼が探し求めていた真理にたどり着く過程であって、研究者としては実り多い季節だったのではないかと思うようになりました。

――文体や視点に関してはどのように決めていったのですか。
岩井 かなり迷いましたね。だから最初期に、絶対に書きたいという場面を書いてみては確かめる、スケッチのような作業を繰り返しました。地の文もセリフも全て紀州弁にしたり、逆に標準語っぽくしたり。現代文だったら「いらない」と書くところを「いらぬ」として講談口調にしてみたり……。結局、地の文は第三者が講談寄りの口調で語っている形、セリフは誰もが最低限の意味がわかるくらいの紀州弁にしました。紀州弁には独特なリズムがあり、関西弁とは全然違うので、結構苦労しましたね。
◆熊楠こそ本当の〝学問〟をやってのけた人
――セリフといえば、本作で熊楠はよく幻の声に惑わされたり、導かれたりしますよね。彼はそれを「鬨の声」といっている。
岩井 あれは創作です。ただ、熊楠にはてんかんがあったと言われていて、その症状のなかには幻聴もあるそうです。彼の深い思考の裏付けとして、頭の中で声が聞こえていたという設定にしました。「鬨の声」と呼ぶことにしたのは、熊楠の少年時代の日記に『太平記』を読んだと書かれていたからです。『太平記』は戦争の話ですから、クライマックスに入るとすぐ鬨の声が上がるんですね。有象無象の人たちが思い思いに声を上げるイメージが、その時に考えていた文体とすごく合いました。
――もうひとつ印象深かったのが、熊楠が見る夢が随所に出てくることです。少年時代に親しかった羽山繁太郎・蕃次郎兄弟がよく夢に出てくるのですが、いつも彼らが非常に示唆的なことを言う。
岩井 夢の内容は創作が多いですが、熊楠が羽山兄弟の夢をよく見ていたのは事実です。兄弟の生前も死後も彼らの夢を見ていたこと、それが性的なニュアンスをおびていたことは日記に残っています。作中でも触れた、繁太郎が夢に出てきて「ここを探すといいよ」というのでそこに行ったら新種の生物を発見した、というエピソードも手紙に記されていて。こういった不思議な体験から、熊楠は夢についても研究していたようです。
――創作と事実のバランスはどのように考えていましたか。事実を改変するのは難しいので、どうしたのかなと。
岩井 そこは難しかったですね。熊楠は基本的に十代のときから死ぬまでずっと、毎日日記をつけているので、小説のなかで噓をつけない、つまり創作の余白が少なかったんです。たとえば「イギリスにいた時期に一回帰国しています」といった、明らかに事実に反することは書けません。なので、どこで噓がつけるかを謎解きパズルのように考えていきました。そのなかで、夢の内容や「鬨の声」については創作する余地があったんです。
ただ、噓がつけないからこそ、事実から着想を得ることもありました。たとえば日記に「雪が降っていた」という記載があったら、じゃあこの日のこれはこういう場面になるな、とか。事実や史実をもとに想像を膨らませていくのはゼロから作る小説の時とはまた違う経験で、歴史小説を書く楽しさってこういうことなのかなと、初めて実感しました。

――熊楠はとにかくインプットの量が半端ではない人です。古今東西の学問に通じ、多くの言語を操っている。科学雑誌『ネイチャー』にも多くの論文を投稿していたという。
岩井 そもそも熊楠って、今の基準から考えると、研究者と断言していいのかわからない人なんですよ。今の研究者というと、たとえば理系の人だったら、仮説を立てて実験をして、その結果新しい法則の科学的な裏付けが取れましたとか、この生物にこういう特徴があるとわかりました、と論文で発表するイメージがありますよね。でも熊楠の場合は、極端なことをいえば、ただ情報を集めただけの人ともいえる。もちろん論文もいっぱい書いていますが、テーマを提示して「西洋にもこんな例がある、東洋にもこんな例がある。以上」みたいなスタイルなんです。要は羅列ですね。正直、今の時代だと、論文として受理されるかどうかすらわからない。でも、それがすごく面白いんです。
たとえば彼は日本に帰国後、燕が石を運んでくるという民話や俗説が各地に多数あることについての論考『燕石考』を完成させます。ここでは、物語や説話についてだけでなく、燕石として伝わっているのはどういう石なのか、といった理系的、博物学的な知識も盛り込んでいる。つまり、いろんな学問がごった煮になった状態で提示されているんです。これって、学問領域が細分化された今の研究者には難しい仕事なんですよ。裏を返せば、当時は学問領域が未分化だったからこそ、熊楠は学会のルールや学問領域に頓着せずに、世界をひとつのものとしてとらえていたのかもしれません。ひとつの分野の専門知識に基づいて世界を見るのでなく、いろんな専門分野の視点をもって世界を見ることができる、そのスケールの大きさは今の時代の科学者にはないもので、そうした研究者としての在り方に僕は大きな魅力を感じました。
――今の時代だったらネットを駆使して、ある程度までは誰でもいろんな情報を集められるだろうな、とも思うわけですが。
岩井 そうですよね。でも逆に、ネットでは拾いきれない情報もあるのかな、とも思うんです。熊楠は書物から得た情報だけでなく、あの博物館にこういうものが展示されていた、といったこと、つまり生の情報も膨大に引っ張ってくるんですよ。ネット空間では誰かが情報をアップしてくれないと検索できないわけですが、熊楠は自分の足で情報を取りに行っていたので、情報量がけた違いに多いんです。だから仮に世界中の書物が検索できたとしても、熊楠の論文は書けない。そこがすごいと思います。
それに熊楠は、たとえば今だったら「燕の石」で検索して集められるような情報だけでなく、燕の生態はこうです、といった枝葉にまで話を広げることができる。通り一遍の知識ではなく、いろんな角度に飛んでいけるし、それがゆえに考察もものすごく立体的です。

――世界のすべてを知りたがった熊楠が、粘菌に着目していくのが面白いなと思いました。ある意味、マクロからミクロにいったというか。ただ、マクロを知るためにはミクロを知らなければならないともいえます。そのあたりは研究者だった岩井さんにもわかるところがありますか。
岩井 わかります。作中にも書きましたが、たとえば熊楠は「(粘菌は)生と死の意味が逆転している」と書いています。粘菌には主にふたつの形態があって、子実体というキノコみたいな形でじっとしている期間と、変形体というアメーバ状になってエサを捕食する期間がある。これを交互に行ったりきたりしながら生活している生き物なんですよね。当時の価値観でいうと、変形体は「不定形の痰」のようで「その姿はいかにも死物を連想させる」、一方でキノコっぽい子実体は、「すっくと生えた」かのようで生きている感じがすると。でも粘菌自身からすると逆で、変形体は活発に動き回りエサを捕食する活物としての時期、子実体は消耗を防ぐ死物としての時期なわけです。つまり熊楠にとって、粘菌は生と死が裏返った不思議な存在で、「地獄の衆生を連想する」、と。「人の世で罪人が死にかかると、地獄では新たに衆生が一人誕生する」というやつです。僕はこの解釈がすごく面白いなと思いました。粘菌そのものはミクロの世界ではあるけれど、生物の大きな流れ、生命というマクロな世界を考える上で象徴的だと思います。
◆葛藤し、評価を渇望する姿もまた描きたかった
――少年時代の熊楠は純粋に知的欲求だけに突き動かされていた印象ですが、大人になるにつれ「認められたい」欲が強くなっていくように感じました。それも実際に日記などから感じ取ったことなんですか。
岩井 そうですね。熊楠はお上嫌いで、その性格は後の合祀反対運動などに表れていきます。ただ、お上嫌いといっても、そう単純な話ではなくて、内心はおそらく結構複雑だったと思うんです。つまり、自分が学会で認められなかったが故に反発したい気持ちと、そうはいっても認めてほしいというアンビバレントな気持ちに苛まれていたのかなと。特に田辺に移ってからは、粘菌の研究について、たとえば手紙に新種の発見を横取りされることを恐れるような趣旨のことが書いてあったり、言葉の端々から名誉欲のようなものが読み取れることがあります。そもそも粘菌や隠花植物に着目したのも、まだ誰も深く研究していない領域で、自分が第一人者になれるから――というのもあったと思うんですよね。人生の後半に差しかかって、ただ己の好奇心を満たしたいというよりも、自分が最初の発見者になって世の中に認められたいという欲には抗えなかったんだろうと想像しています。
――家族との関係も「そうだったのか」と思うところが多々ありました。跡継ぎのお兄さんがお金にルーズだったこととか、弟が献身的だったこととか……。
岩井 家族についての描写はほぼ史実通りで、お父さんは立派な経済人で事業家でした。ただお兄さんは形だけ父の跡を継いでいるものの、相場と女に目がなく、金の管理は全くできない人だったようです。最終的に、家督は弟の常楠が継いでいます。
熊楠が常楠と後年揉めたことも事実で、それは手紙にも残っています。揉めた理由はどれも、仕送りを停止するとか、寄付のお金をやったやらないとか、お金まわりのことですね。
――常楠は幼い頃、兄のことを「天狗」と呼んで尊敬していたのに。兄に失望していく様子がつらいですね。
岩井 常楠が幼い頃に熊楠に憧れていたとか、神隠しにあったというのは創作なんです。実はここは、かなり改稿を重ねたところで。事実、常楠は後年、急に手のひらを返して熊楠の援助を止めています。たしかにそれはお金が限界だったからという理由が最も大きいと思いますが、それだけではないんじゃないか、と編集者と話し合いました。その時に確か、アイドルなどの推し活の話になったんですよ(笑)。神格化し、惚れ込んでいたアイドルが、急に俗っぽい感じになったら嫌だよね、とか。常楠も、兄に対してすごく憧れがあったからこそ、家庭を持ったり、社会と折り合いをつけていく様子にかえって心が冷えていったのかもしれない、と想像して。

――最初は距離があった妻の松枝との関係の変化も面白かったし、優秀だった長男との確執は切なかったです。
岩井 もちろん史実を踏まえていますが、松枝に関しては、常楠と同じくらい改稿しました。まあ、松枝と常楠はこの話の中の二大苦労人ですよね(笑)。
実際、松枝自身も、すごく菌を採集しているんです。それに熊楠の死後、彼が残した標本や蔵書を欲しがる人がたくさんいたのに、彼女は一切売らなかったんですよね。もちろん、熊楠に対する愛情もあったんでしょうけれど、それだけじゃなくて、自分も研究に携わってきたという自負があったのではないかと思って。当初は傍観者だった松枝が、主体的に研究に携わっていくようになった過程は描きたいと思い、今の形になりました。
それに松枝が神社の娘だったのは、のちに熊楠が神社合祀反対運動に熱心に取り組んだこととなにか関係があったような気がしてならないんですよね。実際のところはわかりませんが、その繫がりはきちんと書いておきたいなと。
――熊楠は神社の統合が進められた時、自然が破壊されるといって反対運動に傾倒していったといわれています。そのことで熊楠というとエコロジストというイメージも強くなったわけですが、そこも丁寧に書こうと思われていたのですか。
岩井 合祀反対運動をきっかけに、熊楠が社会的な人間になっていくところは重要だと思いました。それまで那智の片隅に閉じこもって独りぼっちで研究していた人が、合祀に反対することで、町の人や新聞社の人間と付き合いだすようになるわけですから。
熊楠はすごく筆まめで、神社の人はもちろん、自分と同じ合祀反対派の人に積極的に手紙を送ってネットワークを作っていきます。それもあって社会的に名を知られるようになり、新聞で特集が組まれるようにもなる。だからこそ彼の中に俗っぽい部分が出てきて、常楠との確執も生まれるわけです。合祀反対運動なくしてその後の熊楠はないんですよね。少なくとも今ほどの知名度はないと思います。
彼のそうした後半生を書くことで、落胆する読者もいるかもしれないとは思ったんですよ。なんだ熊楠も一人の人間じゃないか、と。でも、今回はそこを書くことこそがすごく大事だと思っていました。肉親との葛藤や、困窮との闘い、評価への渇望、そうしたものを抱えて生きる一人の人間であることを描き、我々と地続きの人間であることを知ってもらってこそ、彼が見ていた景色や、研究の喜び、悲しみが伝わるはずだからと。
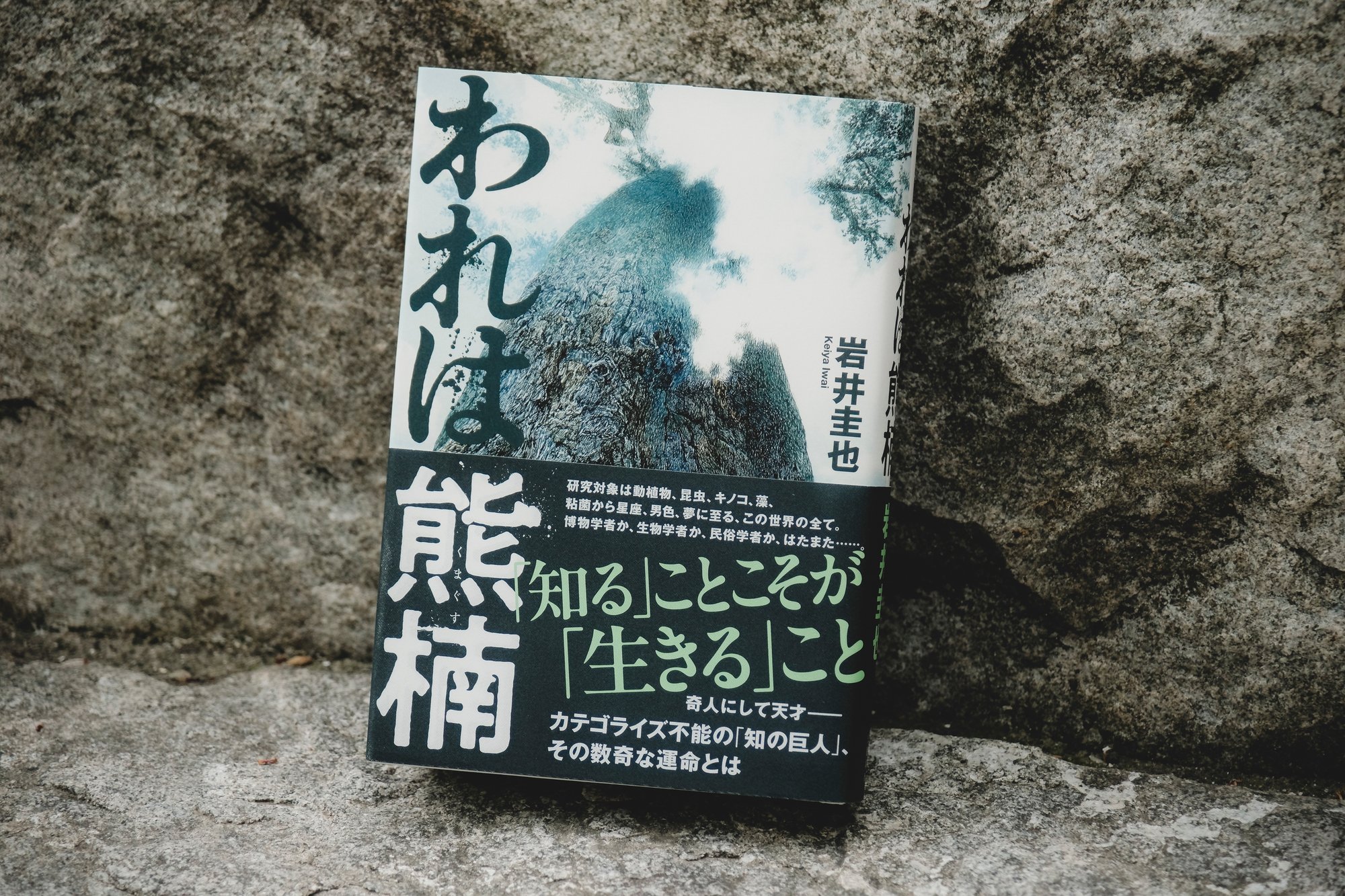
――彼の研究者としての姿勢の変化を見て、学問ってなんだろうと思いました。
岩井 私もこれを書いている時に、学問ってなんだろうとずっと考えていました。一応、文部科学省が提示している学問の定義があって、ホームページに載っているんですよ。「学問の意義は、人類の知的認識領域の拡大である。それは、個人の知的好奇心を満たすということを超えて、人類共有の知的財産の拡大を意味している」と。今学問をやっている人のなかで、どれだけの人がこの根源的なことを意識しているんだろうとも思うんです。
そしてこの文科省の文章を踏まえると、熊楠のやっていることって、まさに学問だと思うわけです。個人の知的好奇心から研究を始めて、それがのちにどんどん社会に開かれていく過程って、まさに「人類の知的認識領域の拡大」だと思うんですよね。その意味では、熊楠は間違いなく、学問中の学問をやっていた人だと思います。彼が書いた論文なんかは、今の基準に照らすとちょっと違うよね、となっても、学問の本来あるべき姿を考えると、熊楠のやっていたことは正しかったはず。なのでこの小説は、熊楠が個人的な興味から研究を始め、やがて本当の学問、つまり自分の研究によって、人類みんなが共有できる知的財産を拡大することの面白さに目覚めていく過程を描いたものと言えるのかもしれないですね。
◆これほど〝岩井圭也〟が投影された小説はない
――書いてみて、熊楠のこういうところが好きだな、と改めて思ったところは。
岩井 やっぱりひたむきさですね。少年時代から死ぬまで、知的に何かを求めるという姿勢が一貫して変わらなかった。人って成長する中で、「自分はこれに向いているのかな」「これは向いていないのかな」などと寄り道しながら、ちょっとずつ自分というものを形成していくものだと思うんですが、熊楠は少年時代からもう完全に熊楠で、芯がぶれない。
私は一貫している人が好きなのかもしれないですね。迷いながら進む人のほうが人間臭いとは思うのですが、なぜだかずっと同じものを核として握り続けている人に惹かれてしまいます。

――岩井さんも小説を書くことはずっと一貫してきたのでは。小学生の時に書き始めたんですよね?
岩井 そうですね。雑誌『小学三年生』に連載されていた北森鴻先生の『ちあき電脳探偵社』が好きすぎて、連載が終わってしまってから自分で続きを書きはじめたのが最初です。
それからずっと小説は書いていましたが、普通に遊んでいた時期もあるんですよ。北大の剣道部に入って学生生活が楽しくなってしまって(笑)。それに文筆の道ではなく、博士課程に進学して研究者を目指そうかと迷った時期もありました。でも、紆余曲折しながらも小説を書くことに戻ってきたのは、やはり自分にとっては書くことしかなかったんだろうなという気がします。
もちろん、熊楠にも挫折はあったんですよね。『燕石考』が認められなかったり、海外の学術誌に送っても送っても論文が受理されなかったりして、本来思っていた形の研究者ではなくなっていった。那智の山中から下山した後、一年間くらいは捨て鉢になって飲み歩いていたらしいです。那智の山に入る前にも、飲み歩いている時期がありました。でも、結局研究に戻っていったんです。そういうところも自分と結構重なるなと感じます。なので『われは熊楠』には、どこか自分を投影した部分がありますね。研究者としても、子供への接し方などにしても、自分もこうしただろうなと思うことが多い。これはもちろん評伝小説なんですけれど、結果的にこれまででいちばん〝岩井圭也〟が投影された小説になっていると思います。
――岩井さんも結局書くことに戻り、デビューを果たし、そこからは毎回毎回、まったく切り口もテイストも異なる作品を発表し続けている。題材は自分発信と編集者からの提案と、どちらが多いのですか。
岩井 自分発信が多いです。編集者に提案するときも、「現代小説と恋愛小説と経済小説と歴史小説とそれぞれ種がありますが、どれがいいですか」みたいに相手の希望を訊いたりする。
でも最近は編集者からテーマの大枠をもらうことも増えてきましたね。「現代的な小説」とか「岩井さんの人生の根源に迫るような小説」みたいな感じで。
――「人生の根源に迫るような小説」って、どんな小説になるんですか。
岩井 実はこれから書くつもりなんですけれど……。私はこれまで自分の人生経験を直接反映して書いたことがなかったので、技術職としてやってきたことを反映させたものを考えています。
――それにしても、ライトな読み心地のものから重厚な作品まで、ジャンルレスに書かれていますよね。
岩井 岩井圭也ってどんな作家なのか、読者にわかってもらえないんじゃないかという恐れみたいなものはあります。たとえばこの人は本格ミステリを書く人だ、とかホラーを書く人だ、と認識してもらったほうが読者におぼえてもらえるんだろうし、ジャンル横断型だと、編集者にとっても売りにくいだろうなという悩みはあります。
――それでも、毎回違うモチーフを思いついてしまう。
岩井 しまうんですよね(笑)。しまうし、それぞれのテーマと格闘していると、毎回自分の違う面が引き出されるような感覚があるんですよね。だからやめられない。こうなったらもう変に自分を縛るのはやめて、流れに身を任せて書いていったほうが、成長できるのかなと思ったりしています。開き直って、その結果、〝岩井圭也〟というひとつのジャンルが生まれることを目標にしてやろうかなと。
――では今後の具体的な執筆・刊行予定は。
岩井 刊行予定としては、これから十一か月間、毎月なにかが出ます。たとえば六月には、二年前に出た『最後の鑑定人』(KADOKAWA)のシリーズ最新刊『科捜研の砦』が出ますし、七月には角川春樹事務所から「横浜ネイバーズ」シリーズの第五巻が出ます。『コフレ』(祥伝社)で連載していた舞台女優の話『舞台には誰もいない』も本になりますし、幻冬舎からは読書会をテーマにした連作短篇集『深海ブッククラブ』が出ます。来年はSFも出す予定です。
撮影:佐藤亘
岩井圭也(いわい・けいや)
1987年生まれ。大阪府出身。北海道大学大学院農学院修了。2018年『永遠についての証明』で野性時代フロンティア文学賞を受賞し、デビュー。23年『完全なる白銀』で山本周五郎賞候補、『最後の鑑定人』で日本推理作家協会賞候補。24年『楽園の犬』で日本推理作家協会賞候補。その他の著書に『水よ踊れ』『生者のポエトリー』『付き添うひと』『暗い引力』「横浜ネイバーズ」シリーズなど多数。24年5月、『われは熊楠』刊行。