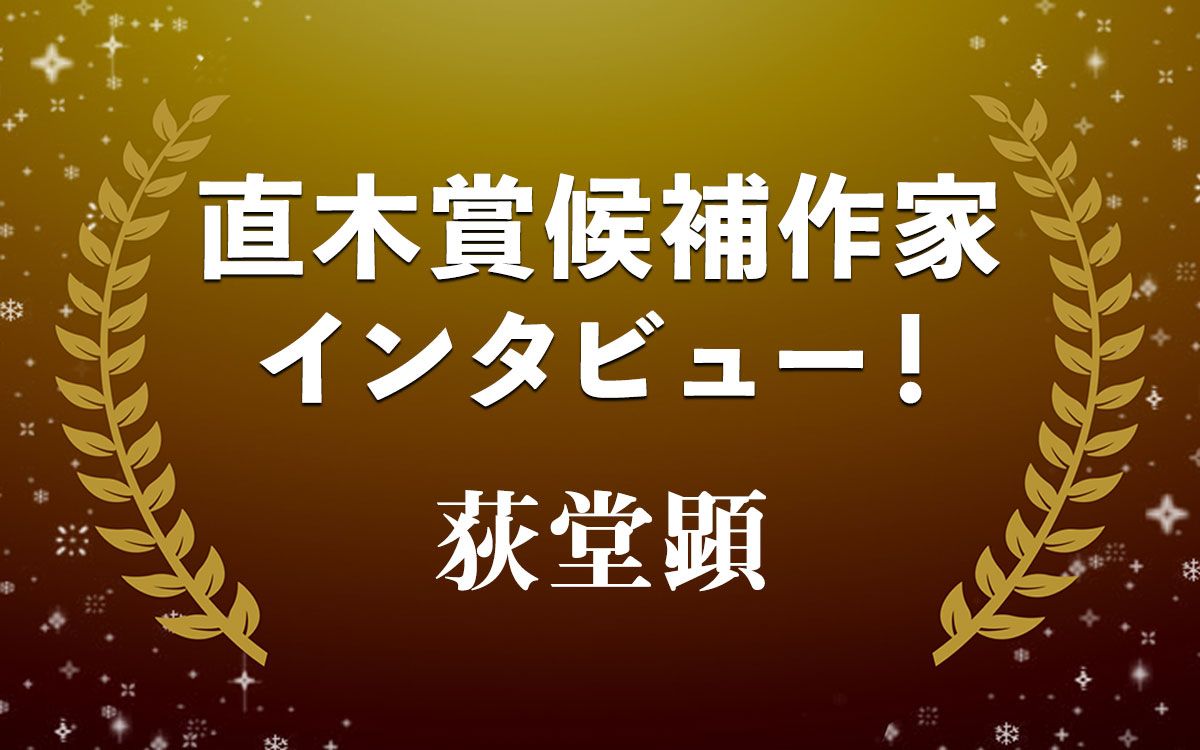荻堂顕『飽くなき地景』(KADOKAWA)
現実の補助線
振り返ってみると、一番多く本を読んでいたのは高校生の頃かもしれない。学校への行き帰りの電車、授業中、「怪我のリハビリ」と称して部活をサボっているとき、読書に充てられる時間が多かったからだと思う。僕は個人的な信条として、何かを始めるのに「遅すぎる」ということはないと考えているのだが、小説家になりたいという方の「子供の頃から本を読んでいた方がいいですか?」という問いにだけは「そうだと思います」と答えるようにしている。
基本的に、小説は「大人の読者」を想定している。書き手も大人だからだ。ファンタジーの世界は大人が読んでもフィクションだけれど、高校生の頃に読む「大人の世界」は、大なり小なりフィクショナルに感じられる。その時点では経験しえない出来事があり、感情があり、全てを理解することは難しく、想像力を働かせるしかない。僕は「大人になる」ということは、想像力を働かせなくてはならない状況において、参照できるリソースが増えることなのではないかと考えている。「この問題、進研ゼミでやったことある!」的に、パターンとして理解できるようになってくる。しかしそれは、必ずしも想像力を働かせた結果とは言えないはずだ。
小説の世界はフィクションだけれど、そこで描かれている人間の感情は、その物語のなかにおいては本物だ。少なくとも、僕は書き手としてそうしようと心掛けている。そもそも、他人を正確に理解することは不可能で、他人の人生はある程度(自分からしてみれば)フィクションと言える。小説は、現実世界の他者を理解するための補助線として機能してくれるのだ。
話を冒頭に戻す。あなたもそうだと思うけれど、僕は人が嫌いだった。今でもそんなに好きじゃない。それでも本を読むのが好きだったのは、逃避できる場所を求めていた以上に、心の底では「誰かと関わりたい」と強く願っていたからだと思う。高校にいたトレーナーの先生は、部活をサボってシュリンクの『朗読者』を読んでいた僕を咎めたりせず、最後まで放っておいてくれた。読み終えて帰るとき、無性に「誰かと話したい」と思った。その気持ちは今でも忘れていない。
(初出:「オール讀物」2025年7・8月号)
第13回(2026年)高校生直木賞の応募はこちらから