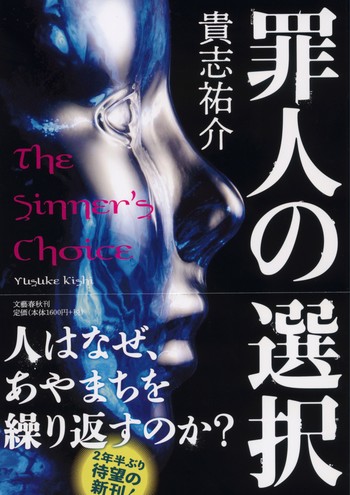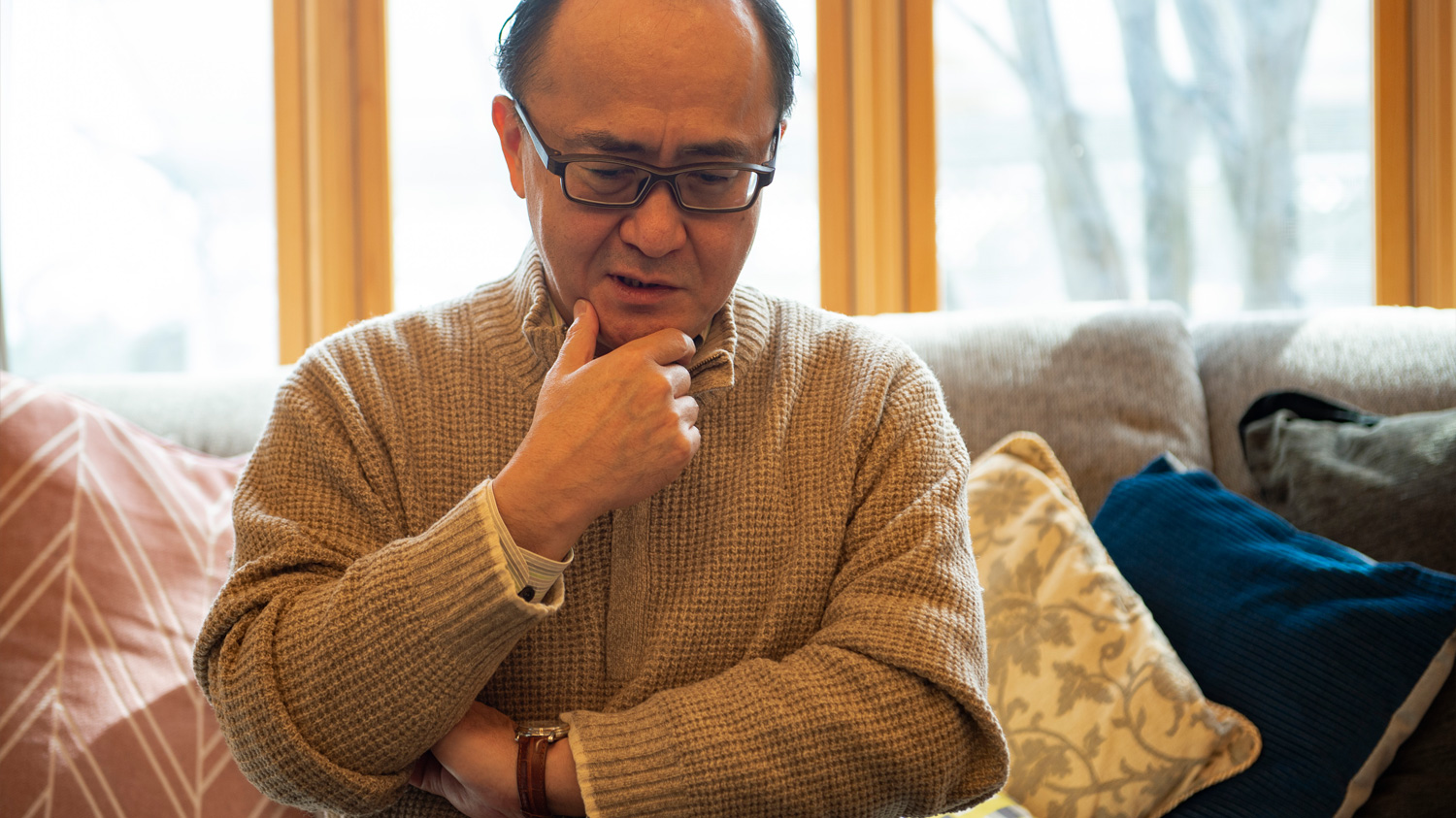――ネヴィル・シュートですね。
貴志 そうです。あれも、なんでもない日常が失われる時にはじめて、それがいかに貴重なものだったかが分かる。なんですかね、美しいガラスの器が砕け散る瞬間に一番光を放つみたいな、そういう感覚が好きなようです。
――また、「赤い雨」だけでなく他の作品でも、貴志さんは生物学的なものの知識をお持ちだなあ、と。
貴志 生物は非常に好きで、いろんな本を読んでいます。でも以前はこんな生態の生き物がいるなんて、と驚くだけで思考停止していたんです。でもある時リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』を読んで、全部腑に落ちたというか。結局、遺伝子以前に、安定的なパターンの存続というものが、宇宙の絶対的な真理だなと思いました。安定的なパターンというのは、なかなか壊れないパターンと、自分を複製するパターンの二通りあります。それは善でも悪でもなく、宇宙の根本原理みたいなものですね。非情なメカニズムです。

――どれも中短篇にしておくのはもったいないほど世界観が丁寧に作られていますが、小説を書く際、事前に設定やプロットはかなり綿密に作りますか。
貴志 書く時は理屈というか論理が中心にあります。起承転結より先にテーマがある。それを凝縮させるために、事前に設計図は作りますが、やっぱり途中で変わってしまいますね。駄目な場合は最初の見通しが甘くて設計図通りにならなかったからですが、そうではなく、時々登場人物が自己主張しはじめて別の方向に行くことがあります。そういう時は、最初から最後まで設計図通りに書く時よりも、物語が活き活きしてくる気がします。「赤い雨」に出てくる、瑞樹の恋人の光一という人物も、最初にストーリーを走り書きした時はもっと嫌な奴だったんです。それが書いているうちに変わりました。他に、たとえば『悪の教典』だと、簡単に死んでしまうはずの人がなかなか死ななかったり、殺す予定だったのに最後まで死ななかったキャラクターもいますね(笑)。
――今回、1987年の作品から最近のものまで、本にまとめる作業で読み返して、何か自分の変化などは感じましたか。
貴志 根っこの考えは変わりませんが、文章はずいぶん変わったなと思います。特に「夜の記憶」の文章は、それこそ一文の長さから句読点の打ち方まで、今と全然違いますね。最初はもっと直そうとしたんですけれど、今の自分の書き方が正しいというわけではないですし、あまり直すと当時のフレッシュさみたいなものが失われてしまうかなと思い、ほどほどにしました。