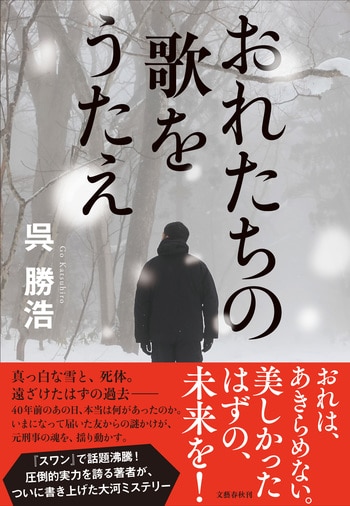――呉さんは青森育ちで大阪の大学に進学。長野には縁もゆかりもないですが、この話って、地理がすごく大事ですよね。
呉 そうですね。まず、菅平高原は出したいなと思い、そこから地形を調べていって。ちょうど菅平高原を挟んで真田町と長野市というふたつの町があり、そこから主要な舞台を真田町とすることに決めました。実は当初、第二章まではGoogleマップしか見ないで書き、その後、答え合わせがてら担当編集と取材に行ったら、「Googleマップ、嘘つけ!」と(笑)。やっぱり行かなきゃ分からないことが多いですね。山がちな地形なので、どこが坂になっているのかといった高低差は平面で見ても分からないし、川と道路のあいだに大きな茂みがあったり、画面だと分からなかったことがたくさんあった。数日滞在して、そこに昔何があったのかを住んでいる方に訊ねたりもしました。それまで自分はあんまり取材をするタイプの書き手ではなかったので新鮮だったし、モヤモヤとしか掴めていなかったものが固まっていく感覚があって、ここで腹が据わりましたね。すごくいい経験をさせてもらったと思います。上田、松本、長野市からもう一回上田へとぐるっと回って。長野県はいい場所だなって、好きになりましたよ。
――あさま山荘事件を最初に考えたということは、やはり学生運動を背景に入れたかったのでしょうか。
呉 それは確実にそうですね。この話をやろうと思った時にふたつイメージしていたものがあって。ひとつは横軸としての時代性。あの時代の雰囲気を書きたいというのがあった。それと、縦軸として、そこから連なっていく歴史。昭和51年、52年あたりというのは、括弧付きの「正義」が終わりかけていた時代だったのではないかと思うんです。60年・70年安保、全学連、全共闘という流れがムーブメントとしてあり、学生運動としては昭和43年から44年頃がピークなんですが、その残り香がギリギリあったのが昭和51年、52年くらいではないかと考えました。逆に言うと、そこが「正義」というものが死んだ年なのではないかと、僕のなかで位置付けて。
じゃあ、そこからどうなる? と考え、次の舞台を平成11年にしました。「正義」が経済に取ってかわられて、バブルの勃興と崩壊の影響が社会生活に出てきていた時期だからです。資本主義を全肯定していたら、経済も駄目になってしまった。僕はこの年を「やり直せたはずの最後の時期だった」ととらえています。
結論を言うと、日本はやり直さなかったわけです。失敗したけどそのまま行ってみるかと突き進み、現代に至る。じゃあ現代はどうなのかと訊かれたら、もう何もないよねというのが実感です。それが今回の作品を書く上での僕の基本的なものさしで、それを踏まえたうえで、それぞれの時代を自分なりに書いていきたいという最初のコンセプトに取り組みました。だから主人公たちも、時代ごとにそれぞれのテーマと向き合っていく。
今回出てくる、運動に関わった人たちは、ピュアでもあるし、ずるくもある。狂信的な部分を持ってもいる。それが人間だと思う。言い換えると、あり得たかもしれない自分のひとつの像でもあるんです。もし自分がその時代にいて、目の前で運動を見たら、何もしなかったとは考えにくい。全共闘にかかわらず、今回は登場人物の一人一人に対して、あり得たかもしれない自分の姿を重ねているところがあります。

ノスタルジーではなく、次の世代にどう繋げていけるかを描きたい
――綿密に構築されている印象ですが、呉さんってプロットを作らないんですよね。
呉 だから、今回もヤバかったです(笑)。でも、僕の場合、書かなきゃ小説の核が見つからないんですよね。書いて、駄目出しされて、また考えてというのを繰り返さないと出てこない。
今回は、主人公たちの先生にあたる人とその家族が出てきて、主人公たちのせいで何らかの事件が起きてしまう、みたいなところまでは考えていました。でも、それがどういう事件で誰が亡くなるのかは分からないままにとりあえず書き始めて、こねくり回しているうちにだんだん「あ、こういう話なんだな」と見つけていって。
――そうなんですか! あの真相は最初から決めていたのかと思いました。少年時代、主人公たちは、「キョージュ」と呼んで慕っている国語教師の影響を受けて、永井荷風など古典的文学作品に触れますよね。しかもそれが、後に暗号として活きてくる。
呉 永井荷風はパッと浮かんだとしか言いようがない。キョージュの人物像を考えていくうちに、おのずと出てきた。でも僕、荷風作品をそれまで一度も読んだことがなくて(苦笑)。とりあえず読み始めてみたら、『断腸亭日乗』で一気に荷風への興味がわきあがってきました。日記文学って歴史と記録という側面もありますよね。『断腸亭日乗』の下巻の最後のほうはもう、1日1行くらいの記述になって、何も書かない期間も長くなり、最期の断末魔のようなものも感じられる。そこに感情を喚起されるものがありました。最後の日も、40年書き続けてきたという歴史があったうえでの1行だから、詩のように見えるんです。それと、荷風はエッセイもいいんですよ。『雪の日』の最後のほうに、ヴェルレーヌの詩を荷風がオリジナルで訳したものが出てきます。ヴェルレーヌは当時の日本の文壇で人気の詩人で、調べてみると中原中也も彼の詩を訳しているし、太宰治の『ダス・ゲマイネ』にもヴェルレーヌが出てくる。『ダス・ゲマイネ』は仲間と同人誌を作ろうとする話なのですが、現実でも太宰は、中也と『青い花』という同人誌を作り、1号で休刊になってしまった。それが自分の中でぴったりきたんです。