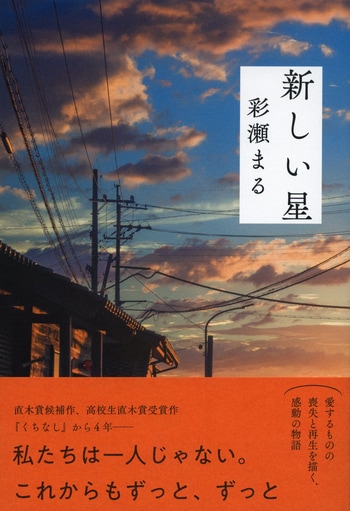みんなが「新しい星」に叩き落とされた時代に
――タイトルにもなっている「新しい星」は、青子が想起した言葉ですよね。人生が一変した後に、自分は今「ふいに叩き落とされた新しい星」に居るようだと感じる。
彩瀬 なんらかの強烈な体験をすると、それまでと同じ場所に居るのに違う世界で生きているような感じがすることって、そんなに珍しくないと思うんですよ。いろんな要因で想定外の事象に巻き込まれたり、思いもかけない環境に連れて行かれたりしても、生きるためにもがいていかねばならない。それはまるで新しい星に降り立って、サバイブする方法を探しているようだという感覚がありました。
――実際、コロナ禍で私たちも「新しい星」に叩き落とされましたよね。だから、この言葉を自分ごととして感じるひとは多いと思います。「新しい星」に叩き落とされても、そうやってひとは生きていくんだよと、強さと温かさと光を感じさせてくれる作品ですね。
彩瀬 後半を書いている時に思ったんですけれど、長い人生で「新しい星」に一回も叩き落とされないひとって、きっとなかなかいないですよね。いつも誰かしらが傷を負っていたり不調であったり、望むような姿でいられないでいることが普通というか。それについて、他人と幸福度を比べあったり、うまくいかないことを恥じたり引け目に感じたりする必要なんてないんですよね。誰もに傷があるし、傷を負っている場所も違うから、サポートしたり手を貸しあったりすることも特異なことじゃないと思います。ひとに迷惑をかけるなという前提で生きていくと、誰かに傷を見せることも、助けてもらうことも、ものすごくハードルが上がってしまう。サポートする方も絶対に誰かを助けなければということではなく、ふと手伝えるシーンで手伝えばいいし、わざわざ感謝されなくてもいいし、忘れられてもいい。そんなふうになったらいいですよね。

――彩瀬さんご自身は、コロナ禍でお仕事に変化はありましたか。
彩瀬 私は編集の方と対面で打ち合わせをしないと、ちょっと辛いんですよね。担当さんと話しながら次にどう物語を掘っていくか決めたいのに、オンラインだと相手の反応や思考が読みづらくて。特に新しい担当さんだと、そのひとがどんなものを読みたいのか、なかなかつかみきれない。
――組む編集者によって書く内容は変わりますか。
彩瀬 相当変わると思います。私は担当さんにあてがきみたいなことをしていて、そのひとが一番喜んでくれそうなものを書くんです。そうすれば、その担当さんの向こうに、同じ思考や好みを持った読者さんがいるから、誰かに届く物語になると思えるので。
――今年は『新しい星』のほかに、『草原のサーカス』と『川のほとりで羽化するぼくら』を刊行されましたよね。その時は、どんな感じだったのでしょう。
彩瀬 『草原のサーカス』の時は最初、担当さんと、歳をとることについて話していたんですよ。私は、歳を重ねるとだんだん自分の欲がなくなってミニマルになっていく、みたいなイメージを持っていたんです。そうしたら、その場に同席していた他の担当さんが、「えー、物を手放していくって寂しいよー」って。あ、歳をとることのイメージも、こんなに個人差があるんだな、それは個人の資質もあるけれど、生まれた世代や社会の状況によってだいぶ揺れ動くんだろうなと気付きました。バブル期に青春を謳歌した世代はお金に対する考え方も世界に対する考え方も前後の世代と違うだろうし。だとしたら私たちの自我ってなんだろうと思ったのがきっかけでした。それで、話の中で社会情勢を激変させ、視点人物たちの考え方も変わっていくなかで、変わらないものはあるのだろうかと模索しました。

――ああ、だから好景気に沸く社会を舞台に、その勢いに翻弄される姉妹が出てくるんですね。一方、『川のほとりで羽化するぼくら』は短篇集で、1話目は現実的な世界が舞台ですが、2話目で織姫と彦星的なファンタジー世界に引き込みますね。
彩瀬 第1話は「カドブンノベル」の「その境界を越えてゆけ」という特集号に載せたものなんです。「境界を越える」というテーマなので、価値観から出ていくというモチーフがよいなと考えて書きました。
そこから始まって、川を渡ったら別の国というイメージで、大きな境界や規範をまたいでいく話を書いていったんです。短篇の並びも、現実の話から始まって抽象度の高い話に移行して、最後にまた現実の話に戻るというのがアーチ状の橋みたいでいいのかなと。
――そして今回は、編集者から白米を所望されたわけですね。
彩瀬 はい、コメ農家をやりました(笑)。コロナ禍も大変だしこれからもいろいろなことがあるだろうけど、本を手に取ってくれた方々に、4人と一緒に家飲みしている感じで一息ついてもらえたら嬉しいです。