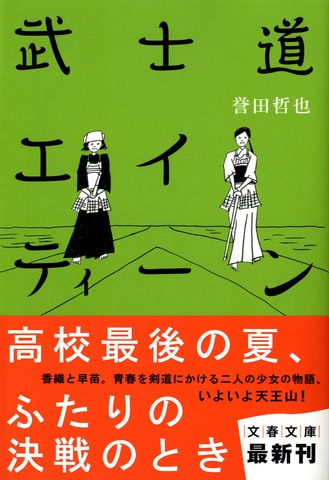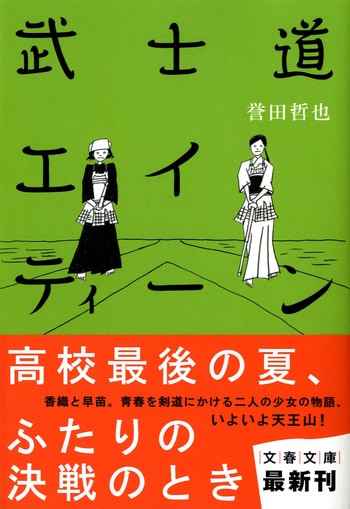──日舞から剣道に転身した柔の早苗(さなえ)が、剣道エリートの剛の香織(かおり)を市民大会で破った、二人の運命的な出会いから始まる青春エンターテインメント。『武士道シックスティーン』を第一弾とするシリーズも、今回いよいよ最終学年である十八歳、『武士道エイティーン』を迎えました。まず初めに、一冊目から二冊目の『武士道セブンティーン』へとシリーズ化したきっかけからお聞かせください。
誉田 『武士道シックスティーン』は、今まで自分が書いてきた小説の中で、人が死なない初めての作品だったんです。書いている最中は人が一人も死ななくて本当に面白いのかどうか不安で、とにかく物語を終わらせることに必死で、続編にはまったく頭がいきませんでした。刊行後に担当の方から続編のお話を頂いたのですが、主人公の一人を転校させてしまっていましたし、すぐに書けるかどうか自信がなかったので二年待ってくださいと申し上げたんです。
──二年を待たず、ちょうど一年後に続編の『武士道セブンティーン』が刊行されています。
誉田 一冊目の刊行後に、ある雑誌から「武士道について」というインタビューを受けまして、その中で、武士道とは、武道とは何かという話をしたんです。それがきっかけで「武士道」とタイトルに謳(うた)っていながら、武士道については何も書いていなかったと気付きまして、だったら『セブンティーン』ではそれをテーマにしようと。真正面から武士道や武道を早苗と香織の物語の中に詰め込んで書いてみようと思いました。
誉田 早苗と香織の「十八歳」を考えたときに、彼女たちの関係や武道観というのは前二作ですでにできあがっているので、これはもうテーマにはできないと思いました。じゃあ、なんなら成立するのか。十八歳の部活というのは夏で引退になってしまうので、実際の剣道部員の方もそうでしょうし、物語上も、本当にがむしゃらに高三の夏までを駆け抜けるしかない。ならば、そのあと彼女たちはどうするのか。クライマックスを過ぎ、部活を引退したあとの彼女たちの選択。これにテーマをしぼってみようと思いつきました。そう考えると脇のキャラクターによるスピンオフ的な短編も、四人のうち三人が香織と早苗より先に「十八歳」を経験している人生の先輩の物語と捉(とら)えることができる。彼らが十八歳のときにどういう選択をしたのか、それを「十八歳」と「選択」繋がりで香織と早苗の物語に絡めていったらいい一冊になるのではないかと、短編を書きながら固めていったんです。──今回刊行される『武士道エイティーン』は前二作とは少しかわり、早苗と香織の高三のインターハイにむけての流れの中に、早苗の姉である西荻緑子(にしおぎみどりこ)、香織が唯一尊敬する師匠、桐谷玄明(きりやげんめい)、早苗の転校先の福岡南高の剣道部顧問、吉野正治(よしのまさはる)、そして香織に心酔する東松(とうしょう)学園の後輩、田原美緒(たはらみお)の四人の短編が入るというスタイルですね。
──ほかにも登場人物がいる中で、この四人を選んだ理由はなんだったのでしょうか。
誉田 まず最初に、ちょっと毛色の違う緑子が決まったんですが、今までずっと香織と早苗を交互にやってきたので、四人出すとしたら、今回も不公平にならないように二対二で分けたかった。緑子、玄明、吉野先生、ここまではすんなり決まって、でも最後の一人を決めるのに悩みました。吉野先生というのは武道的スタンスの人なのに、早苗側の登場人物なんです。ところが、もう一人を選ぶときにどうも早苗側になりがちで、なかなか香織側からは出てこない。武道具屋のたつじいも考えたんですが、玄明の幼なじみであるため玄明の話と内容が近くなってしまう。ある意味、香織が強烈な個性の持ち主なので、香織の周りから誰かを出してくるのが難しかったんです。でも、香織も早苗もいなくなった東松の剣道部をみることができる美緒なら面白いんじゃないかと。掲載の順番も最後ですが、決まったのも美緒が最後でした。
──挟み込まれている順番どおりに、書き進められたんでしょうか。
誉田 はい。文春さんのウェブでこの四人の短編を連載し、その順番どおりに挟みこんでいます。緑子の短編はどこに挟んでもよかったのですが、玄明の話は先にもってきたほうがいいだろうと思いました。
──先にというのは、江戸から明治に剣道のプロ興行ともいえる撃剣興行が流行(はや)ったなど、今、剣道を実際にされている方でもあまり知らないのではないかと思われる、面白い剣道の歴史が玄明の章に描かれているからでしょうか。
誉田 前作までで、剣道の決まりごとというのは書いてきましたし、今回、またそういうことを書く場面自体もなかったんですね。早苗と香織の場面は、夏までは稽古、試合、稽古、試合の繰り返しなので、剣道の枠組みが最初に挟んであるほうが、インターハイへの助走になるのではないかと思いました。また、玄明の章で最初に考えていたのは、桐谷道場をめぐるお家騒動だったんですが、常識とはまったく違うであろう玄明なりの剣道観というのも書いておきたかったんです。
──『シックスティーン』で、礼をし、いったん構えた後は決まった回数も終わりの時間もなくなり、ただひたすら相手を斬る、蹴りを食らっても転ばされても「待て」がかからない、それが桐谷流の勝負稽古、とありますね。
誉田 彼の剣道観がどこで普通と乖離(かいり)したのかという分岐点を探ろうと思って、剣道の歴史や古流剣術のかたちを調べ始めたんです。そうしたら、剣道の歴史自体にとても興味深い流れがあったので、これを桐谷玄明の人生と家の歴史に絡めたらいいのではないかと資料を読むうちに思いました。
──真ん中にインターハイを挟んだあと、吉野の章となりますが、これは『セブンティーン』で描かれた剣道と暴力のテーマに繋がります。前作で、香織は、一撃で相手の戦闘能力のみを奪うという武士道の境地に立つことができましたが、吉野は暴力の側に立ってしまいます。香織自身も吉野の噂を聞いた時に、「他人とは思えない武勇伝の持ち主である」と思うなど、似た二人が逆の立場に立ち、対比として非常に面白いなと思いました。
誉田 『シックスティーン』や『セブンティーン』の作風からして、香織が助ける清水(しみず)君に絡んでいた不良というのは、ガチガチの武闘派でなくてもいいわけで、結果、香織が勝つことになりました。でも、恐怖から暴力に走ってしまうパターンは、現実では非常に多いと思うんですよ。誠実に生きていても、恐怖に負けてどこまでやっていいのかわからなくなる。香織は幸運にも、そのどこまでやるかという線引きをしてから助ける現場に臨めましたが、吉野先生はその線引きがないまま飛び込んでいってしまい、そうなると暴力を振るう結果にならざるを得ない。一定の割合でそんなふうに暴力って生まれてくるんじゃないのかなと思います。
──最後の美緒ですが、インターハイまでの稽古の流れの中で、上段の構えではない相手に、剣先(けんせん)を相手の左上に向け、刃を自分から見て左斜め下に向ける平正眼(ひらせいがん)の構え方をすることで、香織と対立します。この理由は美緒の章で明らかになりますが、この構えにした理由はなんでしょうか。
誉田 中段の相手に平正眼で構えるというのは、面が空いてしまうのであまり有効ではありません。ただ、普通に中段に構える中でも左目につけるという構え方はありますし、竹刀を握るときに二つの拳があれだけ離れているわけですから、竹刀を本当に真っ直ぐにするというのは、実はそんなに自然なかたちではなくて、開いたほうがむしろ楽だったりもするんです。これが美緒なりの平正眼になりました。ただ『武士道』シリーズを書く中で、最初から必殺技は作らないようにしようと思っていました。香織に関してもその時々で重点を置く技、試合の軸にしていく技は違いますが、それはごくありきたりの誰でも使っている技にしようと。『セブンティーン』からでてきた黒岩伶那(くろいわれな)に関しては、彼女自身が剣道そのものを改革したいと考える性格のため、レナの思想と現行のルールのぎりぎりのところで、今回はレナにだけオリジナルの技をあみ出させました。そうなると、実はレナと美緒は似ているのだと分かってくる。彼女たちの目的というか意識は全く逆なんですが、レナはオリジナルになるために色々な模索をし、美緒は常に何かのコピーをすることで技術を会得する。その上あっちこちに興味が向くため、剣道以外のスポーツからもコピーして持ち込んでしまう。結果的にレナに近いようなこともしてしまうんです。そういう中で、コピーを脱却するため平正眼に目をつけるというのは決して突飛なことではないんです。
──なぜ必殺技を作らないようにしようとされたのですか。
誉田 必殺技に限らず、一般に行われている剣道に近い物語にしたかったんです。例えば、主審がどちらの手に赤旗を持っているかとか一本の決まり方であったりとか。『シックスティーン』から『セブンティーン』のときに、鍔迫(つばぜ)り合(あ)いに関する高校の剣道ルールが変わったんですが、これ以降に読まれる方は現行ルールに慣れているわけですから、作品もそれに倣(なら)おう、とか。できるだけ近い世界観にしておきたいと。こんなのありえないよ、と剣道をやっている方に言われるよりは、わかるわかると読んでもらえる物語にしたかったんです。また、突飛なスーパースポーツヒーローみたいにしてしまうと、剣道をばかにしているようにも読めるので、できるだけ現実の剣道に即して書こうというのは最初からのスタンスですね。
──山場となる、インターハイの試合の組み立て方も見事ですね。早苗と香織が最後かと思いきや、そのあとで香織とレナが死闘を繰り広げるという……。
誉田 主役に相応(ふさわ)しい舞台とクライマックスをと悩みました。早苗との勝敗に関してはずいぶん前、香織が二度市民大会で負けたあたりから決まっていました。ただ勝ち負けよりも、どんな勝負であるのか、どんな試合になるのかというほうが重要でした。個人、団体とも決勝であたるということはトーナメントの山であったら右と左に分かれていなければならない。一緒になるパターンもあるんじゃないかと思ったので、だったら決勝戦であたることに拘(こだわ)らなくてもいいのではないかとだんだん思い始めました。むしろ強豪校の主力選手という対外的な意味合いで、高いところで戦う意義があるのは香織とレナのほうではないかと。早苗と香織に関しては、彼女たちの戦いはどこで実現しても、それこそインターハイでなくとも市民大会で実現してもいいので、だったら無理に決勝戦まで引っ張る必要もないだろうなと途中から思ったんです。
──この三冊を通して、香織の、自分の剣道から指導的立場にという精神的な成長ぶりが目覚しいですね。
誉田 香織が、自分より下のものに剣道を伝えたいというのは当初の設定通りなんです。『シックスティーン』の頃から、子供たちがやっているのをみるのが好き、時間があったら稽古をつけてあげたい、そういうことに元来喜びを得る子だったんですが、本人はそのことに気づいていないし、さほど大切にも思っていません。しかし、あの一番尖(とが)っていたときの香織が唯一向ける優しさというのを置いておきたかったんです。先輩には牙をむきますし、同輩は薙(な)ぎ倒していこうとしますが、後輩は基本的に育てるものだと思っています。剣道が好きなので、自分より後に始めた人にはやめないで欲しいと思い、それに対しては協力するという姿勢なんです。学年があがるにつれて、その姿勢がわかりやすく外に表れてきたんだと思います。ただ過去においても、その指導が決して甘いものであったとは思えませんが。
──そう考えると、一方の早苗は基本的に剣道が好きだという考えから変わっていないですね。
誉田 早苗は今は剣道が好きですが、基本的には、何かを好きでいるという気持ちが変わらない子なんです。剣道をやめるときも剣道を嫌いになるからではなく、剣道が好きだという気持ちのまま、次のものに移っていけるんです。何かから別のものに移るとき、過去の経験を次に活かせる子。ジャンルには拘らない、逆に言えば発展させていける子なんです。読者の方にも一つのジャンルを続けていけなくなることイコール挫折で、イコール暗いことだと思ってほしくないんですね。一つのことがダメになるというのはよくあることで、自分が何を好きだったのか、どうして好きだったのかを見つめ直すと、じゃあこういうことでも満足感を得られるんじゃないか、と発想って変わっていくと思います。それを早苗を通して書いておきたかったんです。これは、片腕でも剣道を続けてやろうとする香織には絶対無理なことなので。