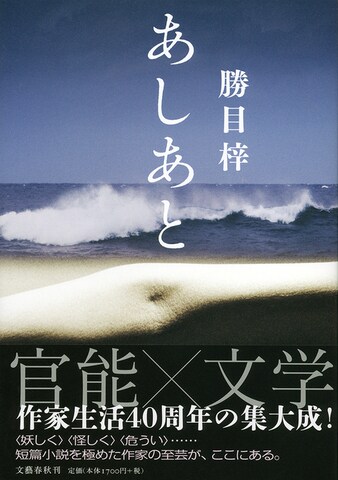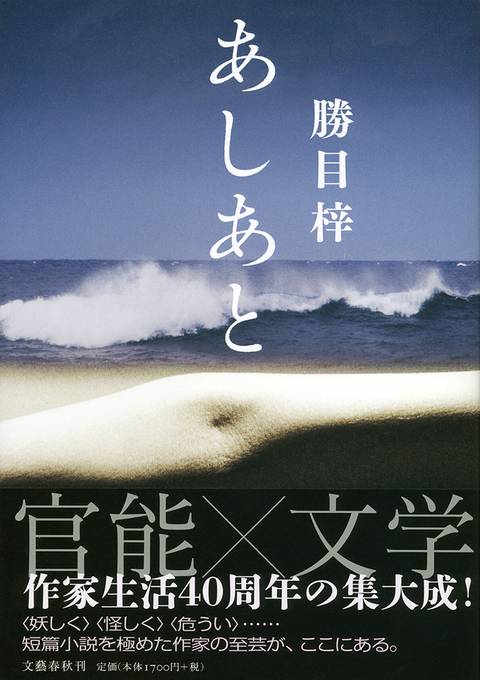今年でデビュー40年を迎えた勝目さん。バイオレンスロマンの第一人者というイメージを持つ長年の読者もいるかもしれないが、著作が300冊を超えた10年ほど前から、バイオレンスはほとんど描いていない。
「年齢とともに暴力シーンの想像力が働かなくなったんです。それでもセックスは頭に浮かぶので、ずっと書いてきたのですが、今回は今までと違った、不思議な話に手を伸ばしてみたいという強い動機がありました」
こうして生まれた320作目は、夢とも幻ともつかないものに遭遇したり、意識下に沈んでいた記憶でつながってしまう人々を描いた短篇集だ。
認知症が進みつつも出征した夫との記憶は鮮明な92歳の老女(「ひとつだけ」)、1通の手紙から高校時代のひと夏の経験が蘇る中年男(「橋」)、漁で亡くなった夫を想いつつも、男のぬくもりを欲する女(「あしあと」)など、10篇の主人公たちは皆、自他のセックスを媒介に、現実と非現実、現在と過去の間を行き来することになる。
「一定の年代以上の人にとっては、人生を振り返ってみると、ある性的な体験のせいで、人生のその1カ所だけ歪んで見えたり、乱気流を起こしていた、ということがあるのではないかという思いがあったんです」
セックスがキーワードとはいえ、いずれも直接的なシーンは抑えられ、中にはセックス自体が描写されない作品すらある。それにも関わらず、巧みな筆致で全篇に官能の気配が漂っている。そして、勝目さんの言う「人生」とは、自身だけのものではない。
「僕たちの年代になると、周りの中での自分の人生、というように、自分と関わった人のことをあわせて振り返ることもある気がします。人同士の関わりが濃密で、いろんな人と生身でぶつかってきた人生ですから。場の空気を読んで本音を言わない今の若い人たちが思う人生とは違うでしょうね」
その言葉通り、10篇とも主人公のみならず、彼らの周囲の人々の人生の哀しさや切なさまでもが迫ってくる。「ぎゅっと人生が凝縮されたようなものがあって、何らかの余韻が残るものが良い短篇」という勝目さんだが、今作はまさに珠玉の短篇集といえるだろう。
かつては月100枚ペースで執筆していた時期もあったが、今回は小誌で約3年をかけて連載した。
「量産していたころは締切に追われた肉体労働のようなもので、小説を書く楽しみとか喜びというものがなかったんですが、今はそれがある。ゆっくり時間をかけて、考えながら書いているこの楽しさ。作家生活のなかで今が一番幸せですよ」