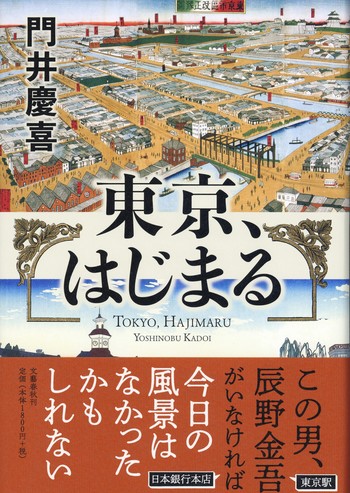現代人が一生抱くことのない国家観とは?
――辰野金吾は1854年生まれ。明治維新の前に生まれているんですね。建築家になった時は日本が近代国家になったばかりで、金吾は「俺」イコール「国家」くらいに思っていますよね。
門井 そうなんです。21世紀を生きる我々にとっては、個人と社会だったら社会のほうが大きいイメージがありますよね。でもどうも辰野金吾は、自分と国家を同じくらいの大きさに考えていたんじゃないかというところがある。作家としては、ここまでイメージできればしめたものでした。
金吾は本当に自分のことを肥大化させていたというか、一種の誇大妄想を持っていたのかもしれませんが、でも待てよと。このひとが生きていたのは明治時代です。近代が始まってたかだか十年ですから、むしろ国家のほうが小さいんじゃないかと。だから金吾は国家そのものを子ども扱いしているんじゃないか、という発想が出てきます。
――息子の隆が、〈金吾にとっては国家のほうが年下なので、最初のうちは赤んぼうにしか見えなかったろう〉と思う場面で、なるほどなと思いました。ただ名を残したいという人ではなくて、また違う国家観を持っていたのだと気づきました。
門井 息子のあの言葉は、僕のオリジナルで入れさせてもらったものです。あれは我々が一生抱くことのない国家観、国家の見方ですよね。それを、いまの読者にとって腑に落ちるように紙の上に定着させるのは、歴史ものを書く醍醐味のひとつです。

――本作は父と息子の話にもなっていますね。それは金吾の人生を小説化する時に息子の存在が特別に思えたからなのか、それとも門井さんが父と息子という関係に惹かれるものがあるからでしょうか。
門井 僕自身、息子が3人いる父親だということもあるのかもしれません。正直『銀河鉄道の父』を書いた時に「もう父と子はいいや。自分に書けることは全部書いたわ」と思ったんですけれども、こういうふうに新たな親子が出てくると興味は湧きますね。
そもそも辰野金吾と辰野隆は、物理的な意味での共通の人生体験がないと思うんです。生まれ育ちからして違いすぎますから。僕らにとっての、生まれた時からスマホがあるかどうか、なんて目じゃないぐらい大きな違いが。さきほどの、金吾にとって国家というものが赤んぼうに見えるという点においても、隆の場合は生まれた時からもう国家があって、その存在を最初から疑っていない。見えてる世界、住んでる世界そのものが違うんです。それは書く甲斐がありました。
――日銀や東京駅の建築にまつわるエピソードなどももちろん読ませますが、他にも「へえ」と思うことがたくさんあって。高橋是清ってこんな人だったのか、とか、金吾と同期の建築家、曽禰達蔵が、金吾とは正反対で、自己承認欲求みたいなものを見せないところとか。
門井 高橋是清はめちゃくちゃですよね。この人のほうが小説になるわ、みたいな(笑)。
曽禰はああいう人だったようです。同時代の証言を読んでも、性格的に淡白というか、あまり物事にこだわらないと書いてある。でも日本の近代建築のナンバー2ですからね。金吾の隣にいたから淡白に見えただけなのではないか、という気もしますね(笑)。戦前の設計事務所で一番大きかったのは、曽禰さんが後輩の中条精一郎と組んで作った曽禰中条建築事務所なんです。ここが作った講談社の建物はいまも現役です。本当はすごい人なので、金吾さえいなかったら曽禰さんがオラオラな感じになっていたかもしれません(笑)。
――それぞれのプロジェクトへの取り組みやその苦労でも読ませますが、その過程や、日銀の地下に意外な仕掛けがあることや、東京駅の周辺が昔は海だったといった蘊蓄などを、説明的にならずに楽しく物語として読ませますよね。それはすごくテクニックの要ることだと思うんです。
門井 ありがとうございます。そうなんです。日銀や東京駅を建てるところは、書き進めるのに非常に時間がかかったところでした。わかりやすく説明しなきゃならない、でもその文章は説明的でなく小説的でなきゃいけない。さらに言うなら目の前でどんどん建物が建っていると読者に思わせることができなきゃいけない。ここのところ、ちょっと話が逸れてもよいでしょうか。
――もちろんです!

門井 これを書いて思ったのは、日本文学史なんですよね。日本の近代散文というのは、物事を、目の前であったことをその通りに書くのに適していないと感じたんです。人間の心理とか、言ったことを書くことには非常に適している。端的に言うと、自分語りに適している。なぜかというと、日本の散文、特に「何々だ」「何々である」という近代口語体というのは、小説家が作ったからです。でも、客観的に目の前で起こっている事件は書きづらい。今でもニュースでアナウンサーが読む原稿などは、文字で読んだら分かりづらいじゃないですか。
ですから、大げさにいいますと、今回は、日本語における近代散文の質というものと正面からぶつかる苦労がありました。
――その苦労は、どうクリアしたんですか。
門井 時間を大事にするということだと思います。ひとつは、基礎があって柱を建てて屋根を建てるという、そういう物理的な順番です。もうひとつは、読者が読んでいる時の認識の順番ですね。文章というのは、映像みたいに複数の情報がいっぺんにぱっと入ってくるわけではなく、必ず時間順に入ってくる。逆に言えば、時間とは絶対に縁の切れないメディア、それが文章なんです。ですので、認識の順番を間違えないようにすることに非常に注意を払いました。たぶん、具体的なテキストがあったほうが説明しやすいと思うのですけれど。
――では、本作の中からどこかご指定いただけましたら。
門井 (本を開きながら)たとえば鹿鳴館を建てている足場から、金吾がコンドル先生と東京の街を俯瞰する場面。21ページあたりから。彼らが見る景色について、〈手前から奥へ、二本の川がながれている〉と先に言っておいて、その後に、その川の間にある陸のことを、大雑把に外桜田、永田町、麹町というふうに書きました。もし、ここに外桜田があるよ、と言ってからそれが二本の川に挟まれていると説明しますと、読者の認識の順番としては、輪郭を与えられる前に中味が与えられちゃうわけです。輪郭に何か特別な意味があるから後で言う、というなら別ですけれども、そういう意味がない場合は、通常は輪郭を与えてから中味を書いたほうが分かりやすい。家を建ててから家具を入れる、みたいな感じかな。