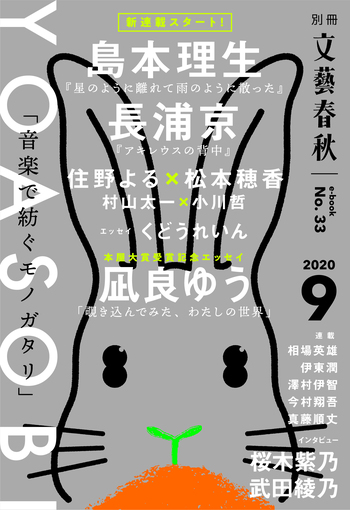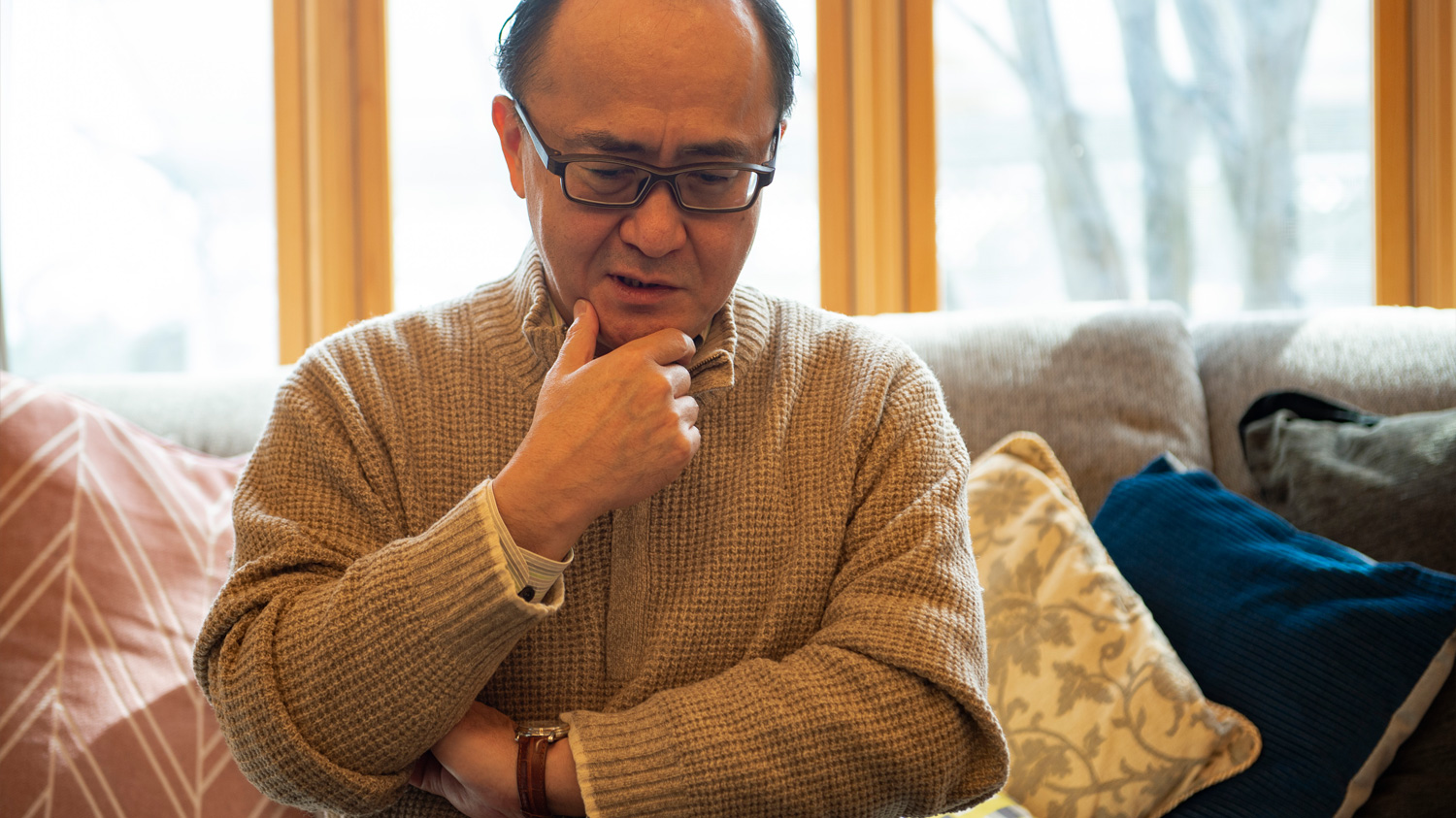毒にならない親なんていないと思うの
――第5章の視点が年配の登美子さんという女性で、これまた意外な角度から描かれる。
桜木 登美子さん、私は大好きです。最後の視点人物はまた智代に近い人物にしようかとも考えたんですが、待てよ、これは『ラブレス』の百合江しかいないだろうと思って。だから百合江と登美子はどこか似ているところがあるんです。こういう人物が好きなだけに、書く時には腰に力が入りますね。
――ああ、『ラブレス』の主人公、百合江は、傍から見れば理不尽な目にあって暴力も受けて貧困も味わっているのに、自分のことを幸せだと言える女性なんですよね。確かに百合江さんと登美子さん、重なります。
桜木 よかった。書いている時は私も精神的に健康でしたね。
私、こういう人になりたいんですよ。しゃんしゃん身体が動いて、頭もそこそこ回って、子どもに面倒かけないところとか。子どもたちが自分を捨てても、親を捨てるくらい自分を肯定できる子どもを育てられたのだから御の字だ、と思うような人。
私も子どもたちに、言葉は悪いけど「ほどのよいところで親を捨てなさいよ」って言ってます。擦り切れてつらくなるまで親と一緒にいることはないと思っていて。もともと子どもには、和を大事にしようとかみんなと仲良くしろといったことはあまり言わなかったですね。自分ができなかったから。
今回も、全体的に人の弱さを書いていると思うんですけれど、書き終えてから、他人の視点を持ってきたことで誰も悪者にせずにすんだと気づきました。2章で陽紅さん、4章で紀和さん、5章で登美子さんを書いて、ようやく丸くなったというか。この老夫婦を書くのに必要な視点でした。

――タイトルの「家族じまい」は最初から頭にあったのですか。
桜木 一等先にタイトルが決まりました。家族って捨てる時は捨て合えるんだという意味合いもあるし、自分の中の家族へのわだかまりみたいなものを仕舞う、という思いもあります。今、毒親とか鬼親とか言われているけれど、正直言うと、毒にならない親なんていないと思うの。親の言うこと聞いててよかったためしなんてないでしょう? 少なくとも私のまわりではなかった。今55歳の私が辿り着いたのは、親を否定しても始まらないということ。自分を肯定したいんだったら、否定したい親から離れるということ。親のことを「毒」とか「鬼」とか言うのではなく、いったん他人の棚に入れてみる。表面的には変わらず親子だけれど、自分の中では隣のおじさんといった感覚で、責任と善意でお世話する気持ちで接する。言葉にすると身も蓋もないけれど、言語化せずにそうして心のバランスを取っている人は多いのではないかと思います。
――ああ、そう言ってもらえると楽になる人は多いのでは。
桜木 そうだとすれば、これを書いた意味があると思います。
私の場合は親を一回他人の棚に入れて、家族だということに甘えるのを止めたんですよね。自分の親にできないことは夫の親にもしないし、夫の親にできないことは自分の親にもしない。それは嫁に出る時にはっきり言ったし、こっそり小説を書きはじめた30歳の時もそんな感じだったんですね。あの時代、親とつきあわない、つきあってる時間がないことを分かってもらうための方法のひとつが、納得させるような仕事を持つことでした。私の場合は小説を書き始めたわけだけど、だからこそ、本を一冊でも出さないと落とし前がつけられなかった(笑)。
――それで新人賞を受賞して本を出せたのだから、よかった。
桜木 直木賞をいただいた時、授賞式に親が4人とも来てくれたの。遅ればせながら、あの時に親孝行をひとつできたと思えました。親には、小説を書く嫁のことも、小説を書く娘のことも決してよく思われていなかったし、たぶん多少は憎まれていたんだと思うけれど、仕方なくでも許してもらった気がします。
――ご両親、4人ともご健在なんですね。
桜木 そうなんです。今後1人欠け2人欠けしていくし、そのたびに私は新しい感情を手に入れるわけだけど、今のところの私の答えがこの『家族じまい』かな、と思います。つまり今じゃなかったら書けなかった一冊といえますね。そう思うと、「そろそろ自分と向き合いましょうよ」って水を向けてくれた編集者には感謝してます。ずっと私を近くで見てくれていたことがよく分かる。
(続き「10年かけて何者かになりたいと思った」を読む)