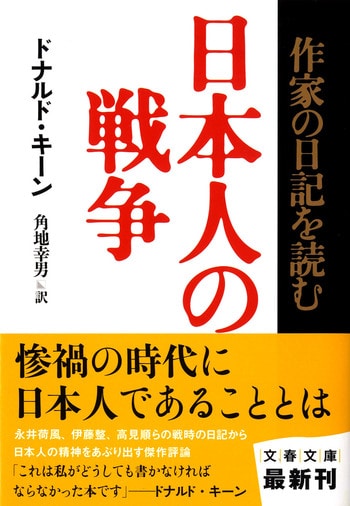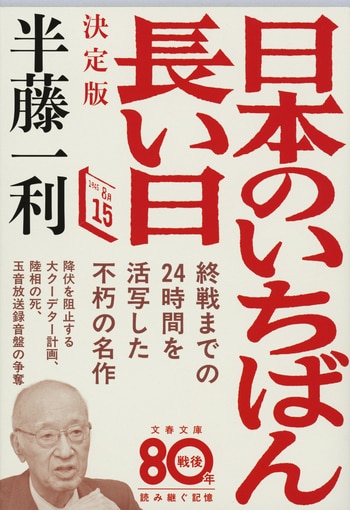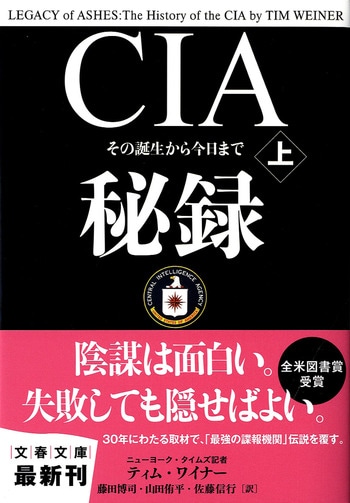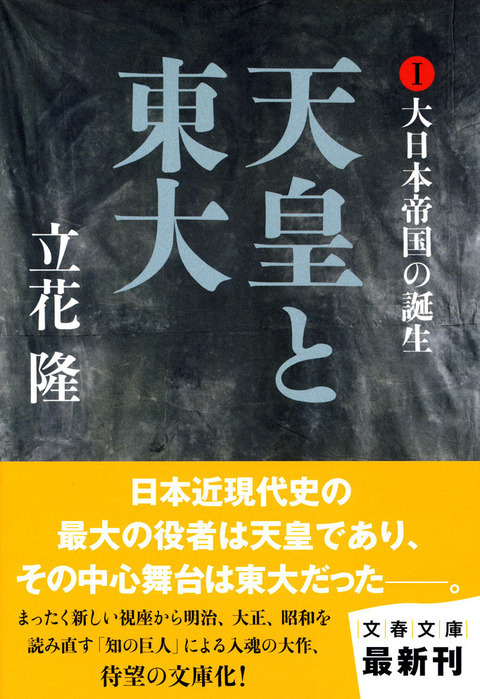
昨年、重くて読みにくいと造本が不評だった拙著『天皇と東大――大日本帝国の生と死(上下)』が、文春文庫に入り、4冊本として刊行された。それに合わせて慶應大学の丸の内シティキャンパスで、「『天皇と東大』を軸に日本の近現代史を読み解く」という講座を開講して、3ヶ月かけて4冊本を読みあげた。といって、本に書いてあることを祖述するような授業を行ったということではない。逆に、本に書いてあることは、事前に各自読んでおくことを当然の前提として、授業ではもっと大きな視点から時代背景をながめ直したり、全くちがう角度から同じ時代をながめたらどう見えるかといったことを史料中心で語ることにつとめた。つい最近その授業を終えたところだが、ふり返ってみると、文春文庫を相当に利用することになった。

授業の眼目は、あの戦争の時代をもう一度ながめ直し、考え直すことにあったが、そういう視点からの近現代史ものは、雑誌「文藝春秋」が最も得意とするジャンルだから、それも当然といえる。『天皇と東大』は、「大日本帝国」が生まれてから死ぬまでを描いた大河ドラマみたいな本だから、その最終幕は、昭和天皇の現人神時代の終りとそっくり重なる。だから寺崎英成、マリコ・テラサキ・ミラー編著『昭和天皇独白録』は最良の資料となる。天皇が長時間にわたって肉声であの時代と自分とのかかわりを語ったものは他にない。開戦時と終戦時の天皇の心境と立憲君主制下の天皇の行動の限界に対する認識など、当事者ならではの証言の重みがある。授業ではほんとうに天皇はあれしかできなかったのか、など多くの(学生側からの)議論がわいたが、それもあの独白録の心情告白があればこそである。

あの戦争がらみで、資料として用いて、学生たちに少なからぬショックを与えたものに、ドナルド・キーン『日本人の戦争』がある。これは永井荷風、伊藤整、高見順、山田風太郎など、多くの有名作家たちの日記から戦争中に彼らが何を考え、何を感じていたかを抜き出した本だ。これを読むと、驚くほど多くの日本人が、心情的にあの戦争に強くコミットしていたことがわかる。詩人・彫刻家の高村光太郎はこう書いた。「記憶せよ、十二月八日。/この日世界の歴史あらたまる。アングロ・サクソンの主権、/この日東亜の陸と海とに否定さる」。英米文学者の伊藤整は12月8日、戦争の開始とともに新聞の見出しを見て、「全身が硬直し、眼が躍ってよく読めない」という状態におちいった。「大和民族が、地球の上では、もっともすぐれた民族であることを、自ら心底から確信するためには、いつか戦わなければならない戦いであった」と書いた。左翼文芸評論家の青野季吉ですら、「英米との開戦を知って、いよいよ自分にとって来るべきものが来た、天皇陛下の臣下として一死報国の時が来たのだ、と書いた」。戦局がさらに進んで、東京が大空襲を受けた昭和19年3月10日、山田風太郎はこう書いた。「昨晩目黒で、この下町の炎の上を悠々と旋回しては、雨のように焼夷弾を撒いているB29の姿を自分は見ていた。おそらくきゃつらは、この下界に住んでいる者を人間仲間とは認めない、小さな黄色い猿の群とでも考えているのであろう。勿論、戦争である。敵の無差別爆撃を、天人ともに許さざるとか何とか、野暮な恨みはのべはしない。(略)さらばわれわれもまたアメリカ人を幾十万人殺戮しようと、もとより当然以上である。いや、殺さねばならない。一人でも多く。(略)きゃつらを一人でも多く殺す研究をしよう」

そして迎えた8月15日。徳川夢声は日記にこう書いた。「コーン……正午である。/―コレヨリ畏クモ天皇陛下ノ御放送デアリマス、謹シンデ拝シマスルヨウ(略)玉音が聴え始めた。/その第御一声を耳にした時の、肉体的感動。全身の細胞ことごとく震えた。/(略)これで好かったのである。日本民族は近世において、勝つことしか知らなかった。(略)勝つこともある。敗けることもある。両方を知らない民族はまだ青い青い。やっと一人前になったと考えよう」
この日早朝、宮城では天皇の終戦の詔勅発表を阻止しようとして、一部若手将校が決起してクーデタまがいの事件を起していた。その顛末を書いた半藤一利『日本のいちばん長い日』は、日本のノンフィクションの傑作である。あの戦争の終わり方を知るために日本人全員が一度は読んでおくべき本といえるだろう。
戦後の日本史のポイントをおさえるために読むべき本もまた多い。
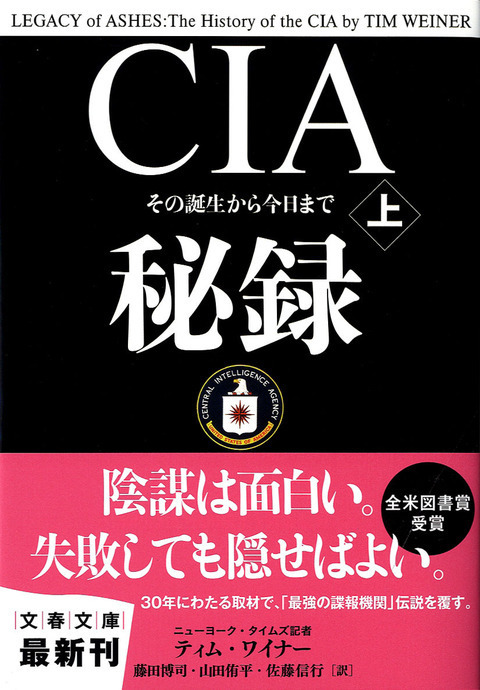
ティム・ワイナー『CIA秘録』の第12章「『別のやり方でやった』自民党への秘密献金」は日本人全員ぜひとも読むべきだ。児玉誉士夫がCIAの秘密エージェントであったことはロッキード事件で暴露されたが、実は岸信介もそうであったことが本書で暴露されている。A級戦犯容疑者から「釈放後岸は、CIAの援助とともに、支配政党のトップに座り、日本の首相の座までのぼりつめるのである」。「七年間の辛抱強い計画が、岸を戦犯容疑者から首相へと変身させた」。本書には、CIAと岸の間をつないだミドルマンのハリー・カーン、ビル・ハッチンスン、クライド・マカボイなど実名で記されている。「岸は当初は舞台裏で仕事をし、先輩の政治家に首相の地位を譲っていたが、やがて自分の出番がめぐってきた」。その結果、「CIAが外国の政治指導者との間で培った、最も強力な関係」が生まれたのである。「岸はCIAから内々で一連の支払いを受けるより、永続的な財源による支援を希望」し、その願いは、ジョン・フォスター・ダレスによってかなえられる。その資金は少くとも15年間にわたって、4人の大統領の下で流れつづけ、それが廃止されるのは、1964年以後だったというのだ。岸以後も70年代までCIAの買収工作はつづいたという。
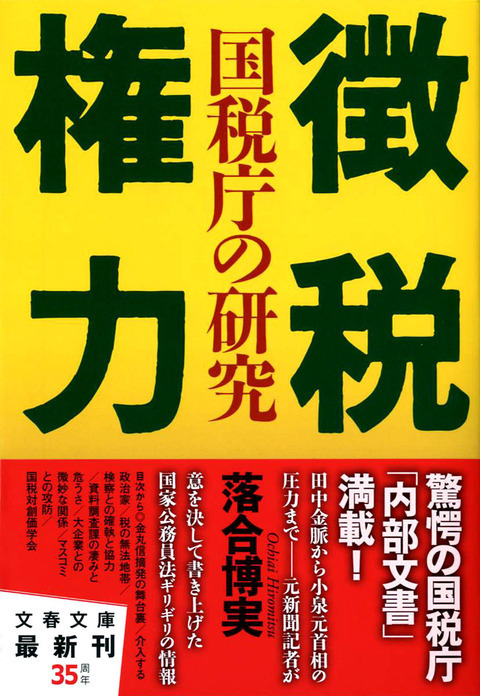
最後に日本人の著者による政治とカネの裏をあばいた作品を1つだけあげれば、落合博実『徴税権力』だろう。92年に東京佐川急便事件で、自民党の実力者金丸信の5億円のヤミ献金事件があばかれたのに、検察がわずか20万円の罰金で事件を処理したために国民の怒りを買い、検察庁舎に黄色いペンキがぶちまけられ、「検察の威信回復に10年以上かかる」といわれながら、翌93年、金丸が所得税法違反で逮捕されるにいたるまでの裏の裏が実に見事にあばかれている。結局あれをきっかけに自民党の崩壊がはじまり、ついには自民党が政権を失うにいたったのだ。