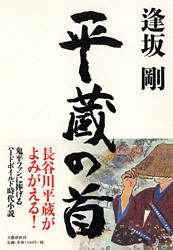――池波正太郎さんが亡くなって22年経ったいまも『鬼平犯科帳』は多くの支持を集めています。「鬼平」と逢坂さんの「出会い」を教えてください。
昭和43年に『オール讀物』で連載中だった「鬼平」に父(挿絵家・中一弥氏)が挿絵を描きはじめてからですね、ちゃんと読むようになったのは。それまではハードボイルドやサスペンス、ミステリー一辺倒でした。
改行が多くて文体がリズミカル、とにかく読みやすい時代小説でしたね。細かい心理描写や余計な説明がない分、読者の想像力を掻き立てるし、短い文章の行間に色々な情報が詰まっている。池波さんは本当にすごい作家です。
――逢坂さんご自身は昭和55年に作家デビュー。スペインもの、警察もの、西部劇小説などを次々と発表。初めての時代小説「重蔵始末」シリーズ第1作を書かれたのが平成12年です。
近藤重蔵という人物に惚れ込んで資料を集めていたんですが、書く自信がなくて。時代考証をきちんと勉強してからと考えていたら、あるとき藤沢周平さんに「逢坂さん、そんなことを言っていたら、一生時代小説は書けませんよ。勉強しながら書くんです」と言われたんです。目から鱗が落ちました。
父が元気なうちに自分の作品に挿絵を描いてもらいたい、という気持ちも強くて、時代小説を書く踏ん切りがつきました。父に現代物を描いてもらうよりは現実的でしょう(笑)。ついこの間101歳になりましたが、今回の「平蔵」シリーズももちろん頼みました。
――重蔵と同時代に生きていた長谷川平蔵も、名前だけ作中に登場します。
このときはまだ平蔵を出して実際に動かす、ということに躊躇していたんでね。池波さんに、礼を失するというか、そんな気持ちが強かった。
今から2年前に池波さん没後20年記念企画で『オール讀物』から平蔵を書いてほしい、と頼まれたときも、最初は断りました。それでもどうしても、と当時の編集長に言われて、まず私がお願いしたのが「池波さんの奥様の了解を得てほしい」ということ。何と言っても池波さんが作り上げた「鬼平」という人気キャラクターを、お借りするわけですからね。
――そうして書かれたのが第1作「平蔵の顔」。平蔵は深編笠をかぶって顔を一切晒さず、登場場面も少ないです。
最初のころはまだ自分なりの「平蔵」が固まっていなかったせいか、あまり出てこない。ただ他の作品でもそうなんですが、私は主人公の心理描写は一切せず、周りの人々の印象でキャラクターを作り上げていくことが多い。この作品でもそれを踏襲してます。
とにかく「別の平蔵を作りたい」という気持ちが強かった。だから「鬼平」を期待して読む人は肩透かしを食らうかもしれない。ああ、こういう平蔵もあるんだな、と読んでもらえるといいんですけどね。
もっとも長谷川平蔵の統率力、判断力の高さ、厳しいだけでなく人情味もある、といった人物としての優れた資質については、文句なしに池波さんに倣っています。一方で平蔵には悪評もあったけれど、そういう清濁の部分を全部含めてね。
松平定信の側近が書いた『よしの冊子』という報告書に、断片的ではあるけれど長谷川平蔵の人柄を彷彿とさせるエピソードが、たくさん出てくるんです。池波さんが「鬼平」執筆時には読んでいらっしゃらないはずなんですが、そこに出てくる平蔵はまさに「鬼平」そのもの。これは池波さんの作家としての直感ですよね。
――逢坂さんがいかに苦心して、また気を遣われて、自分なりの「平蔵」を作り上げていったか、よく分かります。
「密偵(いぬ)」「おつとめ」「いそぎばたらき」といった、池波さんが作られた優れた造語を使えれば楽だったろうけど、それも失礼なので、ごく一般に使われている言葉を使ったりね。平蔵の役宅を本来の場所に戻したり。ある程度自分なりの制約を作り、真似するのではなく、敢えて似せまい、と努めました。
それは池波さんに対するリスペクトでもあり、作家としての自分自身の覚悟、自負心でもありますね。
――6篇の中篇が進むにつれ、平蔵の出番が少しずつ増えます。個性的な悪役が登場し、ミステリー色が強まってどんでん返しも用意されたり。逢坂さんの手腕が充分に発揮されています。
『七人の侍』みたいにだんだん仲間が増えていってね。読者は「鬼平」を期待するのではなく、私がどういう「平蔵」を書くか、に期待しているわけでしょう。人と比べても仕方ない、自分が読んで1番面白いものにしないとね。
この『平蔵の首』は近年書いてきたものの中では、最も苦労しました。批判も含めて、どういう評価を得るのか、怖くもあり楽しみでもありますね。