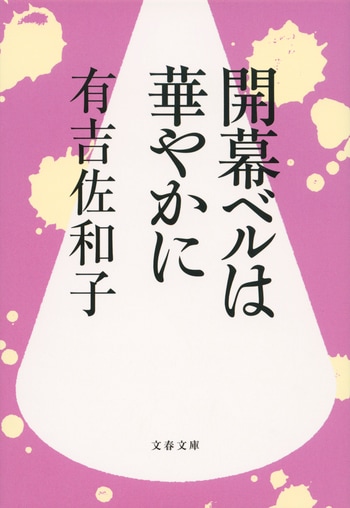有吉佐和子は、芝居の国の住人でもあった。
昭和二十六年、東京女子大学短期大学部に在学中、有吉は歌舞伎の専門誌『演劇界』の懸賞俳優論に三回連続して応募している。「尾上松緑論」「中村勘三郎論」「市川海老蔵論」が編集部から与えられた題目だが、いずれも二等にとどまったために原稿そのものは誌面には掲載されず、読むことができないのが残念でならない。「市川海老蔵論」の選評に有吉の名前があり、「文字を見るだけでもすぐ分かるくらいに馴染みになった」とある。この懸賞俳優論は、この回で打ち切られてしまうが、当時、『演劇界』編集長であった利倉幸一に有吉は見いだされ、「社外ライター」として、インタビュー記事を立て続けに発表するようになる。はじめて活字になったのは、昭和二十七年八月号の「渡邊美代子さんに歌舞伎の話を訊く」である。来日して日本女子大で教鞭をとっていた渡邊は、ロサンゼルスで女歌舞伎を演じた経験を持つ素人役者だった。この記事のみ署名はA記者となっているが、次回からは有吉佐和子とある。
演劇と海外に縁が深かった有吉の生涯を振り返ると興味深い。
本書『開幕ベルは華やかに』は、昭和五十七年三月に上梓されている。年譜をたどると一月は小幡欣治脚本・演出 臼杵吉春演出の『芝桜』が名古屋の中日劇場で、二月には有吉演出 大藪郁子脚本の『乱舞』が帝国劇場で、文学座の戌井市郎演出の『ふるあめりかに袖はぬらさじ』が、サンシャイン劇場で、三月には有吉演出 大藪脚本の『香華』が大阪の朝日座で上演されている。この年は、六月に『和宮様御留』十二月に『助左衛門四代記・第一部』が舞台にのり、一年に六本の有吉作品が劇場にかかっている。二本の演出を含む精力的な活躍は、専業の演劇人でもなかなかあるものではない。
明るい赤とピンクの装丁に飾られた本書が書店に並んだとき、私はわくわくして直ぐに求めた。演劇の裏側もよく知り尽くした有吉が、満を持して書いたバックステージ物として、この小説を読んだのを覚えている。
登場人物のモデルも容易に想像がついた。八重垣光子は、新派の名優、初代水谷八重子である。八重子は歌舞伎俳優の十四代目守田勘彌と結婚していたことがある。また、歌舞伎俳優中村勘十郎は、昨年急逝した十八代目中村勘三郎の父、十七代目勘三郞である。有吉の代表作『華岡青洲の妻』は、何度もキャストを変えて繰り返し上演されているが、昭和四十八年の公演では、青洲役を勘三郎が、妻・加恵役を初代八重子が勤め、ふたりは同じ舞台にのっている。
商業演劇の世界で、座頭級の役者は、演技に専念するばかりではない。特に歌舞伎では、自分以外の役に誰を起用するか、配役にも発言権があり、演出の方向性さえも決めることが多い。いわば舞台の全権を掌握する存在である。モデルとなったふたりは、その自由奔放な振るまいでつとに知られていた。人生のすべてを舞台に賭けたふたりが、同じ舞台に乗れば、平穏にすべてがすすむとは考えにくい。
小野寺と渡は、別れた夫婦だが、渡のワンルームに深夜、小野寺から電話が掛かってくる。東宝重役であった菊田一夫とおぼしき長老の劇作家加藤梅三が降板した。第二次世界大戦のさなか、満州で諜報活動を行った男装の麗人で、清朝王族の川島芳子を描いた新作の脚本を引き受けた。ついては演出をお願いしたいというのだった。
この電話を発端に、光子、勘十郎主演のこの作品が実際に舞台に乗って上演されるまでの曲折が描かれるが、本書は、バックステージ物であると同時に、推理小説の体裁を取る。現実の舞台が進行しつつあるなか、殺人の予告と脅迫、身代金、そして事件が起こる。有吉のストーリーテラーとしての卓抜な技倆を味わうことができる。
私は、はじめモデル探しを愉しんだ。次に役者や劇作家や演出家のリアルで、しかもこうあってほしいという言動を味わった。ふたりの役者の声や話し方は耳に残っているから、小説を読みつつ、肉声が聞こえてくるようだった。さらに待ったがきかない舞台を、俳優の力で延び縮みさせてしまうサスペンスを小気味よく思った。さまざまな愉しみ方のできる小説だが、私がもっとも心を動かされたのは、対立していたはずの光子を勘十郎が気遣うくだりだ。
舞台の上演中に事件が起こる。幕間に支度部屋に戻った勘十郎を刑事が訪ねてくる。脅迫があり、身代金が要求されていると知る。質問が終わった後、部屋を出ようとする刑事を勘十郎は呼び止める。
「本当は僕じゃなくて、八重垣光子なんでしょ、犯人が殺すと言ってるのは」
「私にはよく分りません」
「僕は分ってるよ。演出家はうまく騙したつもりだろうが、狙われてるのはお嬢の方よ。文化勲章なら、もう殺されてもいいじゃないかと思ってたけど、台詞言ってると情が移ってね、やっぱり大女優よ、お嬢は。殺すのは惜しいよ、なんとか助けてやって下さい、お願いします」
勘十郎は、鏡の前に正座し、刑事に向って深々と頭を下げた。
藝のために一生を捧げた人間同士の連帯が、ここにはある。相手の藝に対する尊敬がある。勘十郎の気持ちは本物だ。しかし、刑事というたったひとりの観客さえも、自らの「演技」で感動させたい。舞台を降りても芝居がかった台詞と正座で、演じずにはいられない役者の生理が的確に捉えられている。
「言いたいことは山ほどあるけれど、芝居とはそういうものだと知悉していたからだろう。それでもたまに、有吉さんの意図したこととは違う台詞を書いたりすると、『ねえ、ここは、こう直した方がいいと思うけど』と、人に聞かれないように、小声で註文することがあった。脚色者に恥を掻かせまいとする彼女のやさしさだった」
稽古場は、原作者、脚色者、役者、スタッフの微妙なバランスによって成り立っている。刻々と情勢が変化していく戦場でもあった。有吉は、小幡に対する註文を、他人に聞かれてしまえば、稽古場の空気が変わってしまう事を怖れていたのではないか。演劇人独特の繊細な感受性のありようが伝わってくる挿話である。
このように有吉は演劇界の裏表、独特の空気感を知り尽くしていた。その長年の体験があって、この小説の細部を生き生きとしたものとしている。元手がかかった小説とはこのような作品をいうのだろう。
今回、有吉の筆によるエッセイ「『演劇界』は私にとって育ての親」を読んだ。この文章が収録されたのは、『演劇出版社30年』(非売品)である。昭和五十四年、雑誌『演劇界』復刊三十年を記念した豆本で、第二次『演劇界』に関わった人々の短い文章が見開き二頁に載せられている。
「そもそも私に書いたものが活字になる喜びを教えて下さったのが利倉先生でした。学生時代から三年間も連続して書かして頂いたのです。その時の修業が、小説書きへのウォーミングアップになっていることが、よく分ります」
お祝いのために書いた文章とはいえ、あまりにも率直なもの言いに驚く。
「私は歌舞伎が好きでした。好きだから夢中になって見ていました。運良く私は十五世羽左衛門も六代目も見ているので、昔話がそろそろ出来るようになりました。(中略)私の原点は、やはり歌舞伎だったのですから」
と、結んでいる。
弱冠二十五歳、昭和三十一年一月文芸誌『文學界』に新人賞候補となったデビュー作『地唄』が掲載されている。同年八月、新橋演舞場の東西合同歌舞伎で、自作の舞踊劇『綾の鼓』が上演された有吉ならではの言葉だった。
平成十九年十二月歌舞伎座。有吉の没後、二十三年が過ぎた。坂東玉三郎、十八代目中村勘三郎、坂東三津五郎らによって『ふるあめりかに袖はぬらさじ』が上演された。有吉の代表作は、現代の役者の手にかかり、新作歌舞伎として迎えられたのである。