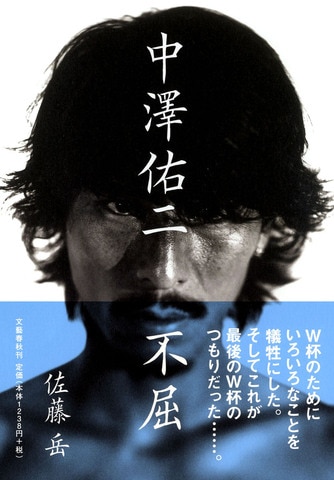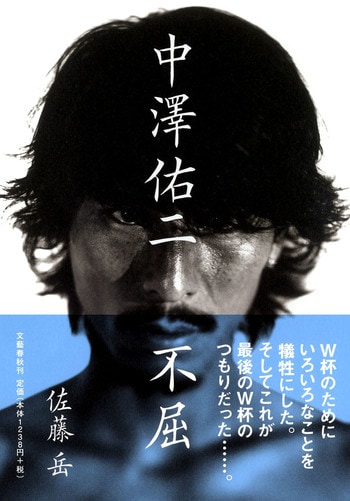南アフリカで取材をしていると、日本国内の熱狂ぶりは意外と伝わってこないものである。例えば、YouTubeの映像で六本木の交差点が狂喜したサポーターによって埋め尽くされる様子を見ても、W杯に対して冷め切っていた日本しか知らないものだから、嘘でしょ、なんて思ってしまう。
だから、電話越しに妻の思いがけない言葉を聞いたときは一瞬、頭が混乱した。 「パラグアイってFIFAランキング、31位なんでしょ? カメルーンが19位だったから、日本は勝てるよね?」
普段サッカーはほとんど見ないはずの彼女がパラグアイのFIFAランキングを語っている。しばし絶句した。日本は大変なことになっていると実感したのはまさにその瞬間だ。
日本に戻ってからはまさしく浦島太郎状態である。パラグアイ戦でPKを外した駒野友一は逆に知名度を上げて「SMAP×SMAP」に出演し、ほかの選手たちもワイドショーにバラエティーに引っ張りだこ。今野泰幸が闘莉王を真似て叫んだ「集まれ~」が脚光を浴び、長友佑都の家族に至ってはすっかり有名人となっていた。ほんのちょっと前まで日本のサッカー人気が風前の灯火だったことを考えると、その尋常じゃない熱狂ぶりに違和感を覚えずにはいられなかった。
ただ、W杯のベスト16自体は偉業に違いないし、それによってサッカー選手の露出が増えるのは悪いことではない。サッカー熱が再び戻ってくれば、Jリーグも注目され、ひいては日本代表の強化にもつながるのだから、むしろ歓迎されるべきことだ。それよりも個人的に奇異に感じたのは、日本を率いた岡田武史監督への「謝罪論争」である。大会前に岡田氏のチーム作りを批判していた評論家やメディアに対し、謝るべきという声が上がり始め、あいつは謝った、あいつは謝ってないというような議論がネット上で繰り返されていた。
そのような現象が沸き起こった経緯は詳しくは知らないが、報じる側がその発言に責任を持たなければならないことは当然だし、場合によっては自ら誤りを認める必要もあるだろう。だが、今回の謝罪云々については、日本代表の表面的な部分だけを見て議論されているようなところもあって、どうにも釈然としない気分になった。
新聞記者として長らくサッカー取材に携わってきた僕にとってW杯観戦は今回で三大会目となる。いずれも日本代表の取材がメインで、日々選手と会話をし、練習や試合を見ては原稿を書いてきた。振り返ると、2002年の日韓大会でも2006年のドイツ大会でもチームの内部では実に様々な出来事が起こり、その小さな事象の積み重ねが結果につながっている。そこにはいまだに報じられていないようなエピソードだって存在するし、代表を取り巻く世界は奇麗事だけで成り立ってはいない。それは今回も同じであって、自国開催以外の大会で初めて16強に進んだからといってすべてがハッピーエンドというわけではなく、今大会の出来事が引き金となって代表からの引退を決めた選手もいれば、逆に代表をやめようと考えていたのに続ける意欲が湧いてきた選手もいる。勝ったから岡田監督は名将、選手はよくやったなどという単純な話ではないのである。

南アフリカW杯は日本代表の選手たちにとってどういう大会だったか。もちろん、23人の選手がいるのだから23通りの見方があるだろうし、監督やスタッフから見ても感じ方は異なるだろうが、今回の代表チームを取材した僕なりに見えてきたストーリーがある。
例えば、本田圭佑がなぜこれほど変わったのか、不思議に思う人もいるだろう。彼はW杯の約9カ月前、2009年9月のオランダ戦で後半から出場する際に、ある先輩選手から「お前、死ぬほど走るんだろうな」と念を押され、「いや、走らないです」と平然と返している。代表チームよりもクラブでの活躍に重きを置いている異分子。それが本田という選手だった。しかし彼は、南アフリカではうって変わってチームに対して献身的な一面を見せるようになった。その本田に象徴されるように、今大会ではあからさまにチームの和を乱そうとする選手が現れていない。その裏にはいくつかの転機が存在し、何度か壁を乗り越えることで全員がひとつにまとまっていった。大会直前までテストマッチ4連敗と絶不調だった日本代表は本大会に入って飛躍的に進化したようにも見えるが、チームとして成長していく段階は確実にあったのである。
それらを世間に伝えたいと考えたとき、本書はある意味でいいきっかけとなった。『中澤佑二 不屈』は中澤佑二の半生を綴った本であり、南アフリカW杯の記録本ではない。ましてや暴露本でもない。なので、本田が変貌を遂げていくような、中澤本人とはあまり関連のない事柄は割愛しているし、南アフリカW杯の章自体、全体の三分の一にも満たない。ただ、中澤のサッカー人生にとって今回の大会がメインディッシュ的な意味合いを持つことになったのは事実であり、彼がW杯までの4年をどう過ごし、どんな思いで本大会を戦い抜いたのかに焦点を当てることで、日本代表チームの軌跡の一端、数多くある真実のひとつを描き出すことができたのではないかと思っている。
それにしても、本書を仕上げるにあたっては本当に山あり谷ありで、多くの人に手助けしてもらった。そもそもの始まりは2008年の秋。「Number」で彼の連載をスタートさせ、最終的に単行本にして出版する企画が持ち上がったことだった。「黙示録」と題された連載は月に一度、中澤に1時間から2時間のインタビューを行い、僕が本人の一人語りの文章へと落とし込んでいくというものだったが、書き手にも語り手にも思い入れがあるために、原稿がスムーズにまとまらないことなんてざらにあり、どう構成するかで揉めたことも何度かある。
最大の危機は、確か2009年の春だったと思う。雑誌自体の特集が日本人FWを再考するというもので、連載も中澤が考えるFW論をテーマに進めることになったのだが、これが拙(まず)かった。彼のインタビューを下地にして、各日本人ストライカーの特徴や長所、短所といった話題を軸に文章を構築し終えると、何カ所か削ってほしいところがあると中澤が言う。だが、指摘された時点では締め切りの都合上、どうしても修正がきかない状況にあり、申し訳なく感じつつも無理だと伝えると、彼は納得せず、今度は雑誌の出版自体を止めてくれと言ってきた。このときばかりはどうしていいものか、途方に暮れてしまった。
話を聞く限り、中澤が我が儘でそんな無理難題を突きつけているのではないことは理解できた。FWはディフェンダーの彼にとってみれば商売敵のようなもの。そのライバルについて、俺はこういうタイプが苦手、ああいうタイプが得意などと軽々しく論じることは自分の弱点をさらけ出すようなものだというのが中澤の言い分であり、確かに言われてみればその通りだった。だが、出版の差し止めなどできるはずもない。僕自身、迷いに迷った挙げ句、これで連載を最後にしようかと切り出すのが精一杯だった。最終的に中澤がもう一度だけやろうと言ってくれて最悪の事態は免れたが、一歩間違えればその時点で連載が打ち切られ、単行本の企画もなくなっていた可能性がある。
このことからも分かるように、中澤という人間はとにかく頑固で、妥協を許さない一面がある。何ごとも自分の中でよく吟味するために決断するまでに多少時間がかかるところもあるが、一旦こうと決めたら簡単に投げ出さない。とにかく貫き通すのだ。そのせいか、普段から発しているコメントも恐ろしいくらいブレがない。それは『不屈』を執筆するにあたって改めて感じたことでもある。
例えば中澤が、日本代表はここがいけない、もっとこうしなきゃいけない、と指摘したとする。どこかで聞いた台詞だと思って取材ノートを見返してみると何年か前に同じようなことを言っていた、なんてことがしょっちゅうあるのだ。一番驚かされたのは、日本サッカーの方向性に対する彼なりの提言である。本書で触れているために詳しい説明は省くが、日本代表の戦い方について彼が見出していた問題点はここ何年もの間、変わっていない。そのため、中澤が口酸っぱく言い続け、改善しようと努力してきたことが南アフリカの地で結実するかどうかという点も、本を執筆する上での重要なテーマのひとつとなった。南アフリカW杯以外でも、彼が長らく追い求めてきたもの、目標としてきたものが実る瞬間が何度かあるが、すべては彼が変わらずに持ち続けた信念の賜物だということが、本書に目を通すことで分かっていただけるはずである。
それにしても、最終章の仕上げの段階は殺人的なスケジュールだった。W杯を終えて2カ月足らずでよく出版にこぎ着けられたと自分でも感心する。当初の予定では南アフリカから帰国して1週間ほどですべての原稿を入稿するという流れだったが、編集を担当して頂いた藤森三奈さんの尽力によって、7月上旬の締め切りが下旬にまで延びることになり、中澤自身も、大会が終わったばかりで疲れ切っている中、数日にわたって取材の時間を割いてくれた。綱渡り的な作業ではあったが、勢いで書き上げた分、南アフリカから持ち帰った思いをストレートに文章に込められたのではと個人的にも感じている。
振り返れば、今回の日本代表と同じように本書にも転機はあった。色々と話し合った結果、「黙示録」のような、中澤の一人語りのスタイルをやめたのである。それによって本来は連載をまとめるだけのはずが全面的に書き下ろすことになり、執筆の労力も増したが、すべてをやり終えた今となっては、周辺取材などによって多くの関係者の視点を盛り込むことができ、作品としての幅が広がったという手応えがある。中澤が20年のサッカー人生をどんな思いで駆け抜けてきたのか。ドイツW杯の後、一度は日本代表から引退した彼が南アフリカW杯を終えた今、何を思うのか。そして南アフリカW杯を戦う裏側で何が起きていたのか。『不屈』だけでしか知り得ない真実があると自負している。