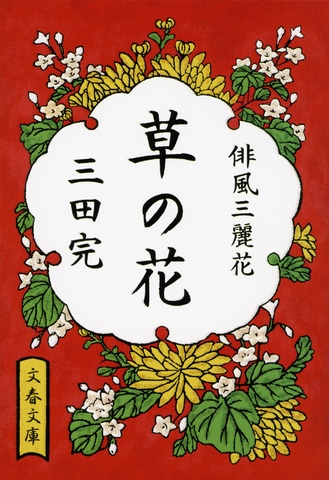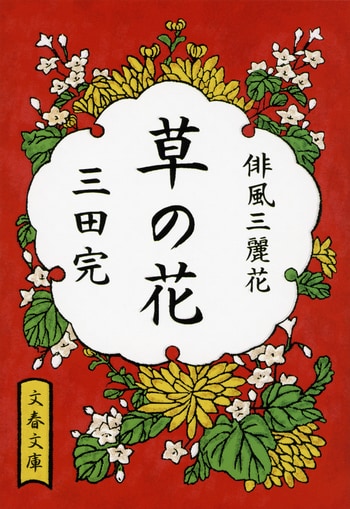三田完さんとの初めてのお目もじは「茉莉花」仕舞いの夜だった。
私の夫であった久世光彦がひょいと三途の川を飛び越えて、残された私はひと恋しさにおずおずと、銀座に茉莉花というバーを開いた。それから五年が経って、もう一生分の人に出会えた、そろそろ幕引きの頃合いだと決めた仕舞いの夜、だった。
そうとは知らずのおでましに、それも生前に私をかわいがってくれた上村一夫さんのひとり娘である汀ちゃんの案内で、なにかご縁があるようで気になった。けれどその夜は初めましての挨拶だけ、ひとりカウンターの中で右往左往しているうちに、三田さんはそっとお帰りになられた。
長い最後の夜が終わって、灯りを落とそうとして気がついた。隅の椅子の上に帽子が残っている。その横にはジョーゼットのマフラーも。どなたかの忘れ物だ。「濃鼠(こねずみ)」のソフト帽に「幽(かす)かな」白を効かせた貝紫のマフラー、こんな粋な組み合わせをまとう方は、と考えて、ふっと目に浮かんだのが三田さんだった。
やはりそうであった。忘れ物を小さな箱に詰めて、思いついて久世の著書『マイ・ラスト・ソング』を入れてお送りした。末期の刻に聴きたい一曲を探し続ける、その本を私はなぜ入れたのか、ほどなくして届いた礼状にそえられていた、昭和の歌との濃密な時間を綴った三田さんのご著書『歌は季につれ』を読んで合点がいった。三田さんは作家ではあるが、テレビの、それも歌謡番組の制作を長くつとめ、四十をすぎて書き始めたという。久世と同じく、戦後というあのころに少年だった、阿久悠さんの息づかいを長らく傍らで聴いていた、とも。そうして俳句。
久世も俳句が好きだった。ただし鑑賞するだけで、詠むことはしなかった。仕事机の上には常に、形見の高浜虚子編の俳諧歳時記があった。久世の父は職業軍人でありながら、鵼王という雅号をもつホトトギス派の俳人だった。といっても趣味の域を出ない、がたったひとつの趣味であった。だから俳句は父の聖域であると、手をそめなかったのだ。三田さんにもそんな時があったと知った。――私は三田さんに、久世と同じ匂いをかぎとっていたのだ。
素敵な「手蹟」であった。三田さんの手にかかると、「日本橋の紙舗、榛原(はいばら)で購(あがな)った」蛇腹便箋の、朋という字が「莞爾と笑む」。
その日から、同じ三月生まれで一つ年上の三田さんに、私は老朋友にしていただいた。それまで縁がなかった歌舞伎や文楽、落語の面白さを教えてくださったのも三田さんだ。
物語のはじまりは昭和十年三月、満鉄大連病院への赴任が決まった三麗花のひとり、東京女子医専の学生であった池内壽子の卒業式からである。前作の『俳風三麗花』の、昭和七年、満洲国の建国宣言がなされた年の夏に、日暮里渡辺町の暮愁庵句会で出会った三人娘に歳月は過ぎ、阿藤ちゑは日本橋で東京帝大工学部助教授の妻に、浅草藝者の松太郎は六代目菊五郎の世話に、そうして池内壽子は医師として「柳絮」舞う大連へ。二・二六事件をはさんだ戦前の、凪いだ青海原のように、日本がつつましくも豊潤だった時代。
登場人物は多彩だ。「広くて狭い満洲国」で、壽子が偶然知り合った川島芳子、甘粕正彦、そして満洲国皇帝・溥儀、東京市では永井荷風まで登場する。歴史上の人物が、三田さんの筆で生き生きと動き出す。「唐辛子で真っ赤に染まった鰻重を平然と口に運びながら、芳子さんは甲高い声でとうとうと語りつづける」。甘粕は「せかせかとウィスキーを口に運びつつ、ぶつぶつと独り言をつぶやいている」。荷風になると「不機嫌な表情で虚子先生から視線を逸らした。ついで日本髪の松太郎を一瞥すると、男の頬がわずかに弛(ゆる)んだ。だが、すぐにまた不機嫌な顔に戻り、浅草寺の方角へ歩きはじめる」と。その虚子先生は「長州薩摩の連中に威張られるのが嫌で、お若いころ、戸籍を琉球に移してしまったんだよ」というおまけまである。その頃は本籍が北海道か沖縄だと、兵役に取られなかったそうだ。
甘粕正彦と川島芳子が企てた、満洲国皇帝・溥儀の御前で開かれた句会を最後に、三人が集うことはかなわなくなった。「銃火と不安の歳月が、病身の象の歩みのように重くゆっくりと流れた」。それぞれが戦禍に呑まれ、もがきながらも生きながらえて、昭和二十二年の三月、「花衣」をまとった「三人の見目麗しい名花」がそろって暮愁庵におもむくまで。その歳月の舞台は東京市と満洲である。
満洲ときくと、胸がときめく。昭和三十二年生まれ、戦後すら知らない私がなぜ、と自分でも不思議である。実際にその時代の風景を見たわけでも、街を歩いたわけでもないのに、なぜかそこが懐かしい土地に思われるのである。さざめくような郷愁を感じるのだ。
奇妙な錯覚なのだろうが、壽子が目にする「そよと吹く風に乗って右から左へ、白く小さな綿毛が陽光をきらきらと反射しながら舞っている」柳絮が、アカシアが咲く五月の大連の並木道が、私の目の裏に浮かぶ。ある夜は夢の中で、御前句会へと新京に向かう「三麗花」を乗せたあじあ号の展望車に、私も乗っているのだ。花街で漁色を重ねる夫に、花柳病を伝染されたちゑ。そのちゑを救うためのペニシリン開発は、甘粕正彦の力に頼るしかない。深夜のヤマトホテル、208号室のドアをノックする壽子は私かもしれない。そうして川島芳子が詠う「壮大な曠野に沈む巨きくて真っ赤な夕陽」を背に駆け抜ける、女馬賊にもなる。
満洲は時空を超えて、ある種の日本人の胸の底に、秘かに棲み続けているのかもしれない。三田さんも、ある種、のひとなのだ。
美は細部に宿る、と私は信じている。その細部が豊富で、柱や梁が立派に組み上がっているこの物語のために、三田さんが選んだ言葉、その使いかたが素晴らしい。「黄ばんだ象牙の箸」、「黄ばんだ」だけで過ぎ去った歳月の長さを表すことのできる日本語。ひとつことを幾通りにでも表現したり、持って回って言ったりする日本語を、とても大切に思っているのだと思う。漢字で表すか、ひらがなにするかにも細かく気を配っている。
たとえば、「欣快に堪えませんな」「逗留する」「磊落な笑い声」「滋養をつけないと」「白い美髯をたくわえた」「おっかない方」「根を詰めて」「気づまりな関係」「狷介な人物」「廚」「匙」「学舎(まなびや)」「いたわしいことでした」「とんでもないことでございます」「難儀なことで」「もくろみ」と、きりがないのでここまでにして。書き出したものは死語と半死語が混ざり合っているが、三田さんは死語に息を吹き込み、まだ息のあるものはなんとか生き永らえさせたいと祈っているようだ。いかにも日本語らしく、日本人の気持によく似合った言葉が消えていくのが哀しいのだ。
『草の花』は昭和十年の三月に幕が開き、昭和二十二年の三月に幕を閉じた。あの時代の、満洲と東京市を舞台にした巨きな物語、のようにみせて、実は「草の花」、「民草」の生きていることの切なさとあたたかさをふんわりと残すあたり、なかなかの手練(てだれ)者とお見受けいたしました。
などと言ったら、三田さんはぽっと頬を染めて含羞(はじら)うだろう。焦茶革のハンチングを目深にかぶり直して、角を曲がって消えてしまうに違いない。――そういう、いろっぽいおひとである。
平成二十六年 雛納の夜に