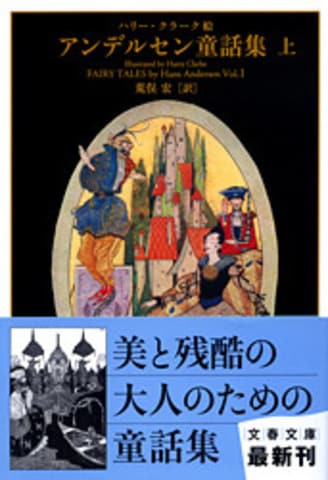アンデルセンの童話というのは未来の読者のために海に投ぜられた「瓶の中の手紙」ではないだろうか? つまり、発表された時には子供向きの童話と思われていたものが、時がたつにつれて次第に別の意味を持つ物語であるらしいとわかってきて、ついには、永遠に新しい現代の寓話(ぐうわ)と評価されるに至ったという意味で、真の読者に届くまで長い時間のかかったお話だということである。
たとえば、誰でも知っている「みにくいアヒルの子」。これは、俗人の間で育てられた芸術家気質の子供の悲劇、ひとことで言えば童話版の「トニオ・クレーゲール」であると信じられてきたのだが、時間がたつにつれて、どうももう少し上のレベルを狙った寓話らしいとわかってきた。
では、いったい、何の寓話なのか?
どうも、人間として生まれた以上、誰もが経験しなければならない、自我の処理を巡る葛藤のドラマなのである。
と、いきなり自我といってもわかりにくいかもしれないので、ここで自我を一つのパイにたとえてみよう。パイは自分のものだから全部自分で食べられるというのは近代以降の話で、前近代にはパイの一人食いは社会的に許されなかった。親の分、兄姉の分、共同体の分というように切り分けを行わなければならなかったからだ。
この自我パイの切り分けを断固拒否して、パイは全部自分で食べるぞと宣言したのがフランス革命であり、ロマン派革命である。
アンデルセンがみにくいアヒルの子で表現しようと試みたのはじつはこの自我パイの一人食いの葛藤の物語なのである。
そのことは、アンデルセン自身の生涯に照らしたとき初めて明らかになる。
アンデルセンは1805年、デンマークの貧しい靴職人の家庭に生まれた。世代的に見ると、生年はフランスのロマン派たちとほぼ同世代だから、アンデルセン少年が抱いた「自我パイは自分だけで食べたい」という願いはそれほど突飛なもののようには映らないかもしれないが、当時のデンマークのおかれた状況、及びアンデルセン少年の家庭環境などを考慮に入れると、これはある意味とんでもなくだいそれたことなのである。
ヨーロッパの後進国にすぎなかったデンマークで、しかも、靴職人の息子ということであれば、選ぶべき人生の選択肢は職人になるという道しか与えられてはいなかった。にもかかわらず、アンデルセン少年は職人でない何かになりたいと思った。その選択は極めて例外的なことだったのである。
この例外性がみにくいアヒルの子の切実さを支えている。どうしてそうなったのだかわからないが、自分だけは自我パイを1人で食べたいと思うようになり、そのことが周囲との摩擦を呼び、いじめの原因にもなる。この苦しさはだれにも理解してもらえない。ならば、自我パイの一人食いが許されるどこか架空の国に空想の中で旅立つほかはない。
これがまさにアンデルセン自身の物語であり、童話を貫く1本の糸なのであるが、その切実さは自我パイの一人食いが19世紀デンマーク以上に認められていなかった高度成長以前の日本社会には正確には伝わらなかった。
しかし、そんな中でも、ごく一部だが、アンデルセンの問題提起をしっかりと受け止めている人もいた。そうした少数者の1人がほかでもない、本書の翻訳者たる荒俣宏氏である。
幻想文学の紹介に一生を捧げようと決意しながら、あえてアヒルたちの群に混じってサラリーマン生活を送っていた若き日の荒俣宏氏こそ、自我パイは全部自分で食べたいと最初に願ったみにくいアヒルの子であり、日本のアンデルセンであったのだ。
ゆえに、ここには原著者と訳者の間の幸せなる同一化があり、それが訳文にも見事に反映されている。
アンデルセンの童話が最高の理解者の手によって翻訳され、おまけに、訳者の最も愛する挿絵画家のイラストまで添えられて、文庫として蘇ったことを心の底から喜びたい。