忙しくても1分で名著に出会える『1分書評』をお届けします。 今日はヤマザキマリさん。

約12年の留学生活を終えていったん日本に戻って来たのは1996年の事だった。10代から暫く離れてしまっていた日本という祖国へ再びどのように入り込んで行ったらいいものか、美術の学校しか出ていないのに仕事は見つかるのだろうかといった大きな不安と懸念を抱えての帰国だったが、イタリアという国と文化への強いシンパシーを様々な分野で活性させていた当時の日本は、そんな私を積極的に迎え入れてくれた。
いくつかの大学でのイタリア語の講師、テレビでのイタリア家庭料理紹介、イタリア文化関連のイベント企画。私は様々な場所でイタリアに憧れる日本の人たちの為に、イタリアの魅惑をアプローチするのに大忙しな日々を送っていたが、反面で、自分が見たり感じてきたものとはかなり次元の違うイメージをアプローチする事への強い虚無感を抱えてもいた。私のイタリアでの暮らしは明るく楽しく、美味しいものを食べたり歌ったりしながら人生を謳歌する、という概念の世界とは程遠いものだったからだ。
お金のない文化人達や解放の神学を唱える神父、政治的理由で亡命を余儀なくされた他国の知識人達が集まるとあるフィレンツェの画廊を兼ねた小さな出版社で、素うどんならぬ「塩・こしょうパスタ」を作って皆で分け合ったり、家の水道も電気も止められ、バス代も無いから徒歩かキセル乗車という荒んだものだった。映画館ではパゾリーニの映像を見て仲間で論議し、政治的見解の齟齬で喧嘩をし、創作という行為に無意味さを感じて鬱にもなり、画廊に集まる老衰した知識人達の切ない死にも幾度か接してきた。そのうちの何人かは大戦中の記憶を昨日の事のように語って聞かせてくれる元パルチザンだったりした。それが私のイタリアにおける暮らしだったが、そんな過去を日本に戻ってから表に出すことは全くなかったし、知りたがる人もいなかった。
須賀敦子という作家を知ったのは丁度その頃だった。『コルシア書店の仲間たち』が彼女の作品で初めて手にした一冊だが、私はその美しく構築された文章の中から表れる情景に救済されたような感覚に陥った。それは、日本に帰ってきてから、やっと自分の見て来たイタリアを判ってくれる人と巡り会えたかのような、深い安堵だった。
「コルシア書店」で描かれているミラノと、この書店と彼女が拘わりを持っていたのは1960年代なので、私が留学をしていた80年代とはまた社会全体や人々の様子も違っていたはずだが、それでも私はこの作品の中から、あのフィレンツェの画廊の空間を満たしていたのと同じ空気を感じ取れるのだった。
その画廊で「お前はイタリアの事が何も解っていない。これを読みなさい」と作家の人から手渡された幾つかの本の中には「サバ」や「ウンガレッティ」と言った、コルシア書店で須賀が接してきた詩人達のものもあった。イタリア語もろくに理解できていなければイタリアがどういう過去を持つ国かも知らない私にとっては、どちらも頗る難しい詩集であったが、イタリア文学というものを、ああいった作家達の側面から知るに至ったことを今ではなんて恵まれていたのだろうと思う。
ちなみに、「日本人なんだからこれも読みなさい」と同じく老作家から手渡されたイタリア語訳の『砂の女』は実写版の、抱き合う男女がカバーになったものだった。既に沢山の人に読まれてボロボロだったが、後になってから知ったのは、その手渡された『砂の女』だけでなく書棚にあったイタリア語訳の日本文学を扱った書籍の多くが、コルシア書店時代の須賀さんの翻訳だったということだ。つまり須賀敦子という人は私の日本文学への誘い人でもあった。
貧しさと苦悩で費やされたかのような留学時代のイタリアの記憶に、須賀敦子という存在が彩りと確かな質感を加えてくれたように感じている。




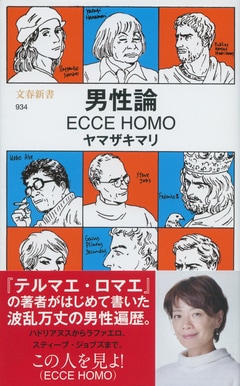
![[刊行記念対談]島田雅彦×ヤマザキマリ美女ほど不幸の蜜を吸う? 『傾国子女』白草千春的・女の生き方](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/f/5/480wm/img_f5b3c91428ea64da253decb18608918646443.jpg)









