二〇一七年、第四回高校生直木賞を受賞した須賀しのぶさんの『また、桜の国で』は、第二次世界大戦下のポーランドを舞台に、ロシア人を父に持つ外務書記生の棚倉(たなくら)慎(まこと)がドイツ侵攻の中で様々な葛藤を経ながら生きる姿を描いた長編小説だ。選考に参加した代表生徒からは「登場人物が生き生きしている」、「戦争だけでなく友情やアイデンティティの問題を扱い、物語の中に一番入り込めた」という意見が上がり、恩田陸さんの『蜜蜂と遠雷』と最終投票にまでもつれこんだ。第五回の本選考会前に催されたトークショーには、前回の選考に携わった生徒も含め百人以上の高校生が参加し、創作の裏側や須賀さんの高校時代のエピソードに熱心に耳を傾けた。
歴史を作るのは普通の人の集まりだと学んだ高校時代
須賀 小説を書くときに、私は若い読者を想定することが多いです。理由は二つあって、コバルト文庫という少女向けのライトノベルで二十歳の頃にデビューして、三十六歳ころまで少年少女小説を書いてきたこと。そして、自分の高校生時代を振り返ると、そのころ出会った本が、私の人生を一気に広げてくれたという実感があることです。まず一冊あげると、ウィリアム・シャイラーの『第三帝国の興亡』というナチスドイツのドキュメンタリーです。この本はヒトラーの幼少期からナチスが崩壊するまでを描いています。筆者はアメリカ人ジャーナリストなので、今から考えると視点は偏っており、ナチス憎し、という気持ちが冒頭からあふれています。ところが、その辛辣さにもかかわらず登場人物が非常に魅力的なんです。あえて小説的な表現を使うと、キャラクターが、歴史活劇やライトノベルのキャラに近い個性を持っている。私は小説の必須条件として、キャラクターのどこかに共感できる部分が必要だと思っているのですが、『第三帝国の興亡』の登場人物には理解できるところがたくさんあるのです。もちろん、ナチスドイツが犯した罪は絶対に許されないことですから、ナチスに心酔していく彼らに時おり共感してしまう自分に戸惑いました。そのとき、歴史を作るのは、異常な人ではなく普通の人の集まりだとわきまえて過去を見るべきなんだと学びました。
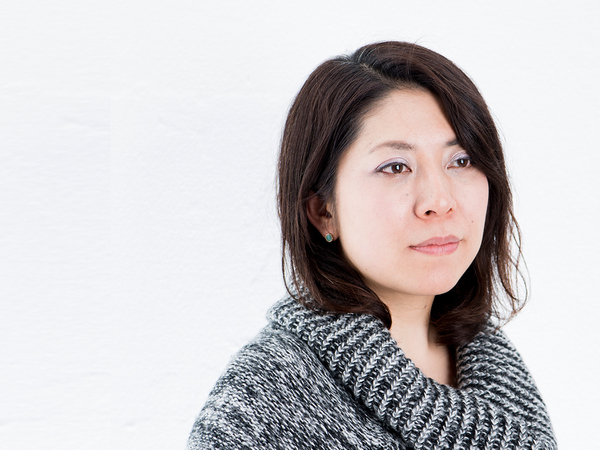
新しい世界を知る喜びが高じて大学では史学科に行き、気が付いたら小説家になっていました。自分が本を書くときも、かつての自分のように、世界を違った視点で見たいという人のフィルターになれたらいいなと思っています。
ただ、『また、桜の国で』の舞台のポーランドはあまり知られていない国ですし、第二次世界大戦のポーランドには悲惨な事件が多くあります。過酷な歴史だけが印象に残らないように、青年たちの友情を描いて読みやすくするなど努力をしましたが、最初はあまり売れ行きが芳しくありませんでした。そんなこともあって、皆さんが賞に選んでくださったときは、高校時代から今まで抱いてきた思いが報われたと感動しました。



