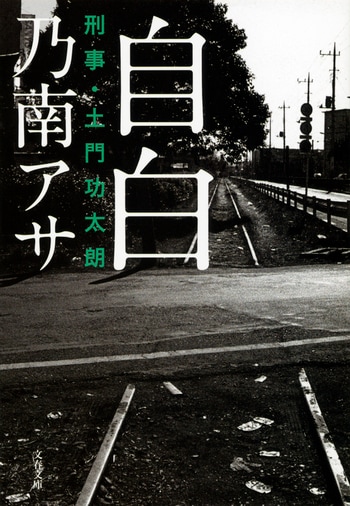明治十六年、十勝内陸部の本格的な開拓に初めて乗り出した「晩成社」をご存じだろうか?(帯広「六花亭」名物マルセイバターサンドのレトロな包装は、晩成社製バターの「成」マーク入りラベルを復刻したものだ)。
乃南さんの新刊は、この晩成社を率いた依田勉三、渡辺勝、鈴木銃太郎ら三人のリーダーの“苦闘の日々”を、鈴木の妹で渡辺の妻となった才女カネの視点で描いた大長編小説である。
「十年前、知床の開拓移民を主人公に『地のはてから』を書きました。その取材で、アイヌの専門家である学芸員さんにお話を聞こうと帯広百年記念館を訪ねた時、たまたま目にしたのが晩成社のパネル展示だったんです。中でも、落ちぶれ果てた格好で、ボロ簑を被って座り込んだ男の写真が強烈で、聞くと『これが依田勉三だよ』って」
その時の学芸員さんの解説が、乃南さんの背中を強く押したという。
「第一声は『あれは桁外れな連中でねえ』でした(笑)。『何もないとこに都会からやってきて、鍬一本で土地を開こうとした。学歴も、家柄もあるのに無茶ばかりやった連中なんだよ』と。
しかし――と、話は続きました。
『晩成社のすばらしかったのは、リーダーの鈴木、渡辺やカネさんがキリスト教徒で、差別意識なくアイヌの人たちと交わり、彼らに慕われ、その知恵を借りて生き延びることができた』のだと。
それを聞いて、私は思わず『この話、他の人にしないでください、私が小説に書きます』と言ってしまったんです(笑)」
それから十数年、他の小説に取り組みつつも、ずっと晩成社のことを調べ続けた乃南さん。知れば知るほど依田たちに惹かれていったという。
「依田は伊豆の豪農の三男坊で、素封家のお坊ちゃんだけに、亜麻、牛肉、バターと、思いついたら何でもやる。だけど、ひとつもうまくいきません。彼の直筆の日記を見ると、信じられないくらい細い字で几帳面に書かれていて、融通のきかない性格だということが一目でわかるんですよ(笑)。
そのくせ彼は“天然”でもあって、井戸を掘ろうとカンテラを持ったまま穴に入って酸欠になったりもする。貧しい環境や寒さを苦にしないのは立派だけど、その実、一年の半分くらいは内地に帰って羽をのばしているし、とても人間臭さのある人だと思います」
明治維新後、全ての価値観が一変する変革期に、従来の暮らしを捨てて、突然、原野に渡った若者たち――。
「遠い昔のようだけど、ほんの三、四世代前の物語です。今、先の見えない毎日を生きている我々もまた、依田勉三たちの孫であり、ひ孫であるという事実を、私は忘れたくないんです」
のなみあさ 一九六〇年東京生まれ。『凍える牙』で直木三十五賞、『地のはてから』で中央公論文芸賞、『水曜日の凱歌』で芸術選奨文部科学大臣賞。近著に『六月の雪』等。