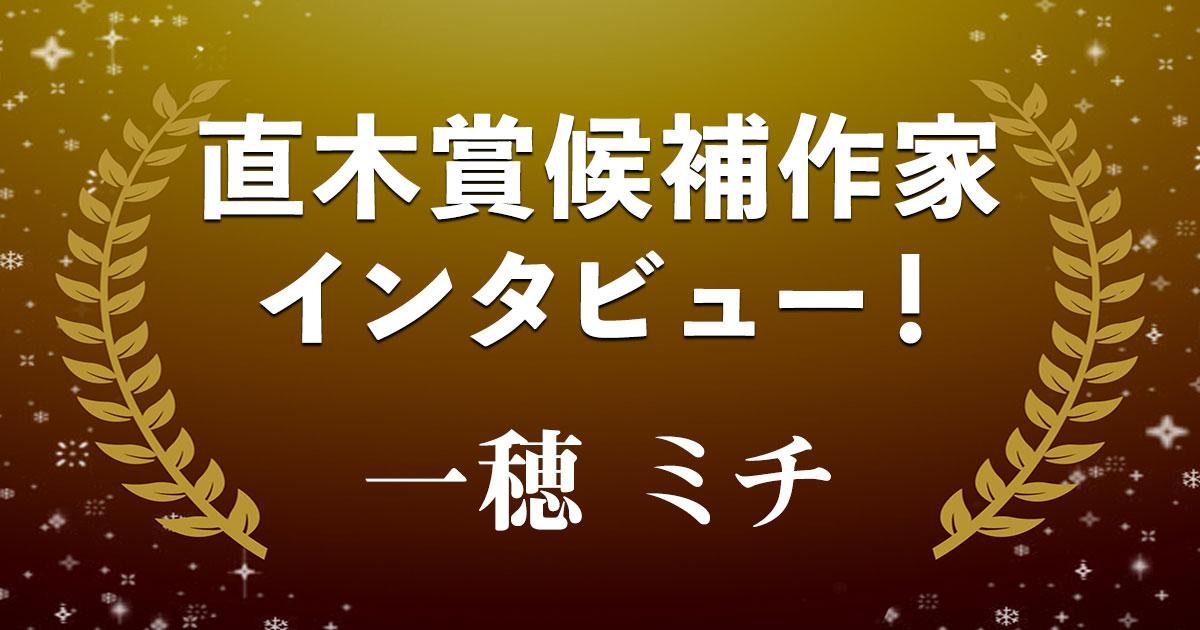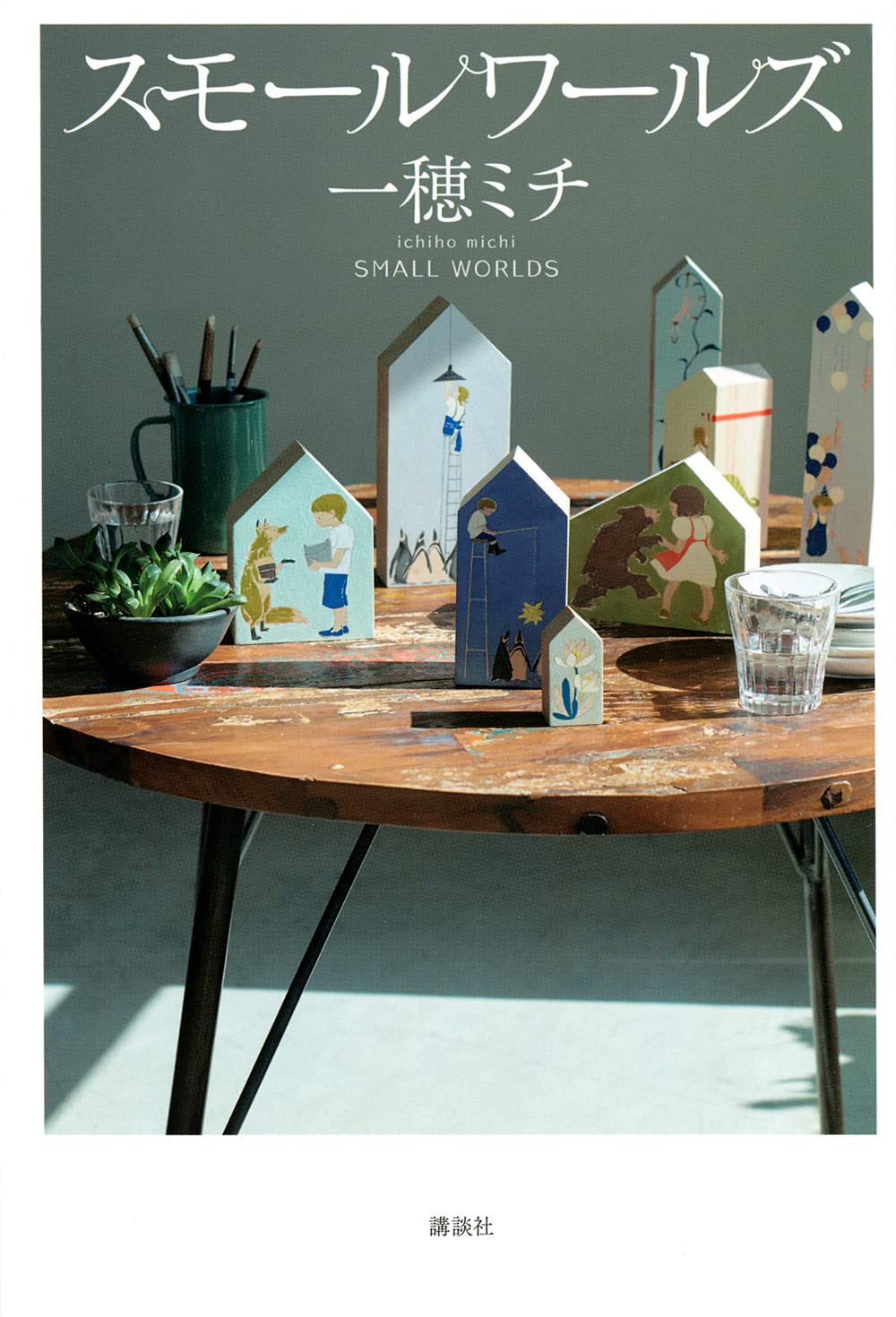
永遠に読まれない本のこと
高三の時の現代文の教科書が、今も家にある。日栄社の「近代名文選 作品とその評論」。いたく物持ちが悪いわたしのもとで五回の引っ越しを生き延びた本は端っこがパンケーキの色に褪せて何やらおいしそうだ。
夏目漱石のエッセイ「硝子戸の中」と、江藤淳の評論「現代と漱石と私」が妙に好きで捨てられない。「美しい月が静かな夜を残る隈なく照していた」夜、人知れぬ苦悩を抱えて生きる女性に「そんなら死なずに生きていらっしゃい。」と声をかけた漱石、そんな文豪について「人と人とのあいだにあえて身を投じ、その心のもっとも柔かな部分を進んでひらくことができた」と書いた江藤淳の文章をセットで読むと、しんみりと穏やかな気持ちになる。月光の下を「懐手をしたまま帽子も被らずに」歩いていく後ろ姿や、足下に伸びた影を思い描いて、夏目漱石という人がもうこの世にいないことがふと寂しくもなる。わたしが生まれるはるか以前に生きて死んだ作家なのに、おかしな話だ。「死なずに生きていらっしゃい。」という言葉の重みは、年を追うほど切実になっていく。
言わずもがな、教科書に載っているのはごく短い抜粋に過ぎない。だから「硝子戸の中」も江藤淳の評論も、ちゃんと読まなきゃと思いながら四半世紀以上経ってしまった。年に何回か教科書を読み返しては「やっぱりいい、ちゃんと読まなきゃ」と決心し、すぐに忘れてしまう。この世に未完の書物が数多存在するように、わたしには「未完読」の本がたくさんある。相性が悪かったり、難しすぎたり、時間が空いて何となく読みさしのままになっていたり、理由はさまざまだが、この教科書の二篇に関しては「十七歳の自分から上書きしてしまいたくない」からだと思う。何度でも「ちゃんと読まなきゃ」と十七歳の新鮮な気持ちに立ち返って安堵したい。わたしの心の「柔かな部分」はまだ生きていると。そんな「永遠の未完読作」が今も本棚の片隅に押し込まれている。