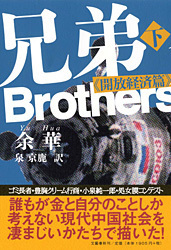もっとも両民族が近いと思った心情がある。それは、両国民ともコンプレックスの塊(かたまり)だということだ。中国人は何ごとにも傍若無人(ぼうじゃくぶじん)というイメージがあるが、実は自分たちの欠点をよく知っている。日本を含めた西側先進国を簡単には越えられないと諦めてもいる。だが、彼らはそれを悟られたくないから、とにかく強気な態度を見せる。一方の日本人は、劣等感故に明言を避け、曖昧な態度に終始してしまい、国際社会では目立たない善人に徹してしまう。双方のコンプレックスの本質は、余り違わないように思う。なのに、それが表に出る時に正反対の行動になる。
同じ根っこを持ちながら、正反対の行動として表出してくる。双方は違うという目を持つと、その向こうに同じ臆病で見栄っ張りの“よく似た顔”の隣人が浮かび上がってくる。
余華氏の『兄弟』を手にして、私の認識は、より強固な確信に変わった。
同作は、二人の血の繋がらない性格も真逆の兄弟が、文革から改革開放という二つの破壊的な時代を体験する物語だ。読んでいるうちにアゴタ・クリストフの『悪童日記』やジェフリー・アーチャーの『ケインとアベル』を思い出した。
だが、本書は中国の小説であるという覚悟と共にページを開いた方がいいだろう。とにかく全篇に中国的毒がちりばめられている。その毒にはまれば、麻薬的快感を手にして寝る時間も惜しんで読み耽(ふけ)る事になる。だが、あまりにも日本的なる価値観の中で暮らしてきた人には、毒気に当てられて怖くてページがめくれなくなるかも知れない。
私自身は、その何(いず)れでもなかった。いや、最初は毒気に当てられた。だが、前述した中国人への認識を思い出すにつれ、この作品にちりばめられた毒の意味の深さにひたすら感心した。
過剰で過激、露悪的で偽悪趣味の登場人物たちの行動の奥底に、えも言われない人間の業(ごう)や哀(かな)しみが見えてくる。そして、人の幸せとは何かという大命題が、容赦なく襲ってくる。そこまで行き着いた瞬間、読者は“国境”を越える。そして、根っこの根っこでやっぱり同じ本質を持つ隣人としての共感が込み上げてくるのだ。
別に中国を知るために読む小説ではない。それどころか、泣いて笑って吃驚(びっくり)している間に読み終えてしまい、中国と日本の違いなど考える間もないだろう。だが読み終えた後、中国人というものが今までと違うイメージをもって理解できるのではないだろうか。
その時こそが、私たち日本人が中国人と向き合う準備が整った時になるのだ。