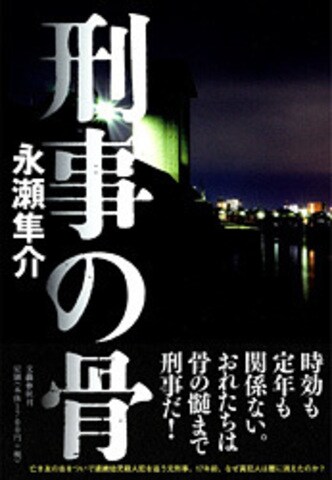永瀬隼介の小説家デビューは2000年である。以後、精力的に、ときには1年に2冊、3冊といったペースで力作を刊行してきた。なかでも警察小説は明らかに得意分野であろう。近年はこのジャンルの短篇執筆に意欲を見せているところもあった作者だが、本書『刑事の骨』はまぎれもなく重厚さを感じさせる、ボリュームたっぷりのエンターテインメント長篇だ。
物語の第1部は、1993年から始まる。東京都内の2箇所で発生した連続幼児殺人事件。偏執的な愉快犯と思われる人物から捜査本部に電話がかかってくる。2人殺したのでこれから3番目を殺す。警視庁捜査一課の管理官・不破孝作に犯行予告をしてきたのだ。ドナルドダックのような声の出し方が何とも不快だ。今の居場所を見つけ出し、身柄確保をできないものか。本庁の出世競争を生き抜き、エリート・コースに乗ったと自負している44歳の不破は、失敗する恐怖、焦燥を強く募らせる。
一方、不破と同期の田村保一は出世街道から完全に外れていた。東京都下の西、田舎然とした場所で交番の制服巡査を務めている。そんな彼がたまたま電話ボックスのなかにいる不審な男を見つける。彼こそがダックボイスの人物であった。電話で不破と田村がつながった。同期とはいえ、不破のほうが命令する立場だ。興奮のあまり「射殺してもかまわん」と叫んでいた。謎の男は逃げ切り、第3の殺人が起きた。迷宮入りになった。不破は責任を取らされ、捜査本部から外れた。エリートの道も途絶えた。