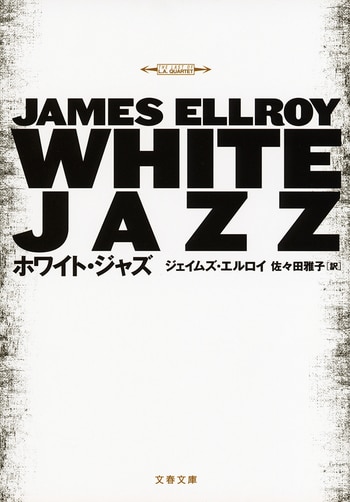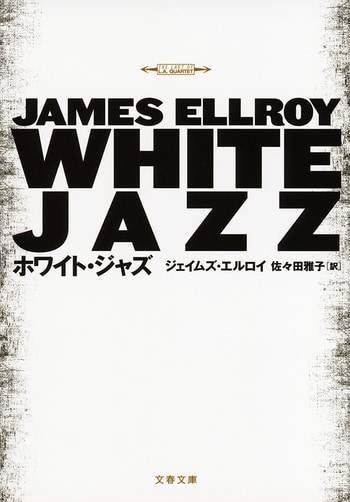擦り切れたカヴァー――白い背景は黒ずみ、黄ばんでいる。背表紙は歪んでいる。いたるところに折れ、ねじ曲がった附箋(ふせん)が貼られている。
歴史の表面には決してあらわれない、暗黒のLAの歴史。悪人たちが跋扈(ばっこ)する。空気は腐臭を放っている。アスファルトには絶えず血が流れている。悪人たちは咆哮する。秩序などくそくらえ、モラルなどくそくらえ。そもそものはじめから、アメリカが清らかだったことなどない。人間が善良だったこともない。この世は歪んでいる。貪欲さといびつな性欲と悪意で成り立っている――と。
『ブラック・ダリア』で幕を開けたその暗黒の歴史書を、わたしは常にある種の陶酔とともに読みふけってきた。『ビッグ・ノーウェア』、『LAコンフィデンシャル』、そして――『ホワイト・ジャズ』。
翻訳が刊行されると同時に読んだ/興奮した/ 眩暈(めまい)を覚えた。貪るように読み終え、余韻が続く中、再び一ページ目から読みはじめた。たった二年ほどの間に、少なくとも五度は読み返した。おかげで本は擦り切れた。三十数年の人生の大半を本を――小説を読むことで費やしてきた。それでも、こんな経験は初めてだった。
『ホワイト・ジャズ』――わたしのバイブル。
読むたびに心が震える。読むたびに眩暈を覚える。それまでのエルロイ作品を読んでも、わたしの心は震える。だが、『ホワイト・ジャズ』は他を圧している。
「悪い白人」たちが奏でる狂乱のジャズ。そのヴォリュームは強大で、計算されたコードの乱れは聞くもの=読むものを酩酊させる。
そう。まわって、落ちていく。懇願する――だれか、おれを救ってくれ。内なる暗黒を垣間見たものに与えられる狂おしい情念。わたしの魂は揺さぶられる。激しく/残酷に/切なげに。
エルロイが与えてくれる。エルロイだけがそれを与えてくれる。
六度目か七度目の『ホワイト・ジャズ』。相変わらず、興奮し、怯え、戦(おのの)く――嫉妬する。
エルロイのように書きたい――エルロイになりたいわけではない。ただ、エルロイのように書きたい。わたしの中の、獰猛ななにかがそう叫ぶ。
エルロイはそれだけの作家ではない。あの綿密に組み立てられた精緻なプロットこそが、エルロイをしてアメリカを代表する作家たらしめているのだ、と。
くそくらえだ。
確かに、出世作の『ブラック・ダリア』以降、エルロイの作品は変わった。精緻なプロットの導入で、それまでは一部の人間から愛されるだけだったエルロイの作品は、全米でベストセラーとなるようになった。だが、それは小説を書く技術が向上したというにすぎない。異論がでそうだが、いいきる。小説は技術で書くものではない。したがって、エルロイ作品の魅力はその精緻なプロットにあるのだとするものは、エルロイの読者たる権利を自ら放棄している。
なぜ、ある種の人間がエルロイの作品に取り憑かれてしまうのか。明確な答えはエルロイの内面にこそある。エルロイはとち狂っているのだ。なかでも、『ホワイト・ジャズ』はとち狂っている。『ブラック・ダリア』からはじまる〈暗黒のLA四部作〉――実際のところ、『ブラック・ダリア』と他の三作にはそれほどの接点はないが――はどれもとち狂っている。しかし、『ホワイト・ジャズ』のとち狂い方は、四部作を締めくくるに相応しい。
厭くことのない妄念、それを作品にちりばめて世界にばら撒こうとする意思。『ホワイト・ジャズ』ではそれは文体となって現れる。
徹底的に削られ、刻まれ、スラッシュやイコール、セミコロンなどの記号がちりばめられた異様なまでに短いセンテンス。読みはじめはとっつきにくいが、やがて、読む者をその粘着質の世界に取り込んで離さない。読むのを止めることができなくなる。狂乱の渦の中で、主人公・デイヴ・クラインの疾走する姿に自らを重ね合わせていく。デイヴ・クラインと同じように、まわって、落ちていく感覚を味わう。
呪文――エルロイは自らの妄念を世界中にばら撒くために、それに相応しい呪文を産みだした。なんという作家、なんという妄念。
この呪文のような特異な文体を産みだした/産みださずにいられなかった執念こそが、エルロイをエルロイたらしめている。その執念こそがエルロイの魅力の全てだ。どれほど歪んでいようと、その純粋さこそ、エルロイ作品がわたしのような人間を魅了してやまない理由だ。それ以外はすべて、付属物にすぎない。精緻なプロット、奥の深い人物造形――そのどれに対しても、エルロイは素晴らしい腕を発揮する。だが、そうしたものを楽しみたいのなら、他の作家の作品を読めばいい。
エルロイは偉大な作家だ。だが、その偉大さは、彼の執筆テクニックに依っているわけではない。断じて、ない。
* * *
わたしの手元には、もう一冊、『ホワイト・ジャズ』の単行本がある。何度も読み返され、くたびれきったものとは対照的に、その単行本は真新しく、わたしの本棚に収まっている。表紙を開くと、そこにはエルロイのサインがある――添え書きとともに。
血をまき散らせ。
これが、エルロイだ。
* * *
ここまでの文章を読み返して、わたしはため息をつく。
エルロイの、それも『ホワイト・ジャズ』のことになると、わたしは常軌を逸してしまう。意味を成さない文章の羅列――独断と偏見に凝り固まった愚か者の遠吠え。
しかし、それ以外にわたしはエルロイを語る言葉を持たない。エルロイは特別なのだ。泣きたいぐらいに特別なのだ。
一九五八年のLA。呪文のような文体のために用意された語り手はLA市警風紀班のデイヴ・クライン警部補。弁護士資格を持ち、時にマフィアの殺し屋も務める悪徳警官。
クラインは翻弄される。
まず、事件――長い間、LA市警と癒着してきた麻薬王が被害にあった、変質者の仕業と思われる押しこみ強盗。
次に、政治――州司法長官選挙を巡る候補者同士の戦いは、LA市警対連邦捜査局の形をとって、ことあるごとに衝突する。
さらに、謎――クラインの上司であるエドマンド・J・エクスリー刑事部長の不可解な指示。
そして、女――大富豪のハワード・ヒューズと愛人契約同然の契約書にサインしながら、それを無視して行動するグレンダ・ブレッドソウ。
はじめは自己保身のために、やがて、理屈では説明できない妄念に突き動かされて、クラインはそのただ中を疾走する。
その行動を、思念を、狂気にも似た情念を、エルロイは、前述した呪文のような文体で書き綴る。
呪文は呪文であるがゆえに、最初は意味を取りにくい。だが、その意味に気づいたときには遅いのだ。語り手のクライン自身が、自らが語る呪文に突き動かされるように破滅への道を転がりはじめるとき、その呪文を読んでいる読者もまた、呪文の魔力にしっかりととらわれる。
クラインが動きまわるLAの街――悪意と腐敗に覆われた街が自らの住む世界と重なり合い、溶け合っていく。それは、逃げることの叶わぬ世界だ。
ある種の人間は、エルロイの呪文に辟易(へきえき)するかもしれない。だが、別種の人間――わたしのような人間ならば、そこになにかを見いだすだろう。
エルロイは読者を選ぶ。万人に好まれる小説など、彼の目指すものではない。
血をまき散らせ――それが、彼が小説を書く理由なのだから。それが、わたしのような人間がエルロイの作品に引き込まれてしまう理由なのだから。
* * *
さらに、『ホワイト・ジャズ』。
本書は独立した物語だ。単独で読んでも十分に楽しめる。しかし、できうることならば、先行作品――『ブラック・ダリア』、『ビッグ・ノーウェア』、『LAコンフィデンシャル』を順番に読むことを薦める。その方が、『ホワイト・ジャズ』のとち狂った魔力をより堪能できるだろう。三作とも、文藝春秋より文庫で刊行されている。
* * *
エルロイはいう――人の感情にへつらうような安っぽい善良さは、最後のひとかけらまで破壊してやる。
わたしの安っぽい良心は、エルロイによって完膚なきまでに破壊された。
わたしもまた、血をまき散らしたいと思っている。