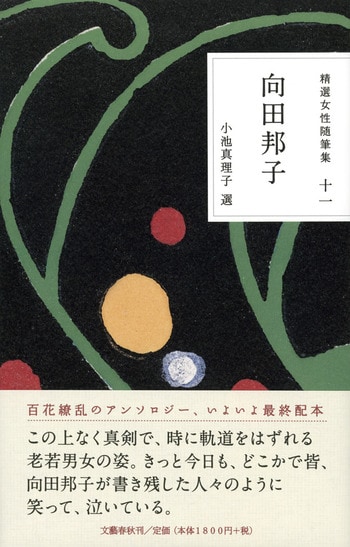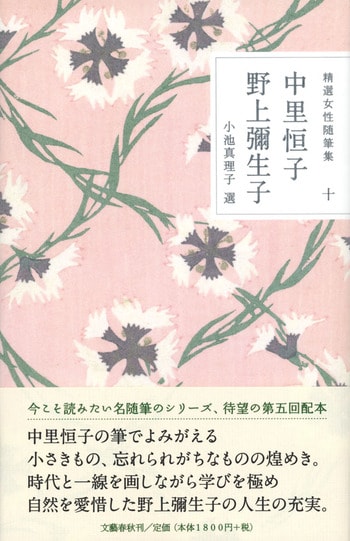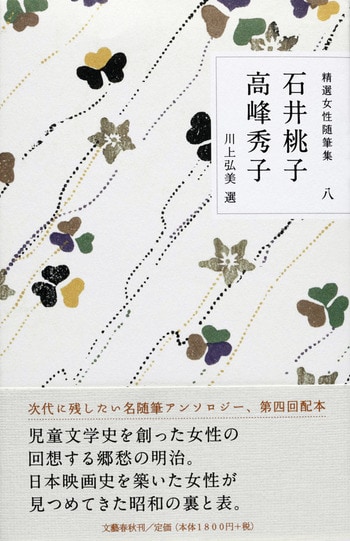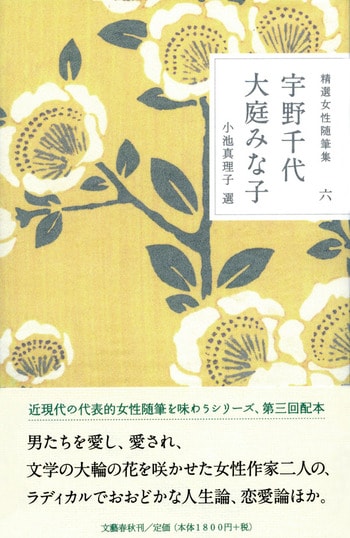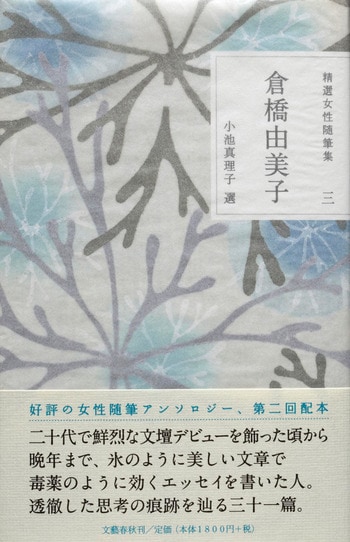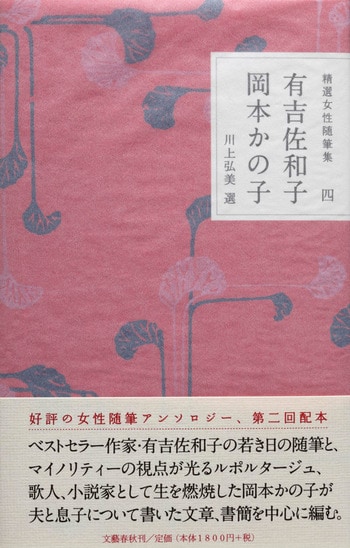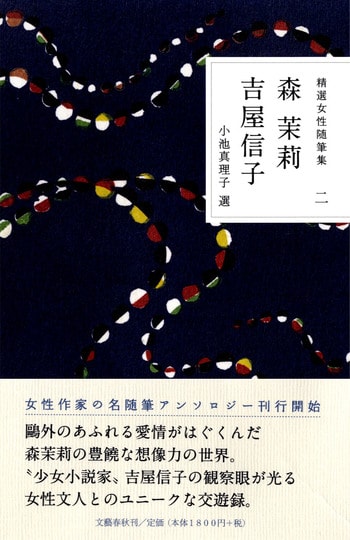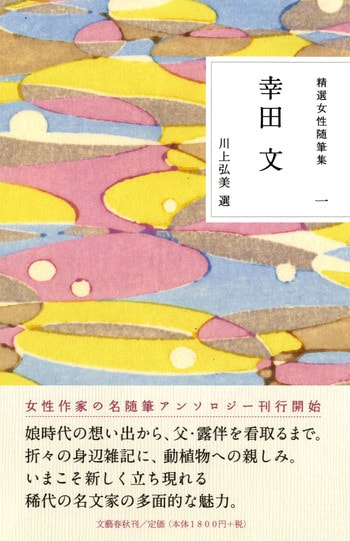『精選女性随筆集』(全十二巻)が、12月発売の『第十一巻 向田邦子』『第十二巻 石井好子/沢村貞子』で完結した。小池真理子と川上弘美という最高の選者を得て、しかも二人は編集者に頼らず、自らその作家のすべての随筆を読んで面白いものを抜き出したから極上の作品が揃った。特徴的なのは、女性作家のみならず歌手の石井好子、女優の沢村貞子や高峰秀子などの作品も収録して女性の風景を豊かにしていることだ。日頃の暮らしや生き方などが色濃く反映される随筆を編んでいるので、全十二巻には明治から平成までの女性の人生と生活の歴史がつまっていると言えよう。
と紹介をすると堅苦しいが、そうではない。むしろ逆で、正直言ってこんなに面白い叢書だとは思わなかった。少年時代から日本文学には親しんでいるので、一部の女性作家たち、すなわち幸田文、野上彌生子、岡本かの子、宇野千代、森茉莉、大庭みな子、中里恒子、倉橋由美子、向田邦子の小説は読んでいる。とくに倉橋は高校から大学にかけて熱心に読んだし、向田邦子も巧さにひかれて再読もした。ただこんなに新鮮に響くとは思わなかった。
ある対談で、小池が“驚くほど新しいのにはびっくり”といい、川上が“この叢書の作家たちはみな野蛮。恰好いい野蛮なの”と応じているが、まさにその通り。身近な所から普遍的な真理を無造作に掴みとっている。男性作家が概して政治と社会と風俗を選ぶために作品が古くさくなるのに、女性が家族や衣食住のことを丹念に描くから古びないこともあるかもしれない。
でもたとえば、新しさに関しては小池が推賞する大庭みな子の「幸福な夫婦」には驚く。“幸福な結婚とはいつでも離婚できる状態でありながら、離婚したくない状態である”、なぜなら“結婚と離婚と再婚が、大変簡単にできる世の中でも一人の男と、あるいは女とずっと結婚していたいと思うような夫婦が幸せ”だからである。“フリーセックスが日常化した状態でも、同棲していたいと思うような男女は幸せなのである”と。大庭が数10年前、旧態依然とした結婚意識が根強かった時代に書いたものだ。このラディカルさには驚く。〝ともすれば常識的になりがちな結婚観をかくも惚れ惚れするほど自由な語り口で鋭く語った女性作家を私は他に知らない”と小池がいうけれど、僕も知らない。淡々とした口調で過激なことをたくまざるユーモアを交えて鋭くシニカルに語る巧さには、本当に惚れ惚れとしてしまう。
人間くさい女性作家たち
あるいは、川上がいう野蛮。川上は幸田文を念頭において“野蛮”を使っているのだが、“どうしてこんなにいいんだろう”とほめちぎる武田百合子にもいえるだろう。『富士日記』は日記の文章だからあからさまになるのは仕方ないとはいえ、夫の武田泰淳との会話(「うんこビリビリよ」と言うと「俺は病気の女は大キライ」と言う。憎たらし)などは特にそう。一方で食事や風景を鮮やかに切り取り、さらに友人・知人の作家との交流も賑やかで同時に切ない(愛犬ポコの埋葬や作家椎名麟三を悼む「椎名さんのこと」はたまらなく哀しい)。
武田はあらゆるものを見つめ語っているのだが、それは幸田文にもいえる。とりわけ人生相談「『なやんでいます』の答え」が颯爽としている。ケチな夫や浮気性の夫をもつ妻たちの悩み、さらに太っていると嘆く15歳の少女の悩みにテキパキと明快に答えていて胸がすく。“柔軟。闊達。自由自在。たとえばそれは、ぶっ飛んだかっこよさ、という乱暴な言葉でもって、わあわあ褒めたてたくなるような文章なのだ”と川上が述べているが、“ぶっ飛んだかっこよさ”をもつ作家など、いまどこにいるだろうか。余談になるが、岡本かの子は大正から昭和にかけて夫と愛人二人と同居生活を送ったし(パリにいる息子岡本太郎にあてた真情あふれる手紙がいい)、白洲正子は自殺した銀座のママの人生を肉体交渉をもった作家たちの実名をあげて(!)回想している(洞察力に富む文章にはしみじみ感じ入ってしまう)。
小池真理子が向田邦子の魅力を、“人間らしさ”ではなく“人間くささ”にあると述べているが、それは本叢書の作家たち全てにいえることだろう。女性の権利はあまり認められず、地位は低く、社会的な制約の多い時代に生きぬいた彼女たち。悲惨な戦争を体験した作家もいて、ニヒリスティックになってもいいのに、なんと優しく逞しくほがらかであることか。生きる辛さと喜びがそのまま言葉になり、おしきせの文章ではない文体を確立した。激しい時代の荒波などない、平和で寛容な中流社会のなかで生まれ育った現代作家がもたない堅固な内面があり、親しみやすい「人間くささ」がある。その唯一の個性にふれたくて、読者は何度も読み返すことになるのではない か。