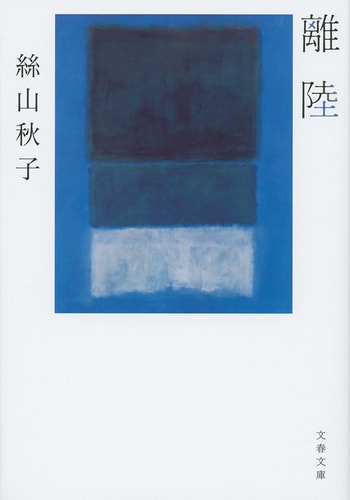「マダム・アレゴリの記録」で乃緒を彷彿とさせるマダム・アレゴリは、パレスチナでジュスティーヌという女性に拾われるのだ。そして彼女と夫・ネシム(ダレルの『アレクサンドリア四重奏』だ)の指令により、パリで亡命者の手助けをする。その中には作家セリーヌもいた。女優としての才能を存分に発揮するマダム。その正体は不明。「名前なんてないのよ。彼女に名前はない」とジュスティーヌは言う。――もし乃緒だとしたら「NO」と名乗る。佐藤はため息をつく。
この「マダム・アレゴリ」のパートにはゾクゾクさせられた。スリリングなエンタメ要素でジャンルの横断を試み、外国文学好きをニヤリとさせ、時空を歪ませ幻想の世界に誘いこむ。それまで淡々とした佐藤の時間に沿って読んでいたところに、別の時間の流れが入り込んでくる。物語がより重層化する。がぜん面白くなってくる。
思えば絲山秋子は、リアリズムとファンタジーを共存させてきた。人物が移動し、流転する作品も多くあり、漂泊というイメージがあった。今回『離陸』を読んで、あらゆる境界をフラットに捉えようとしているのではないか、と思った。
たとえば乃緒は時間も場所も行き来する。佐藤は矢木沢―パリ―東京―八代と赴任する。常にヨソモノの彼から見る風景は、矢木沢もパリも並列だ。佐藤と結婚し来日したリュシーは、赴任先で「ガイジン」という視線を想像してしまう。イルベールとフェリックスは共にフランスの海外県・マルティニーク出身だが、アイデンティティの捉え方はそれぞれ違う。視覚障害者である佐藤の妹・茜は行動的で、より広い世界へ出ようとする。
彼らを見ていると特殊な境遇とは、境界を越えようとする、もしくは否応なしに境界を越えさせられる人々だと気付く。彼らだけではない。人間はどこにでも行ける。逆に言えば、どこにでも行く可能性がある寄る辺なき存在だ。境界を越え旅するうちに、人々は交錯し、やがて別れる。
そう、佐藤は赴任する先々で友情を結ぶ一方、いくつかの別れを経験する。そして死のイメージを飛行機の離陸に重ねる。〈ぼくらは滑走路に行列をつくって並んでいる。いや、まだ駐機場にいるかもしれない。生きている者は皆、離陸を待っているのだ。〉
どこか別の旅に出るべき時を待つこと。人が人を失い、見送ること。その繰り返しが人生なのだろうか。
いくつもの移動と別れを経て、次に佐藤はどこへ行くのか。そして乃緒の行方は。わからないまま残る謎もある。しかしそれが生きているということなのかもしれない。heureuse、malheureuse、heureuseという例の呪文だって、幸福と不幸がきっぱり別なわけではなく、どこで状況が変わるか知れない。一足ずつ幸福、不幸と唱えながら歩いていくうち、気付けばそれが生きている時間になる。
いつのまにか遠くに来たと振り返れば、無情さと豊かさ、矛盾するもので満たされた私達の人生。刻まれるだけの時間、そこで誰かや何かと出会うことで生になる。生のわからなさがそのまま物語になる。このことをしばらく抱えて私は生きるだろう。