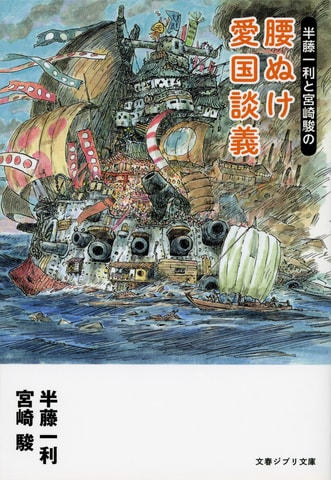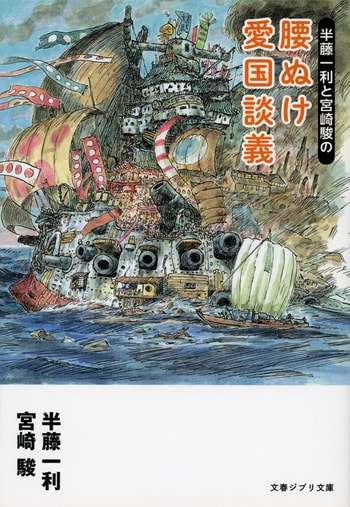『腰ぬけ愛国談義』で対談相手の半藤一利に、「監督ははじめてご自分の映画(『風立ちぬ』)を見て涙ぐまれたという噂を耳にしました。ほんとうですか」と尋ねられ、宮崎駿は答えた。
「ほんとに情けないですが、ほんとうです。ぼくは遅れてきた軍国少年でしたから、そういう心情に触れるところがあったんですね」
『風立ちぬ』といえば、世代によっては松田聖子を連想するだろう。堀辰雄を思い出す人は意外に少ないようだ。宮崎駿も『風立ちぬ』を青年期に読んだが、「なんだか全然響かなかった」。だがその後、堀辰雄の読者とは、「自分がいちばん美しかった時を、時代のせいで失ってしまった人たち」ではないか、と考えるようになった。
恋人と夏の軽井沢で出会った。しかし肺結核を病んだ恋人はやがてサナトリウムで亡くなり、青年はひとり残された。そんな小説の題名は、ヴァレリーの詩の1行「風が起こる。生きるべくつとめなければならない」からとられた。これを「風立ちぬ、いざ生きめやも」と訳したのはうまかった。
堀辰雄が矢野綾子に出会ったのは昭和八年(1933)夏である。その翌年、堀辰雄の1歳年長、30歳の堀越二郎は、三菱が社運をかけた海軍の九試(昭和9年試作)単座戦闘機の設計を任された。当時の航空機業界は、三菱、中島、川西、川崎、どの会社も若い技術者が中心だった。
9年9月、堀辰雄は23歳になる矢野綾子と婚約する。彼女は『風立ちぬ』のイメージと異なり、大柄ではっきりした性格の、成城の銀行家の娘であった。
昭和10年に堀越二郎が「進空」させた九試単戦1号機は、単葉・逆ガル型ウイングの美しい飛行機である。その年の夏、堀辰雄は病の進んだ綾子とともに、かつて自分が療養した長野県富士見高原のサナトリウムに入った。しかし12月、矢野綾子は死去する。12年、堀辰雄は軽井沢で『風立ちぬ』を書き上げる。
堀越二郎が量産型零戦の原形となる十二試艦上戦闘機の開発命令を受けた昭和12年は、モダニズムが流行し、社会に享楽的空気が満ちた昭和戦前のピークであった。
宮崎駿は「遅れてきた軍国少年」と自称。もの心のついた昭和20年代から戦記物に読みふけっていたという意味だが、当時の男の子が敗戦国日本の戦艦と戦闘機を愛したのは、それが美しかったからである。また戦後日本のありようが、コドモ心にも情けないと印象されたからである。
昭和45年に半藤一利は『太平洋戦争 日本航空戦記』という雑誌を編集した。刊行すると、そこに描かれている零戦の風防は21型のではない、ハワイ攻撃に参加していない52型のものだという読者からの抗議が、文字どおり殺到した。
そこで対談2回目に現物を持参、宮崎駿の判断をあおぐと、宮崎駿は一瞥して、こういった。「あ、これは違いますね。……52型でもないです。この風防はアメリカ軍機のカーブです」
宮崎駿の実家は航空機部品の製造工場であった。戦争末期に栃木県鹿沼へ疎開し、零戦の風防をつくりつづけた。敗色濃いにもかかわらず盛況の工場は、伯父が社長、大正3年生まれの父が工場長だった。
宮崎父は、享楽的でモダニストで刹那的、話半分というより話4分の1くらいの明朗な人だったが、それは戦前人の一典型であった。日本の前途に思い悩むことなく、ひたすら遊ぶことに熱心な20代を送ったが、学生結婚した初婚の相手を、わずか1年で肺結核で失った人でもあった。そこに堀辰雄との共通項があった。
もうひとつの戦前青年の典型は、これも国家のためではなく、ただ自分の興味のおもむくまま仕事に没頭した堀越二郎のようなタイプであった。だが天才が成果を上げられる期間は短い。せいぜい10年であろう。設計家としての堀越のピークは開戦以前にあった。
そんな、自分の父親や堀越二郎が生きた時代の横顔を、長い道のりの末にようやくえがき得たという思いが、監督をして自作に涙させたのではないかと私は思う。
『腰ぬけ愛国談義』はたんなる平和論ではない。もちろんオタク談義でもなく、昭和戦前と昭和戦後を生きたふたりの男の文明批評である。また、ゆるやかに落日してはいても、いまだ日本は世界にいるべき場所となすべき仕事を持つと示唆するという意味で、やはり「憂国」の書であろう。