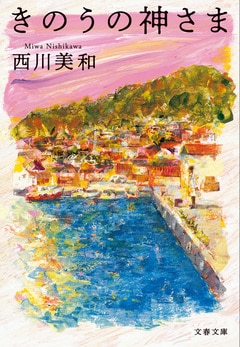ぼく
大学の時につきあった彼女は、絶頂に達する直前になると、もうやめて、と決まって言った。ぼくを鼓舞する意味の「もうやめて」ではない。ほんとにやめて、自分から身体を放してしまうのだった。
彼女はしかし、ぼくを拒絶しているつもりはないと言った。そばに寄り添い、ぼくのまだ薄かった胸に尖ったあごを乗せ、収まりのつかないあそこを片手で掴んだまま、何故もうやめなければならないのかについての長い言い訳を語って聞かせた。
「小学校の三年生の時に、お誕生日会を盛大にやったの。お母さんが腕を振るったごちそうを食べて、歌を歌ってケーキを食べて、プレゼントをもらった後に、風船割り競争をやったのね」
「風船割り競争?」
「膨らませた風船を椅子に置いて、お尻で割っては次の人のところに走って帰って来てリレーするやつよ。割れなきゃバトンタッチは出来ない。知らない?」
「いや、わかるよ。やったことはないけどね。でもそれを家の中でやるの? 誕生日会に?」
「そうよ」
「最高だね」
「ふふ。思ってないくせに」
「そんなことないよ。まあ、だがともかく、華やいでるね」
「そうね。華やいでた。でも普段私はみんなの輪の中心にいるようなタイプではなかったのよ。だけどその日ばかりはのっけから自分が主役でしょ。仲のいい女の子たちや、憎からず思っている男の子たちを片っ端から家に呼んで、大騒ぎよ。大騒ぎの絶頂よ」
「ふむ」
「二つのチームに分かれて競争して、私のチームのアンカーは当然私ね。もう一つのほうは一番仲良しのタマミちゃん。レースはものすごく競(せ)ってたの。今考えれば出来過ぎなくらい。抜いては抜かれ、追い越し追い越されをくり返してね、最後まで息もつけないアンカー勝負になったわけ。だけど私たち、二人ともどんなに乱暴にお尻で押さえても風船がなかなか割れなくて、だんだん自分でそれが可笑しくなってきて、食べたごちそう全部吐いちゃうんじゃないかと思うくらい笑っちゃって、てんでお腹に力が入らないのよ。でも負けるわけにはいかないじゃない。だって私の誕生日だもの。わあわあ友達が声援を送る中で、引きつったお腹押さえながら、必死になって、汗だくになって、やあっ、と力一杯風船の上に乗っかったわけ。そしたらよ」
「そしたら?」
「風船が割れた」
「やったじゃん」
「それと、お隣のお家が、燃えたの」
「何?」
彼女の言うところによれば、彼女とタマミちゃんとが風船の上でお尻をぐにぐに動かしている頃、ちょうど隣で夕食の支度を始めた主婦の天ぷら鍋に火がついたのだそうだ。風船が割れるや否や、隣の騒ぎを聞きつけた母親が、逃げなさい! と金切り声をあげて踏み込んで来た。彼女の家族も子供たちも全員無事家の外に退避、隣の火事も、ボヤ程度で消し止められたが、誕生日会はそれにて解散。あれだけの興奮を見た彼女の風船割りの結果には、喜ぶ者も悲しむ者も無きままに終わった。よりによって、なんで今日。なんで今なのよ。と彼女は隣の主婦の不注意を呪ったが、その体験が人生に深く影響を及ぼしたことを知るのは、セックスを経験するようになってから、厳密には絶頂の感覚を覚えるようになってからのことであった。あとちょっとでいちばんいい時が来る、という段になると、どこからともなくあのパーティの席に母親が出していたポップコーンの匂いが鼻の奥に蘇るとともに言い得ぬ不安がよぎり、いつも、どんな相手とも、直前に「もうやめて」しまうようになったのだと言う。
「さっきもポップコーンの匂いが?」
「ええ。していたわ」
「ぼくにはまったく」
「いいのよ。悲しい匂いだもの」
彼女はひとり世界の不幸を背負ったような物言いになった。
「このまま突き進んだら、またどこかで私が絶対に予測できないようなひどいことが起る気がして、たまらなくなるのよ。調子に乗って、たがが外れて気持ちよくなって、我を忘れたとたんにね。だから怖くて、とても先へは行けなくなってしまうの。どんなに行きたくてもね。私って、自制心の奴隷なのよ」と最後は自分を哀れむようにほろりと涙を流したりしてみせた。
実に納得いかないが、その言い訳を、ぼくは彼女と寝た後にはどんなにへとへとでも満たされていなくても、必ず聞かなくてはならなかった。それは儀式のように繰り返され、時にはセックスをしている時間そのものよりもずっと長かった。おばあちゃんの昔話を聞くように、毎回異なる展開をしたり、新しいディテイルが加わったり、隣の主婦が揚げているのがコロッケになったり唐揚げになったり、それは彼女なりの創意工夫だったのかもしれないが、かと言って若かったぼくがそんなもので満足するはずはなかった。ぼくは「成功体験の重要さ」について彼女に語るべきだったのかもしれない。「恐怖に抗ってともに到達し、そしてひとたび周囲の安全確認さえ出来れば、もうポップコーンの匂いともお別れだよ」と、言えば良かった。「ひとりじゃないさ、ぼくがついてる」とか。でもそんなことを言えるほど自信が持てなかった。もしかしたら彼女は、長い長い言い訳をして、ぼくという男への退屈を取り繕ってくれているのかもしれないという疑惑が、どうしても拭えなかったからだ。半年も過ぎると、どちらからともなく別れを切り出して、彼女がぼくのもとを去る日がやって来た。うちに置いていたほんの少しの下着や化粧道具を片付けているその背中に向かって、ひょっとしてセックスの動作が風船の上に乗っていた時の感覚と似ているのかと尋ねてみたが、それは関係ないんじゃん、と彼女は振り返りもせずに答えた。
長くそのことも忘れていた。彼女は今でも絶頂に達することを自らに禁じているだろうか。仮にそれが少なからぬ不幸だとしても、その掟に従い続けた彼女の人生は、いちばん良くないことが、いちばん良くないタイミングで起るような最悪の不幸には見舞われていないのではないか、と今は思う。ぼくは彼女の話をあれだけ何度も聞かされながら、何も聞いてはいなかった。その後もずっと、気持ちがよくなればたがが外れたようにお尻の下の風船を割りつづけたのである。あのとき彼女の話を一つの箴言(しんげん)として、ぼくが襟を正していたらどうなっていただろう。それともあの言い訳は、やっぱりぼくの寝技のお粗末さに対する回りくどい思いやりだったのか。彼女が今もぼくの友達でいたならば、いずれにしても君は正しかった、と伝えたいが、もう顔すらほとんど忘れてしまった。
衣笠幸夫(きぬがささちお)は、父を恨んでいた。
彼が生まれたのは、広島東洋カープの衣笠祥雄(きぬがささちお)選手が一軍昇格を果たすすこし前のことである。父・衣笠忠郎(ただお)は、幸夫出生の折にはまだ氏の存在を知らなかったし、また、まさか我が子と偶然同じ響きの名を持つ人物がのちに連続試合出場数において球界の世界記録を塗り替えるような偉業を達成し、国民栄誉賞受賞者にまでなろうとは夢にも思わなかったのだと再三弁明を繰り返したが、息子は決して理解しようとはしなかった。
一九七〇年代中盤以降、衣笠幸夫が小学校に上がろうとする頃から、セントラル・リーグにおける赤ヘル軍団の躍進は飛ぶ鳥を落とす勢いとなり、球団史上の黄金期を迎えるとともに、クリンナップを務める衣笠選手の強烈な個性とその存在を知らない者はなくなった。
「キヌガサ・サチオ君」とそのフルネームを教師に呼ばれる度に、クラス全員が幸夫の困惑を確認しようと一斉に振り返る日々が始まった。病院の待合室や、卒業式や、分別のある大人も交じっている場所でさえ、その名が呼ばれると一瞬にして場が聞き耳を立て、立ち上がる幸夫の姿が目で追われ、やがて押し殺すような笑い声が漏れるのであった。
思春期にさしかかって、なおも盛んに我が名への不服を言い続ける息子に、父も随分手を焼かされた。
「衣笠選手は立派な人だぞ。世の中にはもっとどうしようもない、二流、三流のヘボ選手と同姓同名の人たちだっているんだ。それに比べればお前は断然恵まれている」
「何だその理屈」
「だいたい名前を言えば、人に一発で覚えられるだろ」
「だからそれが嫌なんだよ」
「ばかだな。そういうことが社会に出てからは案外とでかいんだよ。お父さんなんて、カープの衣笠選手と同じキヌガサです、って取引先には自分から言っちゃうぞ。そしたら、おお、鉄人か、頑張れよ、なんてことになる、その場も和む」
「しょっちゅう熱出して会社休むくせに。大体お前は“サチオ”じゃねえだろ。俺の気持ちがわかってたまるか」
「お前とは何だ、親に向かって」
いっそ父が熱狂的なカープファンで、とりわけ衣笠選手の大ファンで、氏のように強靱な精神を持ち、真摯な努力を重ねる人間になってほしかった、それを望んでその名を付けた、といういきさつだったなら、まだ納得のしようがあったのに、と幸夫は思った。
幸夫は野球には決して手を出そうとしなかった。自分が自分である前に、誰の目にもキヌガササチオとして認識されることにおびえていたのだ。才人と同じ名前をもつ限り、ひょっとすると似たような能力を発揮するのではないかという周囲の無根拠な期待に抵抗するには、バットを握ることを拒絶し続ける以外に無いと信じていた。もとより体力に自信がある方ではなかったし、とにかく一度でもバットを振れば、それがどんなにお粗末なスウィングだろうと、あるいは豪快なフルスウィングだろうと、一振り目から衣笠祥雄選手のスウィングと比べてどうかという目でしか見られないのであり、幸夫自身のスウィングとしては、誰もみとめてくれはしないだろうと恐れたからである。
また、これも皮肉なことだが、母親譲りの幸夫少年の肌は心もとないほどに色白で、さらさらと揺れる淡い色の髪の毛の隙間からのぞく切れ長の目は、少女たちの好む恋愛漫画の恋人役さながらに繊細で、その風貌は、「鉄人・衣笠」の全身から醸し出されるコクのある野性味や人懐っこい愛嬌とは似ても似つかず、いたずらな冷やかしの対象にすらならないことが却って周囲をしらけさせた。
同じクラスに伊刈靖(いかりやすし)君という珍しい名前の少年がおり、彼はその名前と、ふてぶてしく下唇がぽってり突き出しているという特徴から、ザ・ドリフターズのリーダーを想起させ、「いかりや」「長さん」などとあだ名されてさかんにからかわれた。が、それに対してもさして動じぬ伊刈君の表情とその態度は、ますます本物のその人を彷彿とさせ、たまにからかいに応じて本人自ら「おいーっす」などと返そうものなら、それこそ伝家の宝刀抜かれつ、とばかりに喝采が浴びせられた。実際の風貌はそこまで酷似してはいないのに、そうされるとふしぎに瓜二つのようにも見えてきて、少年少女は腹をよじらせて喜んだ。伊刈君の風貌と器量は、じきにからかう側の好奇心をそのまま親近感と人望に変えてしまい、「長さん」と呼ばれ続けながら、いつのまにか本物さながらの飄々たる長老感と統率力を発揮するに至った。
幸夫は伊刈君の存在に嫉妬した。いっそ伊刈君のように、自分も人に笑ってもらえるような気楽な存在になりたいと思った。いちど笑えない存在となると、人間は笑ってもらうための糸口をどんなにもがいても見つけ出せなくなる。もがけばもがくほど泥沼にはまり、笑えないことがせめて敵意にまでは育たぬようにと相手の顔色をうかがい続けるしかない息苦しい日常が続いて行く。しかしそれもこれも、自らのこの女好きする、潤んだような顔かたちのせいか、それとも父がつけた名のせいか、と考えれば、憎いのはまぎれもなくその名の方であった。幸夫はちっとも自分の容姿が嫌いではなかった。
子供時代が終わってからも、幸夫が野球に興味を持つことはなかったが、大学を卒業して会社勤めをしていた頃、たまたま定食屋でついていたテレビの野球中継の実況アナウンサーがその名を呼び、すでに球界を引退した衣笠氏のおだやかな解説の声を耳にした時、ふと思った。もしも少年のころに衣笠選手と直接出会うことがあったなら、きっと衣笠選手は自分に野球を勧めていたのではないか。いいからとにかく、君は野球をやってみなさいと。最初の一振り、最初の一撃、最初の走塁、最初の守備、最初のエラー、すべてを衣笠選手と比較され、重ねられ、笑われたとしても、やってみれば、やって行けば、じきに幸夫には幸夫にしかないプレースタイルが培われ、衣笠祥雄と衣笠幸夫は、それぞれ別個のプレーヤーであるということを、誰もが認めざるを得なくなる日が来ただろう。そして幸夫は、キヌガササチオという名前から自由になれたかもしれない。
少年時代に衣笠選手との邂逅(かいこう)を得られなかった衣笠幸夫が作家という職業を選択したのは、ひょっとして、この名前を捨てるためであったのか。彼は「津村啓(つむらけい)」というペンネームを持った。作家・津村啓はそのデビュー以来、自分の本名をごく親しい仕事相手にすら明かしたことはなかった。
*
津村啓の本名を知る人間のうち、昔も今も、そう距離を変えずにつき合い続けている者を挙げるとするならば、彼の妻をおいて他にないだろう。彼らは大学入学後、同じ語学のクラスで顔見知りになったが、後期の授業が始まってまもなく彼女は姿を見せなくなり、どうやら大学を辞めたそうだという噂を聞いて、それきりになってしまった。彼女は十九歳、大学受験の折に二年浪人を重ねた幸夫は二十一歳の頃であった。
三年後の初夏、大学四年生になった幸夫は、就職活動の会社面接が一つ終わった帰り道、伸びすぎた髪を切ろうと通りがかりの美容室に飛び込んだ。鳶(とび)色の髪の若い美容師にシャンプー台に連れて行かれ、首にケープを巻かれた時にお互いに気がついた。
衣笠君、と彼女はすぐに幸夫の姓を呼んだが、幸夫は、歓声を上げて偶然の再会を喜ぶふりをしつつも、目の前の彼女が一体誰ちゃんだったか、その名がさっぱり記憶から抜け落ちて、うろたえるばかりだった。
彼女は大学を去った後、一年ほど美容学校へ通い、資格も取得したのだと言った。
「自分で決めたの?」
「他に誰が決めるの」
仰向けに寝た幸夫の顔に乗せられたタオルに、ふっ、と彼女の吹き出した温かい息がかかった。
「ずっと憧れてたのよ。子供の頃から人の頭をいじるのが好きで仕方なかったの。父が亡くなってしばらく大学を休んでるうちに、気持ちが決まったんだ」
それを聞いて幸夫は、彼女が大学に来なくなったきっかけが父親の病死であったことをようやく思い出した。
冒頭部分を抜粋