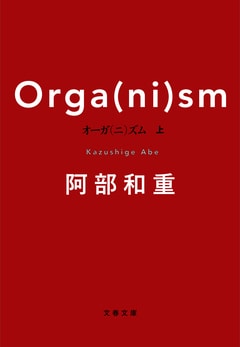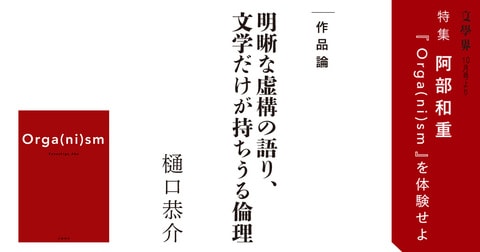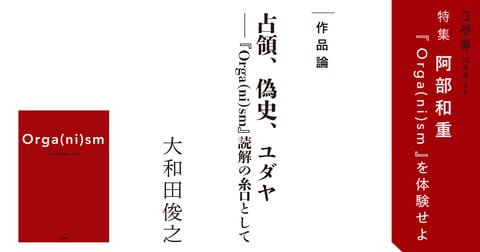――「アメリカの夜」で群像新人文学賞を受賞されたのが「群像」一九九四年六月号ですから、作家としてデビューされて丸十年ですね。十年目にして初めて映画評論集を刊行するというのは意外な気もします。
阿部 正直に言うと、僕は映画に対しては非常にアンビバレントな感情があるんです。映画というものがなければ、僕は多分小説家になっていなかっただろうと思います。映画学校に入って映画について学ばなければ、文学に対しても関心は湧かなかったかもしれない。他方で、作家としてデビューしてからは、映画についての原稿を書くことがある時期からだんだん苦痛になり始めたんです。
――映画を仕事として観て書くということがですか。
阿部 小説家としてデビューしたわけだから、まずは小説をきちんと書かなければ、という気持ちがあるわけです。でも、映画評論の連載などをやっていると、やはりそれなりに作品を観ておかなければならない。それに、一応映画学校の出身ということもありますし、映画監督の青山真治さんや黒沢清さんなど、現場で実際に仕事をしている方々と知り合ったりすると、こちらもぬるい仕事はできないわけです。そうすると、映画の方の仕事に時間をかなり割かなければならない、でも、小説も書かなければ……(笑)というジレンマですね。
――『映画覚書 vol.1』は五百頁を超す超大作です。収録されているのは九〇年代後半から現在の評論が中心ですが、あらためて読み返してみてどのような感想を持たれましたか。
阿部 基本的には僕自身の考えは変わっていないんだな、というふうに感じました。とりわけ今回収録された原稿は、僕なりの問題意識が明確に固まってからのものなので。もちろん映画自体が変化していっている面というのはあります。
――例えば、九〇年代以降のアメリカ映画に起こっている現象を非常に的確に捉えて提示しているという印象があります。

阿部 九〇年代以降は映像技術がどんどん発達するに従って、機能重視の傾向が顕著になりました。新しい技術や機械が開発されると、人はその性能を試してみたくなるじゃないですか。機能を試すということの方が前提になって、物語はそれに従属する形になるわけです。ジャンルとしてはファンタジーが増えましたね。『ハリー・ポッター』や『ロード・オブ・ザ・リング』のシリーズはまさにそれです。あるいは、歴史劇や史実の映画化も多くなりました。過去の物語をかりながら、今の技術で過去の出来事を再現しようという試みです。今ではない、見えていない部分を描いた方が新技術を試せるし、映像表現としても斬新だということでしょうね。
一方で、デジタル技術とは別の形でリアリティを追究しようとする疑似ドキュメンタリーという手法の映画も一つの傾向となってきました。
――阿部さんは否定的な立場をとっていますね。
阿部 映像の詐術の一つとしてそういう手法が蔓延してしまったと捉えていますね。それは映画に限らずテレビでも言えることです。『電波少年』という番組は、疑似ドキュメンタリーだったと思うんですよ。旅をしていく過程をカメラが常に追って、一つのドキュメンタリーではあるんですが、完全にやらせがないかというと、もちろんそうではない。
手持ちカメラで動き回りながら対象を追って、映像を見せれば、安っぽい話でもリアルに見えるだろうということで、九〇年代以降の疑似ドキュメンタリーはそのスタイルをとってしまったというふうに僕は見ているんです。
――『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』なんかはそれで非常に話題になりましたね。
阿部 もうまさに疑似ドキュメンタリーです。『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』は、よく言われている通り、完全に『食人族』という七〇年代後半の作品の反復であり、再現に過ぎません。インターネットを介して口コミで広がったという点に関しては新しい要素といえるかもしれませんが。
――技術重視と物語性の退廃という九〇年代以降の傾向の中で、スピルバーグ監督に関しては「最も輝かしい」仕事をしていると評価されていますね。
阿部 スピルバーグの場合は、映像表現と物語性の面のバランスが非常によくとれているんですね。というのも、彼はもともと新技術をいろいろな形で逸早(いちはや)く取り入れながら撮ってきた人だったから、九〇年代以降のデジタル技術にも安易に飛びつかなかったんです。やはり物語性の工夫は確保しなければならないだろうと。さらに、彼がすごいのは、一つの作品によって一つの物語を語るだけでなく、全く別の作品でも、それを重なり合わせることによって一つの新しい物語が見えるというような仕組みを考え出して実践していることです。
――具体的な作品を挙げると?
阿部 最も最近の作品でいえば、『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』と『マイノリティ・リポート』です。この二作品は実は同年(二〇〇二年)に発表されているんですよ。今となっては同年に二作を発表すること自体が珍しいことです。前者は六〇年代を舞台にした実話の映画化、後者は近未来SFサスペンスで、見た目は全然違う内容の作品です。しかし物語に着目してみると、どちらも父と子という親子間のドラマを撮っているんですね。しかも『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』は父を失った子が主人公であるのに対し、『マイノリティ・リポート』は子を失った父が主人公になっています。そして、話が進展していく中で疑似的な父という存在が現れ、その関係性が描かれて終わるという、ちょうどコインの表裏のような仕掛けになっているんです。
――目からうろこですね。
阿部 さらにこの二作だけでなく、他の作品も同様につながっているんです。例えば二〇〇一年に発表された『 A. I.』と『ジュラシック・パーク3』(製作総指揮)も親子間のドラマを描いたものであり、先ほどと同じ構造になっている(編集部注・詳しくは『映画覚書 vol.1』の「映画覚書(10)」の項参照)。こんなことをやっている人は他にいないし、逆にスピルバーグだからこそできるんだと思います。
――この本の中には中原昌也氏、蓮實重彦氏との対談も収録されています。特に中原氏との対談はまさに9・11テロの翌日に決行されました。
阿部 なんでずらしてくれなかったのか。
――これは偶然以外の何ものでもなかったわけですが……。9・11がハリウッド映画に与えた影響についてはどのようにお考えですか。
阿部 その影響というのは、実はまだはっきりとした形で出ていないのではないかと僕は思っています。ただ、ビルの倒壊を描く映画は少なくなったかもしれません。
――9・11以降では『ギャング・オブ・ニューヨーク』が興味深かったですね。スコセッシ監督の一種の批判が感じとれるような気がします。
阿部 そうなのですが、あの映画は捉えるのが非常に難しい。9・11の後に発表されて、観てみると、確かに9・11に対する批評なのかもしれないという面はあるわけです。ただ、あの作品が製作されていたのが実は9・11前だったということを念頭において観ると、一体何なのだろうなという不思議な気持ちになってしまう。その辺が僕はちょっと引っかかるわけです。テロリストたちが『ギャング・オブ・ニューヨーク』の企画を知っていたわけでもないし、スコセッシがテロの計画を知ってたわけもない。でも、同時代的なある種の流れが見事につながりすぎてしまったな、と感じるんです。
――本業の小説の方の話も映画とからめて少しおうかがいします。昨年刊行された『シンセミア』の中では盗撮集団の話が出てきて、読者はそのシーンをいわば覗き見ている。さらにその自分を、誰か、もしかしたら著者である阿部さんに見られているような感覚に陥るわけです。これは映画的なカメラの視点を小説にも採りいれているということでしょうか。
阿部 いまおっしゃったことで言えば、その視点というのは、カメラではなく、映写技師の視点なんだと思うんですよ。つまりスクリーン上で展開するイメージがあって、それを観る観客がいる。そしてそれを上から見下ろしている映写技師がいて、スクリーン上のイメージと観客の両方を見ているわけです。この視点は『インディヴィジュアル・プロジェクション』でも一つの主題だったことで、僕はこういう構造をよく小説の中で使っているといえるかもしれません。
――文体に関しては、映画批評と小説でご自分の中で使い分けていますか。
阿部 映画批評で心がけているのは、作品を観ていない人が読んでも何が書いてあるのかがわかる文章でなければならないということです。説明性を重視しているわけで、その影響は小説にも現れていると思います。また僕が映画批評に書いていることは、実は僕の小説の種明かしになっていることが多いはずです。だから『シンセミア』と『映画覚書 vol.1』を一緒に読めば、いろんな面でつながるはずなんです。
――小説を書いている時に映画を観て、「あ、これはやられたな」というようなことを感じることはありますか。
阿部 書き終わったあとに似たような映画が出てきて困ってしまうことはありましたね。『インディヴィジュアル・プロジェクション』のあとの『ファイト・クラブ』はまさにそう。また『シンセミア』では、『ミスティック・リバー』や『ドッグヴィル』なんかがそうですね。何でこんなに似たものが出てきてしまうんだろう、と。
――将来的には、映画を撮りたいという気持ちはありますか。
阿部 歳をとってからでも構わないけど、いずれはという気持ちはもちろん持ち続けています。ただ、自分の脚本や原作でなければというこだわりは全然ありません。小説は小説として自分の中で完結しているわけですから。でも、一方で『ファイト・クラブ』なんかを観てしまうと、何だかな、という複雑な気分にはなりますね(笑)。