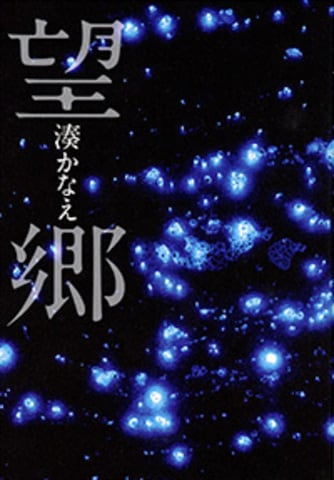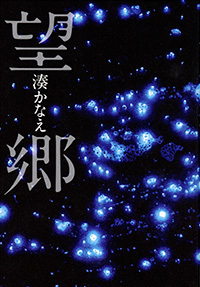
『望郷』は瀬戸内海に浮かぶ白綱島(しらつなじま)を舞台にした連作短篇集だ。同じ島で生まれ育った六人の男女を語り手に「そもそも、故郷とはいったい何なのだろう」と問いかける。黒地に青白い光が浮かび上がる表紙は、第六十五回日本推理作家協会賞(短編部門)を受賞した「海の星」をイメージしたものだろう。
「海の星」は、東京に住む会社員の浜崎が、アクアパッツァを食べている場面から始まる。魚介類を香草とスープで煮込んだ料理だが、その日の具材は息子が釣ってきた小アジだった。白綱島出身の浜崎には馴染みのある魚だ。〈洒落た名前の料理に姿をかえようとも、鬱陶しい小骨の感触は変わらない〉と気づいた瞬間、島での生活が蘇る。
煙草を買ってくると言って出かけたまま失踪した父、父が生きていると信じて毎夜探し歩いていた母、苦しい家計を助けようと釣りを始めた自分、魚をくれたダミ声のおっさん……。母子は親切なおっさんとなぜ決別したのか。浜崎にとって故郷とは、喉に引っかかっている鬱陶しい小骨だ。その小骨が、おっさんの娘と再会してとれるまでを描く。抑制のきいた語り、「海の星」があらわれるシーンの鮮やかさ、過去の謎を解きつつも読者の想像の余地を残したラスト。高評価も頷ける一篇だ。
二十五年ぶりに帰ってきた姉を複雑な想いで見つめる妹、「屋敷の奥さま」と呼ばれる祖母に抑圧されてきた孫娘、人気歌手になったために地元の人々の理不尽な要求に振り回される青年、不登校になった娘を連れて引っ越してきた主婦、いじめ問題に悩む小学校教師。島から出て行った人も、とどまった人も、本書の登場人物はみんな、故郷になんらかの形で縛られ、自由になりたいともがいている。しかし、逃れられない。そこに自分と繋がった人がいるかぎり、どこまでも故郷は追いかけてくる。実に厄介だ。その厄介さを、本土と白い吊り橋でつながれても都市との格差が埋まらず、主要産業を失い、寂れていく島の風景と共に照らしだす。
ただ、本書は単なる田舎ルサンチマン小説にはなっていない。後半の三篇を読んで確信した。犯罪者の子と蔑まれてきたヒロタカにとっての「雲の糸」、友達がいない千晶にとっての「石の十字架」、教師として無力感にさいなまれる航(わたる)にとっての「光の航路」のような、想像の翼を広げるよすがになるものがあれば、遠くに行けなくても心は解放される。一度解放されて、振り返ったとき、故郷の美しさや愛おしさも見えてくるのだ。