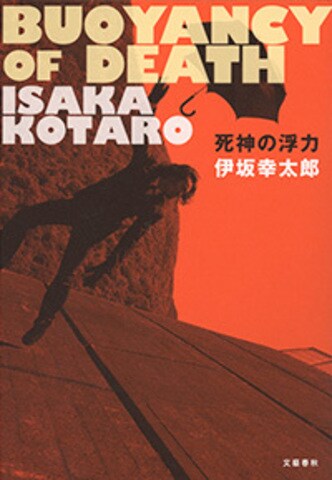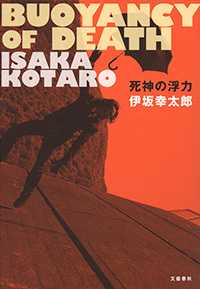
あの死神が帰ってきた。
『死神の精度』から八年、今回は長編での登場だ。
物語は、少女殺害事件の犯人とされた本城が証拠不十分により一審で無罪判決を受けた場面から始まる。
被害者の両親である山野辺夫妻は、本城が犯人であることを知っており、娘の仇を討つ決心をしていた。無罪判決により、むしろ山野辺にとって復讐のチャンスが与えられたのである。
そこに夫妻の夫の方――山野辺遼を訪ねてきたのが死神の千葉だ。
千葉の仕事は、死ぬ予定の人間を七日間調査し、その死が「可」か「見送り」かの判断をすること。
つまりここに千葉が登場したということは、山野辺遼は八日後には死ぬ運命にあるということだ。娘を殺され、犯人は無罪。その犯人に死神がつくならまだしも、遺族につく。この導入からして残酷だ。
けれど伊坂幸太郎の文体はその残酷さを覆い隠す。飄々とした登場人物、すっとぼけた会話。思わず笑ってしまう雑学や、メモっておきたい箴言などなど、読み心地の良さが読者を魅了して、残酷な設定を和らげるのだ。伊坂作品を読む楽しみのひとつは、間違いなくこの文体にある。
たとえば本書の構造は、手に汗握るサスペンスのそれだ。万全の準備をして本城を追い、復讐を遂げようとする山野辺夫妻。一方の本城は良心を持たないサイコパス。逆転に次ぐ逆転、タイムリミット。七日間の濃密なチェイス。
ところがそこに千葉が加わることで、ふっと何かが緩む瞬間が、登場人物にも読者にも訪れる。そのサスペンスフルなのにユーモラスという独特な緩急こそが伊坂小説の持ち味だ。
しかし残酷さは覆われ和らげられるだけで、確固として存在している。意外な展開、思いも寄らぬ結末など、本書が極上のエンターテインメントであることに間違いはないが、その向こうには、「死はこちらの都合など構ってくれない」という厳然たる事実がある。
フィクションでの死は、ドラマの展開に適したタイミングでもたらされるが、現実はそうではない。突然の災害や事故で、命はあっけなく断ち切られる。本書はその現実を描いている。
誰も悪くないのに自然の暴力で何の前触れもなく奪われた多くの命を、私たちは何度も目の当たりにしてきた。明日の予定も、周囲の思いも、もちろん本人の都合も一切忖度(そんたく)されず突然訪れる死。何が起きるかわからない。それが現実だ。千葉はその象徴なのだ。
本書はファンタジーの衣を着た、極めてリアルな死の物語なのである。