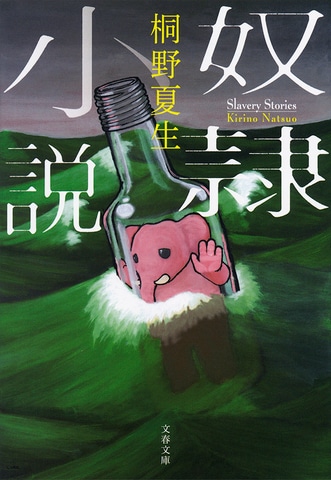桐野夏生氏の作品を読む度に思うことがある。多くの識者がすでに指摘していることであるが、平成の世にプロレタリア文学があるとすれば、それは桐野氏の作品群ではないのか、と。もちろんそれは、内からは「党派性と芸術性」という不毛な二項対立に引き裂かれ、外からは直接的な政治暴力によって抑圧され潰えていった文学史上のそれとは異なる。しかし、現代作家のうち、桐野氏こそ「階級」に、「搾取」に、より一般的な言い方をすれば「構造的な支配」に、最も強くこだわっている書き手ではないだろうか、と私は思うのである。
かつ、『OUT』や『メタボラ』といった重厚な長編作品において典型的だが、「支配」の問題系は、多層的に構成されている。「資本と労働」、「親と子」、「男と女」、「美女と醜女」、「日本人と外国人労働者」、「本土と沖縄」、「沖縄本島と離島」、「カネを貸した者と借りた者」、「異性愛者と同性愛者」といった具合にである。こうした複数の支配・被支配の構造を生きる人間が、支配のもたらす軋轢のなかで呻吟しもがくさまを、桐野氏は残酷なまでに精緻に描き出す。その筆の圧倒的な力は、読者をグイグイと引き込まずにはいない。
そうした地獄めぐりの絵巻に時代性を刻印する役割を果たしているのは、「家庭の崩壊」という主題である。戦前のプロレタリア文学が「自らを縛る鉄鎖以外には失うべきものを何も持たない」階級を人類史の担い手として登場させた文学であったのとは対照的に、桐野氏の作品世界に登場する「崩壊した家庭」は、中流階級にしばしば属する。その構成員たちは、安定した収入をもたらす仕事、持ち家、子供への高等教育といった、戦後日本の「一億総中流」社会において広く行き渡ったものを得ているか、あるいは当然手に入れるはずであると心得ており、それらが家庭に幸福をもたらすものであると信じている。
しかし、かかる信仰こそ、平成の時代において無残なまでに破壊されたものだった。「失うもの」を持った中流階級――それは20世紀後半において、旺盛な消費によって経済成長の推進力であり、生活保守主義に基づく穏健さによって安定した民主政治の担い手であると褒めそやされた、あたかも人類史の担い手であるかのごとくに――が、いったん持ったものを手放さざるを得なくなれば、いかに脆い存在にすぎないか。そして、それら中流階級の標たるものが家庭に幸福をもたらすという観念が空疎な思い込みにすぎず、その幻想を無理にでも維持しようとすれば、人々がいかにますます深く泥沼にはまり込んでしまうものであるか。この残酷な事実を、桐野氏はあくことなく読者に突きつけてきた。
しかも、没落する中流階級がプチブルの虚飾を捨て去れば「素朴な民衆の貧しいけれども幸福な生活」へと戻れるのかといえば、そんなことはもはやできはしない。中流階級からの下方離脱は下流化を意味するだけであり、戻るべき故郷など存在しないという事実を、下流家庭のこれまた荒涼たる有様を執拗に描き出すことによって、桐野氏は読者に告げる。詩人の谷川雁は、中流階級について1984年にこう警鐘を鳴らしていた。「古典的な労働者でも農民でもなくなったかれらが、さりとて市民でもないとしたら、いったい、何者なのか。私はそれを一種の難民と呼びたい。この列島の現代社会で、落ち着く先をもたず漂い続けるボートピープル。過重なローンを背負ったマイホームもまた、漂うボートにすぎまい」(「“あってはならない”産業の闇を凝視せよ」)。桐野氏の作品世界――それは平成の世相そのものなのだが――は、豊かになることによって「何者でもなくなってしまった」人々が、豊かさを失ったことによって、あるいは失うかもしれないという不安によって、お互いを傷つけ合う場所なのである。そこにおいて、重層的な支配の構造は、人々を際限なき悪意の相互投射へと駆り立て、人間をあらゆる偽善と自己欺瞞から切り離された剝き出しの存在として露出させずにはおかない。
さて、本作『奴隷小説』は、そのタイトルからして、桐野文学の主題である「支配」の構造の最も純粋化された形態を追究するものであると見ることができよう。短編集である本作で描かれる「奴隷」の姿は多種多様であり、それによってこの世の奴隷的支配の形態の多様性を表現するのである。
「雀」や「山羊の目は空を青く映すか」は、場所も時間も特定しがたい寓話的世界を舞台としている。前者では、迷信によって覆われた部族支配の村で、女たちが徹底的な奴隷状態に置かれている。後者は、どこかの全体主義国家における強制(矯正)収容所のような場所をモチーフとしているようにも感じさせるが、定かではない。いずれの世界も、理不尽な剝き出しの暴力によって支配された空間として描かれている。
同様に、「泥」という作品も直接的な暴力による人間の奴隷化の瞬間をとらえているが、こちらは、寓話的雰囲気を醸し出しながらも、2014年4月にナイジェリアで発生した、イスラム過激派集団、ボコ・ハラムによる生徒拉致事件という現実の出来事からモチーフを得ていると私は受け取った。この事件では、200名以上の女子生徒が拉致され、現在でも100名を超える被害者が未解放の状況にある。だから、この作品の世界は寓話ではない。この世界でいま現実に吹き荒れている狂気の実像に、桐野氏は迫ろうとしている。
文字通りの奴隷状態を描き出しているもうひとつの作品が、「告白」である。モチーフとなっているのは、戦国時代末期から織豊政権時代にかけての日本を舞台とした人身売買(奴隷貿易)である。フランシスコ・ザビエルの来日以降、キリスト教の布教と並行しつつ、どのようなかたちで当時の日本人が人身売買の対象となっていったのかについては、歴史の知られざる一面として現在では注目を浴びているテーマである。豊臣秀吉によるバテレン追放令から徳川幕府によって鎖国政策が採用されるに至る際に、ヨーロッパ勢力による日本人の奴隷としての輸出を禁ずることが、重要な動機のひとつであったであろうことは、今日有力な説となりつつあると思われる。
近世日本の権力が外国との交流を厳しく制限したことは、その後の日本文化と日本人の精神、ひいては日本文明のあり方の総体に対して重大な影響を及ぼした。幕末期になって覚醒され、近代的ナショナリズムへと編成されていった日本人の民族的一体性の意識は、近世社会においてすでにその潜在的な基盤が育まれていたはずなのだが、そのことと為政者による日本人の奴隷化の禁止がどう関係していたのかは、実に興味深い問題である。また逆に、「歴史のイフ」の想定、すなわち近世日本の権力者が奴隷貿易を許容し、海洋国家的発展を指向していたならば、「告白」に描かれた人々は数を増し、それら異郷の地で隷属にあえぎながらしかし生きる手段を求めたであろう人々が、どんな「日本民族」を、どんな「日本文明」をつくったであろうかということを、想像してみることも興味深い。そしてこうした反実仮想は、産業の崩壊が進み、経済的優位を決定的に失うなかで、海外出稼ぎや経済移民を強いられることになるかもしれない今後の日本人の運命を考える際に、示唆を与えるものとなるであろう。
近代日本史の全体を見渡してみれば、「外国人労働者を受け入れるか否か」を議論している昨今の日本は、例外的な時代を生きているというべきであって、南北アメリカに大量の移民を送り出し、凍てついた満州に開拓団を送り出していた時代においては、「食えない日本人が外国に出て行く」ことが当たり前に行なわれていた。そんな時代の炭鉱労働村を舞台とするのが「ただセックスがしたいだけ」である。奴隷的な労働環境に置かれた者は、自らの欲望の奴隷となり、そのために破滅する。
以上のように、ほとんどの作品が直接的な奴隷状態を描き出しているのに対して、異色のアプローチを採っているのが「神様男」であり、現代日本の田舎の母子家庭を舞台としている。二人の娘のうちの長女はアイドルになるために東京へ出て、母が必死に貯めたカネを食い潰して修行するが、芽は出ない。器量も要領も長女に勝っている次女は、成功しそうにない姉を冷ややかに見つつ、自分もアイドルになることを夢見る。母は、長女の成功を願いながらも、実際の活動の冴えない様子を見て、戸惑いを覚える。
筋書きとしては以上に尽きるシンプルな話のなかに、桐野夏生氏の狂おしいまでの憤りが凝縮されている。桐野氏は何に憤っているのか。それは、「愚かさ」に対してである。大した素質がない自分を直視せずにアイドルになることを夢想し、母親が爪に火を点す生活によって必死に貯めた学資を食い潰してドサ回りを続ける長女の愚かさに対して。その愚かさを「健気な努力」と取り違えて、現実を直視せず、二人の娘に対して不平等な扱いをする母の愚かさに対して。これらすべてを認識し、腹を立てているくせに、「自分もアイドルになりたい」という欲望しか持つことのできない次女の愚かさに対して。そして、この愚かさの連鎖を成り立たしめている社会的背景、言い換えれば、それを一大ビジネスたらしめているところの、「キモヲタ」(=神様男)どもの欲望の愚かさに対して。
こうした愚かさを下流社会の「構造」によって分析することは可能であり、多くの「良心的な」社会科学者たちが現にそれを行なっている。下流化した人々がまともな将来展望を持つことができないのは、「自己責任」なのではなく、彼らが置かれた苦境のためなのである、と。あるいは、キモヲタたちの「歪んだ」欲望を、それを必然化する社会構造によって説明することも可能だろう。
重層的な支配の構造を多側面から照射し続けてきた桐野氏が、かかる「愚かさを生産する客観的構造」について認識していないわけがない。「自己責任」を問う論法が、「構造」への異議申し立てを封殺するものであることも、当然知悉しているはずである。しかし、それでもなお、桐野氏は、究極的には個人に受肉する「愚かさ」に憤り、それを問い質す。
私は、この姿勢に心から共感する。「人々が苦しんでいるのは世の中の仕組みのせいなのだから、エライ人たちはこの人たちが救われるように改良された仕組みをつくってあげなければならない」。社会科学者の処方箋とは、つまるところ、このようなものであり、「改良された仕組み」がもちろん新たな形態の支配をもたらし、新たな構造に即した別のかたちの愚かさをもたらす。桐野氏の憤りは、こうした茶番を根こそぎ吹き飛ばす。愚かさとは個人の心と肉体に宿るものである以上、誰がその責任を取ることができるのか。それができるのは、その持ち主のみである。
自らの愚かさを直視し、その愚かさを強いている構造を認識せよ――これほど厳しい、しかし真っ直ぐなメッセージを正々堂々と放っている知識人が、現代日本にどれほどいるだろうか。このメッセージを読者が受け取ったとき、かつてのプロレタリア文学が果たせなかった夢を、桐野文学は叶えるのではないか。そんな夢想を私は自分に許したくなる。